アドセンス審査は何記事で合格できる?目安と今すぐやるべき準備
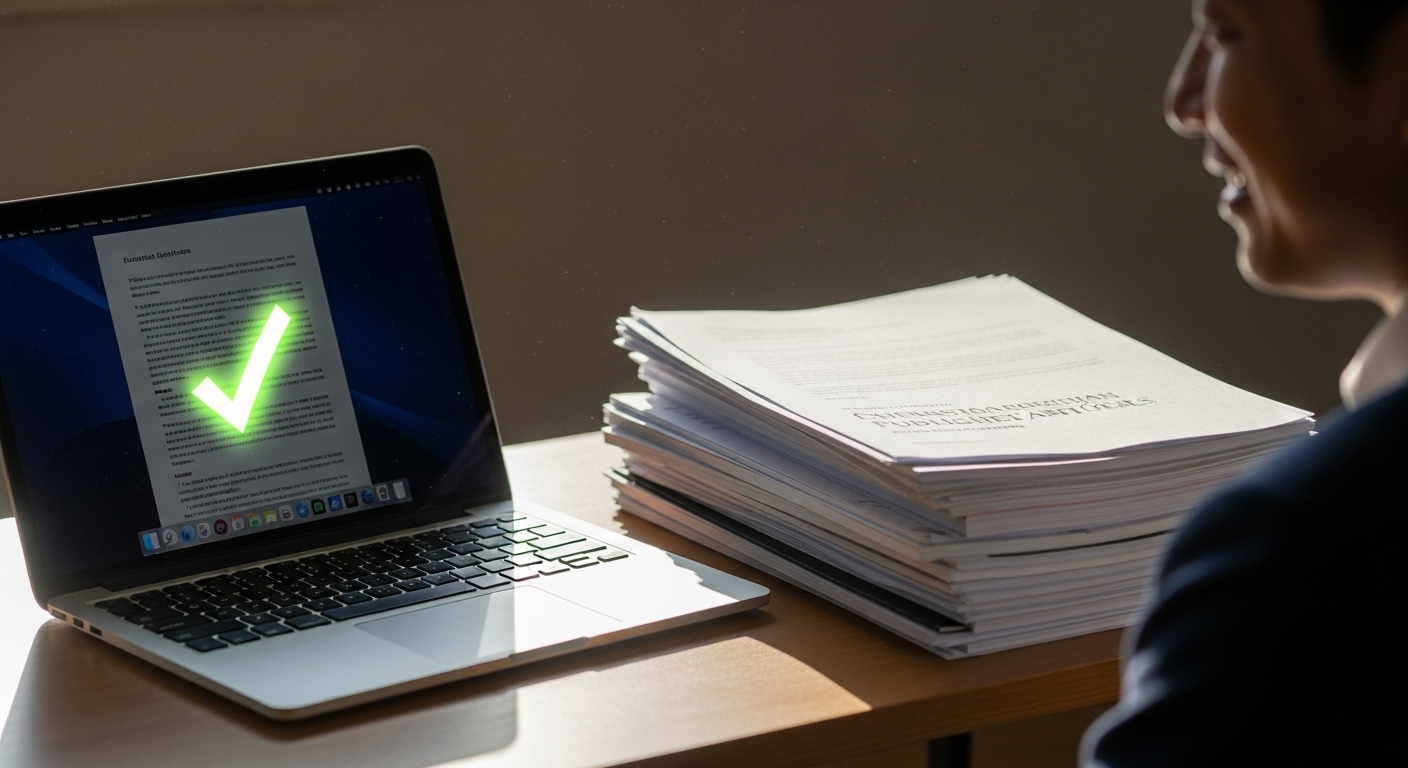
アドセンス審査は「記事数」だけで決まるわけではなく、内容の質やサイト運営の基本が整っているかが重要です。この記事では合格しやすい記事数の目安や、記事ごとの分量、審査前に整えるべきページ、落ちたときの優先対策などを具体的に説明します。申請前にチェックリストとして使える形で整理していますので、手元のサイトと照らし合わせながら読み進めてください。
アドセンスの審査に合格しやすい記事数は何記事か
審査合格に必要な明確な記事数は公開されていませんが、ある程度まとまった量の記事があると審査担当者にサイトの信頼性や継続性を示せます。多すぎても少なすぎても一概には言えないため、目安と現実の事例を合わせて判断するのが良いでしょう。
記事数だけに頼るのではなく、各記事の質やサイトの基本ページ(プライバシーポリシー、問い合わせ、運営者情報など)が整っているかをチェックしてください。特に専門性やオリジナリティがある記事が複数あると評価されやすく、記事数が少なくても合格するケースは多くあります。逆に記事数が多くても内容が薄ければ審査に通りにくくなります。
平均的な目安は10から20記事程度
多くの運営者が報告する目安は10〜20記事です。これは新規サイトとして「一定のコンテンツ蓄積がある」と見なされやすく、審査の判断材料が十分にあるからです。ジャンルや記事の長さによって前後しますが、まずはこの範囲を目標にするとよいでしょう。
記事ごとのボリュームは後述の基準を参考にしつつ、各記事が独立して読めるように質を確保してください。日々の更新頻度や過去記事の整備も含めて、サイトとしての一貫性が見える状態にすることが重要です。
少ない記事で合格した実例
記事数が5〜9記事でも合格したケースは珍しくありません。特に以下の条件がそろっている場合に起こりやすいです。
- 各記事が詳しく、情報の独自性や実用性が高い
- サイト内に運営者情報やプライバシーポリシーが完備されている
- 表示速度やモバイル対応が良好でユーザー体験が良い
少ない記事で申請する場合は、各記事が明確な目的を持ち、ユーザーの問題解決に寄与していることを強調してください。
記事数より影響が大きい要素とは
記事数より審査に影響を与える主な要素は次の通りです。
- コンテンツの独自性と質
- サイト構造とナビゲーションの分かりやすさ
- 基本ページ(プライバシーポリシー、問い合わせ、運営者情報)の有無
- 不適切な広告や著作権侵害の有無
これらが整っていると、記事数が少なくても信頼性が高く評価されます。逆に記事数が多くても、これらが欠けていると不利になります。
PVや更新頻度が与える影響
PV(ページビュー)は合格の直接要因ではありませんが、一定のアクセスがあるとサイトが実際に利用されている証拠になり、プラスに働くことがあります。更新頻度も重要で、継続的に記事を追加しているサイトは運営が継続していると見なされやすくなります。
目安としては週1回程度の更新を続けると良い印象です。ただし、更新のために質を落とすのは避けてください。更新が途切れているよりは、不定期でも質の高い更新を続ける方が評価されます。
早めに申請しても良いかの判断基準
早めに申請しても問題ない場合は次の条件が満たされているときです。
- 記事が複数(5〜10程度)あり、各記事の内容が充実している
- 基本ページが整備されている
- モバイル対応や表示速度に大きな問題がない
逆に、記事が1〜2本しかなく導線や基本ページが未整備であれば、準備を整えてから申請する方が無駄な不合格通知を減らせます。早期申請は時間短縮になることもあるため、上記条件を満たしていればチャレンジしてよいでしょう。
記事数とコンテンツの質の関係
記事数と質は単純な比例関係ではありません。少ない記事でも深く掘り下げた内容があれば高評価を得られます。逆に大量の記事が量産型であれば評価は下がります。重要なのは各記事が読者に価値を提供しているかどうかです。
質を高めるためには情報の信頼性、独自の視点、読みやすさを意識してください。検索ユーザーの意図に合う構成や適切な見出し、内部リンクで関連情報を補完することも有効です。記事数はサイトの信頼性を示す一つの指標ですが、本質的にはコンテンツの内容とサイト全体の整備が審査では重視されます。
1記事あたりの文字数の目安
1記事あたりの目安は800〜2,000文字程度が一般的です。短すぎると情報が不足している印象を与えやすく、極端に長すぎると読み手が離れる可能性があります。テーマに応じて必要な情報量を確保し、見出しや箇条書きで読みやすく整えてください。
専門的なテーマや手順を詳しく説明する記事は2,000文字前後でも問題ありませんが、基本的な紹介やニュース系の記事は800〜1,200文字程度でまとめるのが適しています。
情報の独自性を高める方法
独自性を出すには、以下の方法が有効です。
- 自分の経験や実際のデータを盛り込む
- 他の記事で触れられていない視点や切り口を加える
- 写真や図、スクリーンショットで現物を示す
- 参考元を明記して情報の信頼度を補強する
これらを組み合わせることで、オリジナル性が高まり審査での評価が上がりやすくなります。特に専門性や経験がある分野では、独自の観点を明確に示すことが効果的です。
低品質を防ぐチェック項目
記事公開前の確認項目として次をチェックしてください。
- 主張に裏付けとなる根拠があるか
- コピーや引用の扱いが適切か(引用は最小限で出典を明示)
- 誤字脱字や読みづらい表現がないか
- 内部リンクや関連記事への導線があるか
- 画像の著作権に問題がないか
これらは簡単に確認できる点です。公開後も定期的に見直して、古い情報やリンク切れを修正する習慣をつけてください。
読者の悩みを解決する構成
読者が求める情報にすばやく到達できる構成を心がけます。あらかじめ次の流れで記事を作ると読みやすくなります。
- 問題の提示(読者が抱える悩み)
- 解決策の提示(手順やポイント)
- 実例や注意点の紹介
- まとめと次の行動指針
見出しを適切に使い、箇条書きや図表で要点を整理することで、スマホでも読みやすいレイアウトになります。
審査前に整えておくべきサイトのページ
審査に臨む前に、サイトの基本ページを整えることは非常に重要です。これらは運営の信頼性を示す要素になり、審査担当者がサイトの目的を理解しやすくなります。必ず目を通して漏れがないようにしてください。
プライバシーポリシーやお問い合わせページ、運営者情報は最低限必要です。これらが未整備だと、記事の質が高くても不合格になるリスクがあります。また、表示速度やモバイル対応も事前に確認し、問題があれば改善しておきましょう。
プライバシーポリシーに入れる基本項目
プライバシーポリシーには次の項目を含めると良いです。
- 収集する情報の種類(例:Cookie、アクセス解析の情報)
- 情報の利用目的(例:サービス改善、広告配信)
- 第三者提供についての方針(広告配信事業者の利用)
- 問い合わせ先や責任者の連絡方法
- クッキーの利用と設定方法に関する案内
具体的な文言は簡潔で分かりやすく記載してください。テンプレートを使う場合でも自サイトの実態に合わせた修正を忘れないでください。
お問い合わせページの設置方法
お問い合わせページは専用フォームを設置するのが望ましいです。設置時のポイントは次の通りです。
- 名前、メールアドレス、問い合わせ内容の基本項目を用意する
- スパム対策(CAPTCHAや簡単な質問)を導入する
- 返信方針(何日以内に返信するか)を明記する
- 個人情報の取り扱いについて簡単に触れる
フォームが難しい場合はメールアドレスを明示する方法でも構いませんが、運営者と連絡が取れる状態にしておくことが重要です。
運営者情報の記載ポイント
運営者情報は信頼性に直結します。以下を記載してください。
- 運営者名(個人名や屋号)
- 代表連絡先(メールアドレス)
- サイトの目的や運営方針の簡単な説明
法人であれば会社名や所在地を明記します。個人運営の場合も可能な範囲で情報を載せると審査上有利になります。
表示速度とモバイル対応の確認
表示速度の遅さやモバイル非対応はユーザー体験を損ね、審査にマイナスです。確認ポイントは次の通りです。
- モバイルでレイアウトが崩れていないか
- 画像やスクリプトを最適化して読み込みを速くしているか
- レスポンシブデザインを採用しているか
無料ツールで簡易チェックを行い、TTC(初期表示時間)や総読み込み時間が長い場合は改善を検討してください。
不合格から合格へ 再申請時に優先する作業
不合格通知を受けたら、まずは指摘内容を冷静に読み取り、優先順位を付けて修正を進めてください。焦って全てを一度に直すよりも、審査に直接影響するポイントを優先するのが効果的です。
不合格理由は複数ある場合が多く、その中でもコンテンツの品質や基本ページの欠如がよく見られます。指摘箇所をリスト化し、修正・削除を行った後に再申請のタイミングを判断してください。
不合格通知の指摘内容の読み方
不合格通知は一般的なコメントであることが多く、具体的な記事名を挙げられない場合もあります。指摘を正確に理解するために次の点を確認してください。
- 指摘がサイト全体に関するものか、特定カテゴリーや記事に関するものか
- コンテンツ品質に関する問題か、ポリシー違反に関する問題か
- 追加で求められている対応内容があるか
可能であれば、問題になりそうな記事を絞り込み、順に見直していきます。
問題記事の修正と削除の判断基準
問題記事をどう扱うかは次の基準で判断します。
- 明らかにコピーや転載がある記事は削除または大幅に書き直す
- 情報が古く誤解を招く場合は更新するか削除する
- 内容が薄く価値が低い記事は統合して一つのまとまった記事にするか削除する
修正で対応できる場合は元のURLを維持して修正し、削除する場合はリダイレクトや404対策も考慮してください。
新規記事を追加する際の狙い目
再申請前に追加する記事は「質を高める」ことを意識してください。具体的には次のような記事が有効です。
- 自分の経験や事例を紹介する記事
- 需要があり検索されやすいテーマの深掘り記事
- 既存の弱い記事を補完する関連コンテンツ
数を増やすよりも、審査で評価されやすいコンテンツを一つずつ増やす方が効果的です。
一時的に外すべき広告やリンク
審査中は外部広告やアフィリエイトリンクが多すぎるとマイナスに働くことがあります。必要に応じて次を検討してください。
- ページ上部や本文中の過剰な外部広告を一時的に削除する
- アフィリエイトリンクが記事の主旨を損なっている場合は一時的に外す
- ポップアップや画面全体を覆う広告は審査通過まで停止する
審査合格後に段階的に戻す方法が安全です。
再申請のタイミングの見極め
再申請は「全ての重大な問題を修正した」と判断できるときに行ってください。焦って早期に再申請しても同じ理由で落ちることが多いため、チェックリストを作り、修正済みの項目を確認してから申請してください。
目安としては、主要な問題を修正してから1〜2週間程度運営を続け、アクセス状況や外部からの反応が安定しているかも見てから申請すると安心です。
合格と不合格の事例で見る違い
合格と不合格の実例を比べると、共通する違いが見えてきます。合格サイトは「信頼性」「ユーザー体験」「コンテンツの深さ」が揃っていることが多く、不合格サイトはどれかが欠けていることが多いです。具体的なポイントを把握すると、自分のサイトの改善点が分かりやすくなります。
以下では成功例と失敗例の違い、ジャンル差、流入元の影響などを解説します。自分のサイトの状況と照らし合わせて、足りない点を補っていきましょう。
短期間で合格したブログの共通点
短期間で合格したブログには次の特徴がありました。
- いくつかの高品質な記事があり、ユーザーに価値を提供している
- 必要な基本ページが整備されている
- モバイル対応と読み込み速度が良好である
- 著作権やポリシー違反がない
これらが揃うと記事数が少なくても審査で高く評価されやすくなります。特に専門性や独自体験を示せる記事は強みになります。
記事数は多くても落ちた原因
記事数が多くても不合格になる主な原因は次の通りです。
- コピーコンテンツや引用の過剰
- 情報の浅さや重複コンテンツの存在
- 必須ページの未整備
- 広告や外部リンクが過剰でコンテンツが見えにくい
記事を増やす前に既存コンテンツの質を見直すことが重要です。
ジャンル別に見た合格のしやすさ
ジャンルによって審査の難易度が若干変わります。医療や法務、金融などの専門性が求められるジャンルでは、信頼できる情報源や資格、根拠を示すことがより重要になります。
一方で趣味系やライフスタイル系はオリジナル体験や写真を活かしやすく、比較的対応しやすい傾向があります。どのジャンルでも共通して求められるのは「読者にとって有益で信頼できる情報」であることです。
SNSや流入が合否に与える影響
直接の基準ではないものの、SNSや外部流入があるとサイトが実際に利用されている証拠になります。特に再申請時に一定のアクセスがあると、運営が継続的に行われていると判断されやすくなります。
ただし、流入が多くてもコンテンツに問題があれば結果は変わりません。流入は補助的な要素と考え、まずはサイト自体の整備とコンテンツの質を優先してください。
合格に向けて今すぐ始める申請準備まとめ
ここまでのポイントをふまえて、今すぐできる準備を簡潔にまとめます。まずは基本ページを整え、記事の品質チェックを行い、不要な広告や外部リンクを見直してください。記事数は目安の範囲に収めつつ、各記事の中身を充実させることが最優先です。
再申請が必要な場合は、不合格通知を丁寧に読み取り優先度の高い修正から着手してください。審査は完璧な状態を求められるわけではありませんが、ユーザー視点での信頼性と読みやすさを意識すると通過率は上がります。まずはチェックリストを作り、一つずつ確実に整備していきましょう。









