ブログをやめる人の割合は?挫折しやすい理由と続けるための対策を詳しく解説

ブログをやめる人の割合と主な理由

ブログを始めても続かない人が多いという声をよく耳にします。ここでは、実際にどれくらいの人がブログをやめてしまうのかや、その背景についてまとめます。
ブログをやめる人の割合はどれくらいか
ブログを始める人は年々増えていますが、途中でやめてしまう人も少なくありません。実際、1年以内に更新しなくなる人の割合は70〜80%にものぼるという調査結果もあります。特に最初の3か月以内に離脱する人が多いという傾向が見られます。
また、収益化を目指してブログを始めたものの、思うような結果が出ず挫折するケースも多いです。継続している人と途中でやめてしまう人の差は、目的意識やモチベーションの持続力によるところが大きいといえます。
多くの人がブログをやめる主な理由
多くの人がブログをやめる理由として、収益やアクセス数の伸び悩み、ネタ切れ、時間が取れないといった悩みが挙げられます。特に収益化を目指している場合、期待した成果が出なければ、続ける意欲が薄れることが多いです。
ほかにも、書くモチベーションの低下や、生活の変化による時間不足なども理由として挙げられます。下記は主な理由の例です。
・収益やアクセスの伸び悩み
・ネタ切れ、アイデア不足
・時間が確保できない
・書くことへのモチベーション低下
・他の趣味や仕事に集中したい
継続できないブログの特徴
継続できないブログにはいくつか共通点があります。たとえば、明確なテーマが定まっていなかったり、無理な更新頻度を設定してしまったりすることです。これらの特徴が積み重なると、負担だけが増えて続けにくくなってしまいます。
また、成果や反応が得られないまま孤独に執筆を続けている場合も、途中でやめてしまう原因となります。短期間で結果を求めすぎず、自分なりの目標や楽しみを見つけることが継続のためのポイントです。
ブログをやめたくなる原因とその対策
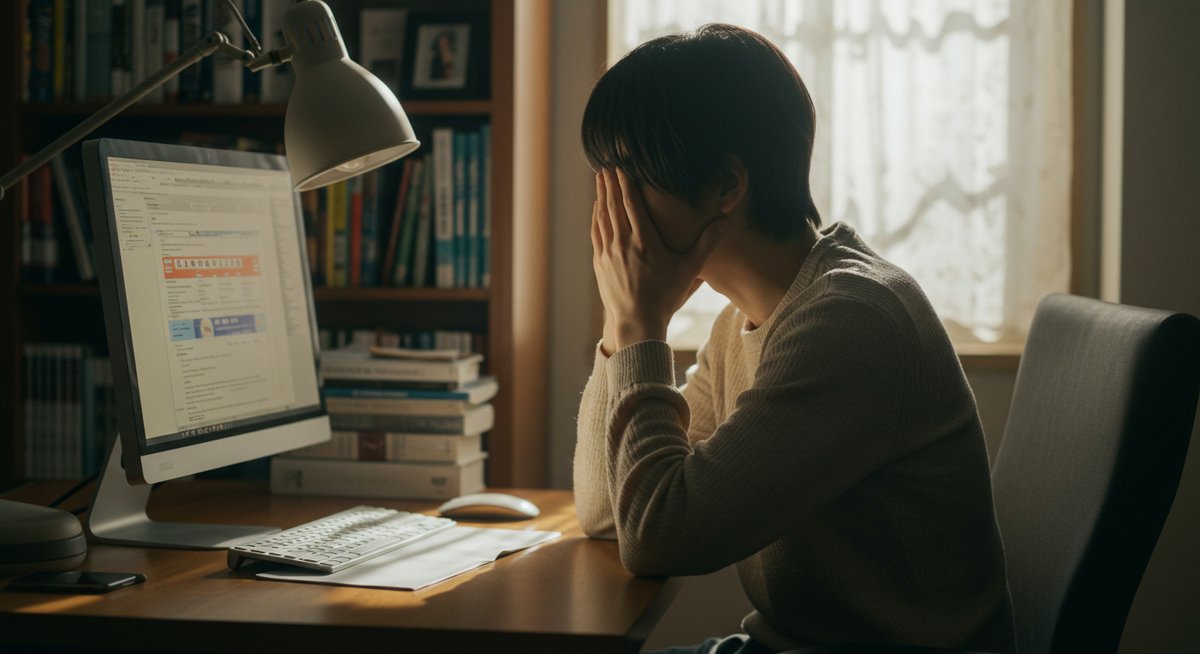
途中でブログをやめたくなるときは、ほとんどがモチベーションや、成果に対する不安が原因です。ここでは主な困りごとと、その解決方法を紹介します。
収益化やアクセス数の伸び悩みへの対処法
ブログを続けていて収益やアクセス数が思うように伸びないと、がっかりすることも多いです。しかし、ブログは結果が出るまでに時間がかかる場合がほとんどです。一時的に伸び悩んでいても、継続することで徐々に成果が見えてくることもあります。
収益やアクセス数が伸びないと感じたら、ターゲットや記事ジャンルの見直し、SNSや他の媒体との連携など、できる工夫を試してみましょう。また、短期的な数字よりも、自分が成長できているか、読者の反応がどう変わったかなど、別の視点からも達成感を見つけられると前向きになれます。
記事作成やネタ切れを乗り越える方法
記事がなかなか書けない、ネタが思いつかないと悩むことも多いです。こうした場合は、無理に新しいネタを探すのではなく、既存の記事のリライトや、自分の経験をもとにした記事を書くのも有効です。
また、以下の方法を取り入れることで、ネタ切れに強くなります。
・日々の生活や仕事で気づいたことをメモする
・読者からの質問や意見を元に記事を考える
・他のブログやニュースを参考に視点を広げる
一度立ち止まって、自分が伝えたいことや読者の役に立つ情報を整理し直すことも大切です。
時間管理や習慣化の工夫
忙しい毎日の中で、ブログの時間を確保するのは簡単ではありません。無理なく続けるためには、作業時間をあらかじめ決めておく、短い時間でもコツコツと進めるなど、時間管理が重要です。
たとえば、1日30分だけ執筆にあてる、週末だけまとめて記事を書く、という方法も効果的です。さらに、ブログを書く時間帯を決めてルーティンにすることで、無理なく継続しやすくなります。習慣化することで、「書かなければ」と思わずに自然と続けられるようになるでしょう。
ブログをやめる前に確認するべきポイント

ブログをやめてしまう前に、今一度自分の運営状況を見直すことが大切です。続けるかどうかを判断する際のチェックポイントを整理します。
目標設定やブログ運営の振り返り
ブログを始めた当初の目標や目的を忘れてしまっている場合は、いったん立ち止まって振り返ることが重要です。収益だけでなく、情報発信や記録、自己表現などさまざまな動機があったはずです。
また、これまでに達成できたことや、感じた成長も書き出してみましょう。小さな達成でも積み重ねを実感できると、やめる理由が本当に納得できるものかどうかを冷静に判断できます。
SEOやライティングの学習状況をチェック
ブログ運営では、検索エンジンで見つけてもらうための工夫や、読みやすい文章の書き方など、学ぶことがたくさんあります。今までにどれくらいSEOやライティングについて学習してきたかを確認してみましょう。
もし、十分に学んでいない場合は、基本的な知識を身につけるだけでも成果が変わることがあります。書籍やネット記事、動画講座など、自分に合った学習方法を選ぶとよいでしょう。学び直すことで、新しい気づきややる気が生まれることもあります。
データ分析や改善の取り組み状況
ブログのアクセス分析や、記事ごとの反応を見て改善につなげているかも大切なポイントです。アクセス数や流入経路、人気記事の傾向などを一度整理してみましょう。
データを活用して記事の内容や見出し、タイトルなどを修正していくと、小さな変化でも成果に結びつく可能性があります。分析や改善を定期的に行うことで、マンネリ化を防ぎ、自分でも成長を実感しやすくなります。
ブログをやめる時の正しい手順と注意点

ブログをやめると決めた場合も、後悔しないよう適切な手順を踏むことが重要です。ここでは、閉鎖に向けた準備や注意点についてまとめます。
ブログ閉鎖前にやるべき準備とバックアップ
ブログを閉鎖する前には、これまでのデータをバックアップしておくことが大切です。自分の書いた記事や画像、コメントなども保存しておくと、後から見返したいときにも安心です。
また、読者への告知も忘れずに行いましょう。突然サイトがなくなると、常連の読者が戸惑う場合があります。閉鎖日や移行先を明記したお知らせを、トップページやSNSに掲載すると丁寧です。
サーバーやドメインの扱い方と注意点
ブログを運営していたサーバーや独自ドメインも、手続きを忘れずに確認しましょう。契約をそのままにしておくと、費用が発生し続けることがあります。不要であれば解約や自動更新の停止を行ってください。
また、ドメインを手放す場合は同じアドレスを他の人が取得することもあるため、個人情報や重要な内容が残っていないか、事前にチェックしておくと安心です。
| 項目 | 注意点 | 推奨する対応 |
|---|---|---|
| サーバー | 解約漏れによる請求 | 早めの手続き、確認 |
| ドメイン | 個人情報の流出リスク | 登録情報の削除・確認 |
ブログ削除後や売却後の選択肢
ブログを削除した後も、その経験は無駄にはなりません。たとえば、今後別ジャンルのブログを始める、新しいSNSで情報発信を始めるなど、新たなチャレンジにつなげることができます。
また、もしブログが一定のアクセスや資産価値を持っている場合は、サイト売却という選択肢もあります。売却後は、利用規約や個人情報の取り扱いに注意し、必要な手続きをしっかりと行いましょう。
まとめ:ブログをやめるか続けるか迷った時の最適な判断基準
ブログをやめるか続けるか迷う瞬間は、多くの人に訪れます。その際は、自分が何を目的に始めたのか、これまでの成長や経験をしっかり振り返ることが大切です。
また、すぐに結論を出さず、数日間考える時間を持つ、身近な人や同じ経験をした人に相談するのもよい方法です。自身の状況や今後の目標に合わせて、「もう少し続けてみる」「一度休んでみる」「新しい取り組みに進む」など、無理のない選択を心がけましょう。
最終的には、ブログを通じて得た知識や経験が、今後の自分にどう役立つかを考えて判断できると、後悔の少ない決断につながります。









