Canvaのフォルダ管理で探す時間を半分にするコツ

デザインが増えてくると「どこにある?」と探す時間が積み重なってしまいますよね。ここでは、毎日の作業で迷わないように、シンプルで続けやすいフォルダ管理の方法をお伝えします。手順やコツを順番に追えば、探す時間をぐっと短くできます。まずは気軽に読み進めてください。
Canvaのフォルダ管理で探す時間を半分にする簡単ルール

フォルダを作るときの基本ルールを押さえておくと、後で探しやすくなります。まずは「分けすぎない」「名前で探せる」「テンプレートをまとめる」の三つを意識しましょう。これだけで迷子になる確率が下がります。
分けすぎないことは大切です。用途やプロジェクトごとにフォルダを作るのは良いのですが、細かく分けすぎると結局探すのが面倒になります。大きなカテゴリをまず決め、その中で必要ならサブフォルダを作るくらいにしておくと続けやすいです。
名前は統一ルールを決めると便利です。日付や用途、クライアント名を組み合わせておくと検索で引っかかりやすくなります。テンプレートは一箇所にまとめ、チームが迷わないようにしておくと作業が早くなります。
共有については権限を決めておくと無駄な編集や混乱を避けられます。まずは一週間だけルールを試して、使い勝手を見ながら調整していくと定着します。
フォルダは用途ごとに最小限に分ける
フォルダはたくさん作るより、用途で大きく分けるのが続けやすいです。例としては「ブランド素材」「SNS投稿」「キャンペーン」「社内資料」など。まずは5〜7個くらいを目安にします。
サブフォルダは必要最低限にしましょう。例えばSNSなら「投稿」「ストーリー」「広告」のように、よく使う分け方だけ作っておくと探しやすいです。細かい分類はタグや検索に頼ると管理が楽になります。
フォルダ構成はチームで共有している場合、全員に分かりやすい名前にしておくことが重要です。略語や個人だけがわかる命名は避けてください。ルールは短くまとめてドキュメントに残しておくと、新しいメンバーも迷いません。
フォルダが増えすぎた場合は定期的に見直しをしましょう。半年ごとにいくつあるか把握して、使われていないものは整理する習慣をつけると、常に見つけやすい状態を保てます。
名前付けは日付と用途を組み合わせる
ファイルの名前付けルールを決めると検索がぐっと楽になります。基本は「YYYYMMDD_用途_クライアント」のように並べると、日付順に並び探しやすくなります。
用途は短い言葉で統一しましょう。例えば「SNS」「LP」「チラシ」といった具合です。クライアント名やプロジェクト名は省略せずに入れると、複数案件が混ざっても見分けがつきます。
バージョン管理は「v1」「v2」のように末尾につけるのがおすすめです。最終版だけを残す運用にするか、履歴を残すかはチームで決めておくと混乱が少なくなります。
検索を活用するために、キーワード順を揃えることも重要です。日付を先頭にすると並び替えがしやすく、用途を次に書くことで探す時間が短くなります。覚えやすいルールをチームで共有しておきましょう。
テンプレート用フォルダを必ず作る
テンプレートは一箇所にまとめて管理すると便利です。頻繁に使うレイアウトや素材はフォルダに集めておくと、同じ作業を何度もやらずに済みます。
テンプレート内でもカテゴリを分けるとさらに使いやすくなります。例:SNS、メール用、プレゼン用など。誰が見ても分かる命名にしておくと、慌てずに選べます。
テンプレートの更新ルールを決めておくと古いデータが残りにくくなります。更新時には日付や担当者名を記載したり、旧バージョンはアーカイブフォルダに移動すると安心です。
共有テンプレートは権限を絞ると誤操作を防げます。編集を許可する人を限定し、ほかの人はコピーして使うだけにすると安全です。これだけで作業のムダが減ります。
共有は権限で役割を決める
フォルダ共有時には「編集」「閲覧」など権限を明確にしておきましょう。誰でも編集できる状態だと上書きや削除のリスクが高まります。
役割ごとに権限を設定するのがおすすめです。デザイン担当は編集、確認者は閲覧やコメントのみ、といった具合に分けると運用がスムーズです。
共有範囲は最小限に留めるとセキュリティ面でも安心です。外部パートナーには必要なフォルダだけ共有し、期限付きでアクセスを許可すると管理が楽になります。
権限の変更やメンバーの追加・削除は定期的に見直すと安心です。放置すると不要な人がアクセスできる状態が続くので注意してください。
まずは一週間で運用を試す
新しいルールは長く続けるために、短い期間でまず試してみましょう。一週間だけルール通りに運用して、使いにくい点をメモすると改善しやすいです。
試用期間中は気づいた点を全員で共有しましょう。小さな不便を早めに直すことで、最終的に使いやすい管理に近づけます。完璧を目指さず、少しずつ改善するのが続けるコツです。
一週間の結果をもとに、フォルダ名や権限を微調整してください。運用が決まったら簡単なガイドを作成して、新しく入った人でもすぐに分かるようにしておくと安心です。
Canvaでのフォルダ作成とデザイン移動の手順

ここではフォルダの作成からデザインの移動まで、順を追って説明します。画面の操作に自信がなくても大丈夫。手順に沿ってやれば短時間で整理できます。
新しいフォルダを作る手順
Canvaで新しいフォルダを作るのはとても簡単です。まずはサイドメニューの「フォルダ」から「新しいフォルダを作成」を選びます。
フォルダ名を入力する際はルールに沿った名前にしてください。作成後、必要なら説明やタグを付けておくと探しやすくなります。チームで使う場合は共有範囲を設定しておくと安心です。
フォルダの色やアイコンが設定できる場合は、一目で分かるようにしておくと視認性が上がります。作成後すぐに中身が空でも問題ありません。あとでデザインを移すだけで整理が完了します。
デザインをフォルダへ移す方法
デザインを移すときは、デザイン一覧から該当のデザインを選び、フォルダへドラッグ&ドロップするか、オプションメニューから「移動」を選びます。
複数のデザインを選択して一括で移動することも可能です。移動後はフォルダ内で順番を並べ替えると見つけやすくなります。移動先が間違っても元に戻せるのでまずは移してみましょう。
移動の際に名前を整えておくと、後から検索しやすくなります。移動直後にチェックする習慣をつけると、整理を継続しやすくなります。
スマホからのフォルダ操作の流れ
スマホアプリでもフォルダの作成やデザイン移動は可能です。アプリを開いて「フォルダ」タブをタップし、新規作成や編集を行います。
デザインを長押しすると選択モードになり、移動や共有ができます。移動の手順はPCとほぼ同じなので、外出先でも整理できます。画面が小さいぶん、名前は短めにすると表示が見やすいです。
外出先で一時的に整理したいときや、急ぎで共有する必要があるときに便利です。操作が不安な場合は最初にテストで一つだけ移してみると安心です。
複数デザインをまとめて移動するコツ
まとめて移動したいときは一覧画面でチェックボックスを使って複数選択してください。一度に移動できるので手間が減ります。
選択後にフォルダへドラッグするか、移動メニューから移動先を選ぶとまとめて処理できます。移動前に名前やタグを見直すと後で探しやすくなります。
大量にある場合は日付や用途でフィルターをかけ、まとまりごとに移すと作業効率が高まります。移動後にフォルダの中身を確認して、抜けがないかチェックする習慣をつけましょう。
フォルダ削除と復元の手順
不要になったフォルダは削除できますが、復元が可能な期間がある場合は慌てずに対応できます。削除前に中身を確認し、必要なら別フォルダへ移してから削除してください。
復元はゴミ箱や削除済みアイテムの画面から行います。復元できる期間はサービスによって異なるので、早めに操作するのが安全です。
完全削除すると復元ができなくなることがあるため、本当に不要か確認してから実行しましょう。チームで使っている場合は、削除前に関係者に確認するルールを作るとトラブルを避けられます。
素材やテンプレートを整理してすぐ見つける方法
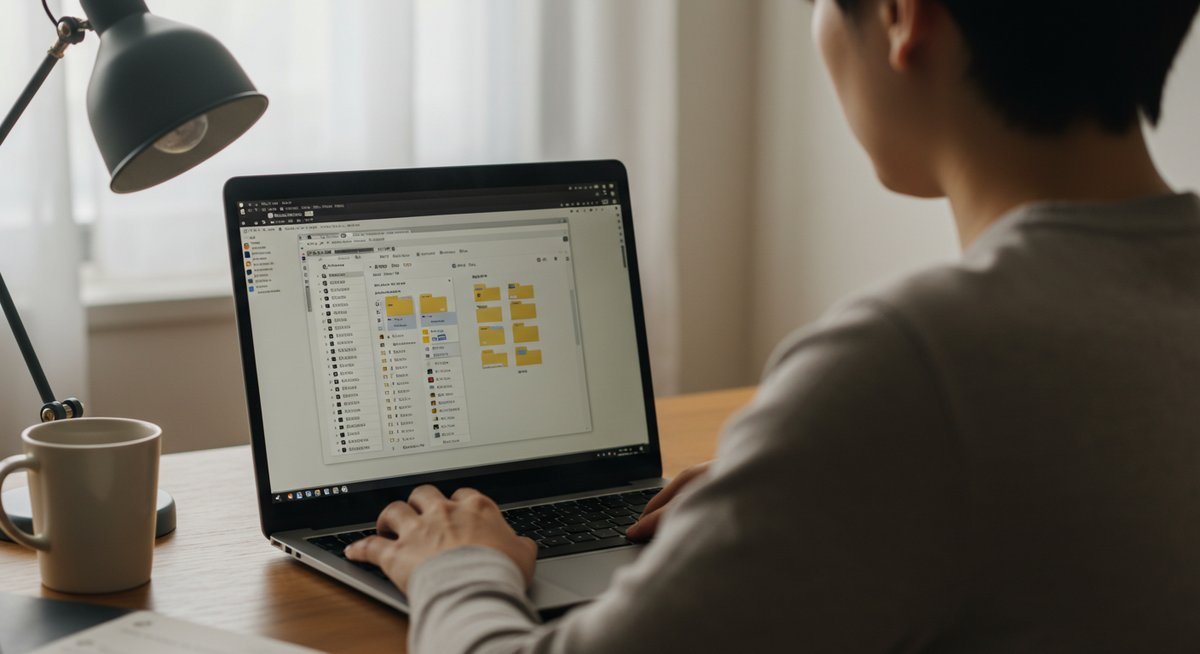
素材やテンプレートは散らばりやすいので、見やすく集める工夫が重要です。いいねやフォルダの使い分け、管理のしかたを押さえておくだけで検索の時間がかなり減ります。
いいねとフォルダの使い分け
気に入った素材は「いいね」で素早く保存できますが、長期管理にはフォルダが向いています。まずはお気に入りに入れておき、後で整理してフォルダに振り分ける流れにすると負担が少ないです。
いいねは一時的な保管場所、フォルダは整理済みの保管場所と区別すると分かりやすくなります。頻繁に使う素材はテンプレートフォルダに入れておくと見つけやすいです。
定期的にお気に入りを見直し、使わないものは削除する習慣をつけると量が増えすぎません。便利に使い分けて探す時間を減らしましょう。
素材をフォルダに保存するやり方
素材を見つけたら、詳細画面から「保存」や「フォルダに保存」を選んで移動します。フォルダ名を付けるときは用途別に分けておくと後で探しやすいです。
画像やイラスト、アイコンごとにフォルダを分けるのも有効です。必要に応じて色やテーマ別に分類すれば、デザイン作業が速くなります。
保存したらすぐに確認しておくと、保存先の混乱を防げます。使う頻度が高いものは上位階層に置いておくとアクセスが早くなります。
フォルダ間で素材を移す方法
フォルダ間の移動はドラッグ&ドロップや移動メニューから可能です。大量に移す場合は一括選択を活用すると効率的です。
移動の際にフォルダ名を見直し、重複しているものがあれば統合しておくと管理が楽になります。移動後は代表的なサムネイルを確認し、正しいフォルダに入っているかチェックしてください。
整理中は作業ログを簡単に残しておくと、元に戻すべきものが明確になります。チームで作業する場合は事前に知らせておくと誤操作を防げます。
有料素材の管理方法
有料素材は使用権やライセンスが関わるため、専用フォルダで管理すると安心です。ライセンス情報や購入日、利用範囲をメモしておくと後で確認がしやすくなります。
チームで共有する場合は、有料素材フォルダへのアクセス権を限定し、不適切な利用を防ぎましょう。購入履歴をスプレッドシートなどで管理しておくと追跡が簡単です。
ライセンスが切れるものや利用期限がある素材はリマインダーを設定しておくと、期限切れで困ることが減ります。
テンプレート専用フォルダの作り方
テンプレート専用フォルダは使う場面ごとに分けると探しやすいです。SNS、広告、メール、資料などで分けておくと、使うときに迷いません。
テンプレートにはバージョンや更新日を入れておくと、どれが最新版か一目で分かります。テンプレートの使用方法を簡単にメモしておくと、他のメンバーも使いやすくなります。
定期的にテンプレートを見直し、不要になったものはアーカイブしておくとフォルダがすっきりします。共有テンプレートは編集権限を限定しておくと安全です。
チームでの共有とアクセス権の決め方
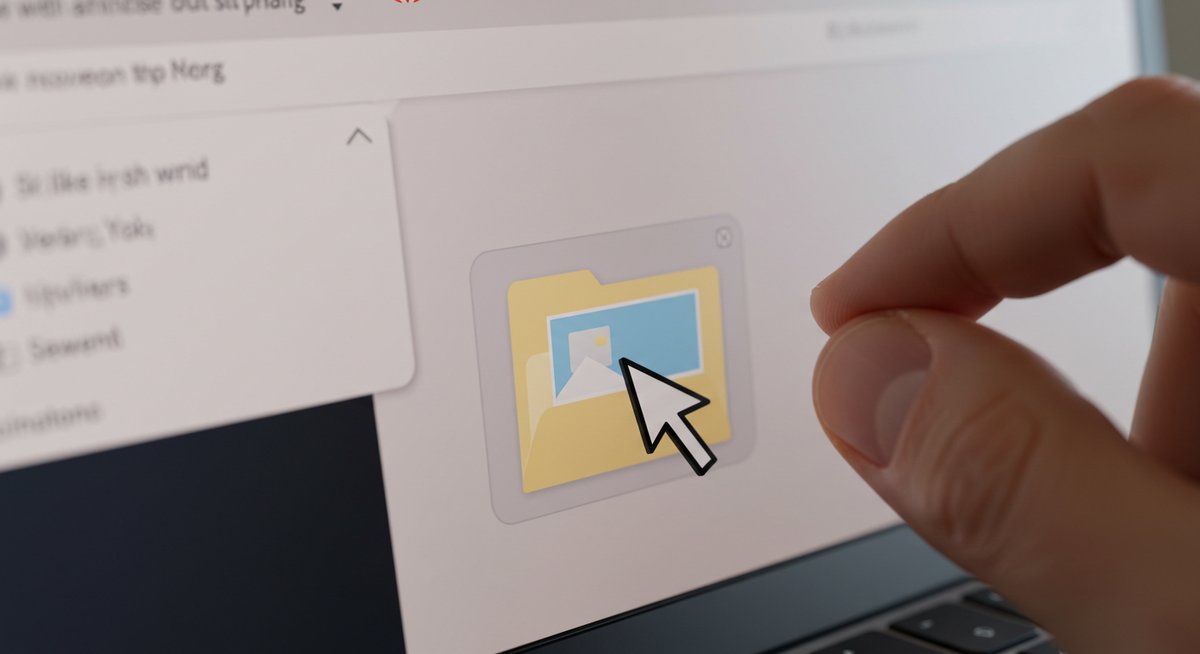
チームで使うときは最初にルールを決めておくとトラブルが少なくなります。誰が何をできるかを決め、運用ルールを守る習慣をつけてください。
フォルダ共有の範囲を設定する
共有範囲は必要最小限にしましょう。プロジェクト単位や部署単位で共有範囲を分けると、関係者だけがアクセスできます。
外部パートナーには期限付きアクセスや限定フォルダを使うと安全です。共有時には目的や使い方を簡単に伝えておくと誤用が減ります。
共有範囲は定期的に見直し、不要なアクセス権が残っていないか確認するようにしましょう。セキュリティと利便性のバランスを保つことが大切です。
メンバー招待の手順
メンバー招待はフォルダの共有メニューから行います。招待時には役割(編集・閲覧など)を明確に設定してください。
招待メールにフォルダ構成や使い方の簡単な説明を添えると、オンボーディングがスムーズになります。大量に招待する場合はテンプレートメッセージを用意しておくと便利です。
招待後はアクセス状況を確認し、不要になれば速やかに権限を外す運用を決めておくと安全です。
編集権限と閲覧権限の違い
編集権限はデザインの追加・削除・編集が可能で、閲覧権限は見るだけの状態です。誤って消してしまうリスクを減らしたいフォルダには閲覧権限を使ってください。
コメントや提案だけを許可したい場合はコメント権限を活用すると良いです。権限を細かく設定することでチーム内の役割が明確になります。
権限の設定は定期的に見直し、プロジェクトのフェーズに応じて変更する習慣をつけておくとトラブルが減ります。
共同編集時の運用ルール
共同編集では命名ルールや保存ルールを全員で共有しておくことが重要です。作業中のファイルにはバージョン名をつけるなど、混乱しない工夫をしましょう。
同じデザインを同時編集する場合は通知やコメントでやり取りを行い、上書きのリスクを減らします。編集履歴を確認する方法を全員が知っていると安心です。
作業が終わったら最終版を「完成」フォルダへ移すなど、流れを決めておくと次に探す人が困りません。
トラブルを防ぐチェック項目
トラブルを防ぐためのチェック項目を用意しておくと安心です。主な項目は以下のとおりです。
- フォルダ名とファイル名がルール通りか
- 権限設定が適切か
- 有料素材のライセンス情報が記録されているか
- 古いバージョンがアーカイブされているか
チェックは定期的に行い、問題があれば改善していきましょう。ちょっとした確認で大きな混乱を避けられます。
自動化とテンプレートで作業を減らす方法
自動化は最初に設定が必要ですが、うまく使えば日々の作業を大きく減らせます。テンプレートと連携ツールをうまく使って、手作業を減らしましょう。
テンプレートから自動で新規作成する
テンプレートを用意しておけば、新しいデザインはテンプレートから素早く作れます。定型のレイアウトやフォント、色をテンプレートに入れておくと作業が統一されます。
テンプレートは用途別に分け、最新版だけが目につくように配置しておくと使いやすいです。テンプレートの更新手順を決めておくと古い版を使うミスが減ります。
チームで使うときはテンプレートを「コピーして使う」運用にすると原本が守られて安全です。
ZapierやMakeでフォルダを連携する
ZapierやMakeを使うと、別サービスとの連携が可能です。例えばフォーム送信で自動的にフォルダを作ったり、ファイルを移動するトリガーが作れます。
連携の設定は初めに工夫が必要ですが、一度作れば手作業が減ってミスも減ります。どのイベントで何を自動化するかを明確にしてから設定しましょう。
外部サービスと連携する際は、アクセス権やセキュリティを確認してから使うことをおすすめします。
Notionやスプレッドシートと同期する方法
フォルダ構成や素材のメタ情報をNotionやスプレッドシートで管理すると、検索や一覧がしやすくなります。Canvaと直接同期できるツールもあるので、状況に合わせて活用してください。
一覧にはファイル名、用途、担当者、ライセンス情報などを入れておくと便利です。更新のルールを決めておけば、どこに何があるかすぐに分かります。
チームで共有するテンプレートを管理する台帳として使うと、探す時間がさらに減ります。
フォーム送信でフォルダを作る流れ
フォームを使ってプロジェクト申請を受け付け、その内容で自動的にフォルダを作ると手間が省けます。フォームにはプロジェクト名や担当者、納期を入れてもらいましょう。
送信された情報を元にZapierなどでフォルダを生成し、必要なテンプレートをコピーする流れにすれば初期設定がスムーズです。申請時にタグを付けてもらうと分類が簡単になります。
この仕組みはプロジェクトが増えても秩序を保つのに役立ちます。設定後は定期的に動作確認をしてください。
自動化の動作を確認する方法
自動化は誤動作が起きないように定期的にチェックすることが大切です。テスト用データで動作確認を行い、ログを確認して問題がないか見てください。
問題が見つかったらすぐに修正して、変更内容をチームに共有しましょう。自動化の担当者を決めておくとトラブル対応が速くなります。
自動化は便利ですが、完全に任せきりにせず時々見守ることが長持ちのコツです。
今日から使えるCanvaフォルダ管理のチェックリスト
最後に、今日から使えるチェックリストを用意しました。毎日または毎週の習慣にして、整理を続けてください。
- フォルダ数が多すぎないか確認する
- 新しいフォルダはルールに沿った名前にする
- デザインは作成後すぐに移動する習慣をつける
- テンプレートフォルダを見直す(最新版が置かれているか)
- 有料素材は専用フォルダで管理し、ライセンスを記録する
- 共有権限を定期的にチェックする
- 自動化のログを週に一度確認する
- 一週間の運用で気になった点をメモして改善する
このチェックリストを手元に置いておけば、少しの手間でフォルダが散らからず、探す時間がずっと短くなります。まずは一つずつ取り入れてみてください。









