Canvaで見開きを失敗なく作るコツ|短時間で仕上げる手順と入稿チェック

冊子やカタログ、フォトブックを作るとき、見開きの作り方を知っていると仕上がりが格段に良くなります。ページごとのつながりや余白の取り方、文字や画像の配置を押さえておけば、印刷での失敗を減らせます。ここではCanvaを使った手順や注意点を、やさしい言葉で順を追って解説します。初めての方でも落ち着いて作業できるよう、段取りとチェックポイントを中心に紹介します。
Canvaで見開きの作り方を短時間で学んで失敗を防ぐ

見開きを作るときは、左右のつながりと余白の取り方が重要です。ページ中央で切れてしまう内容を避け、写真や文字がはみ出さないように設計します。Canvaの機能をうまく使えば、効率よく整ったレイアウトが作れます。ここでは全体の流れをつかめるように、準備から最終チェックまでのポイントをまとめます。作業は順序立てて進めると安心です。
作る前に決めるべきこと
まず何を作るか、ターゲットや用途を明確にしましょう。配布方法や部数、製本方法(中綴じ・無線綴じなど)で最適なページ順や余白が変わります。写真中心かテキスト中心かでページ構成の流れも決めやすくなります。
次に、用紙サイズや仕上がりの向き(横開きか縦開きか)を決めます。これでキャンバスの作り方が決まるので、ここで迷わないようにしましょう。大きさが決まったら、ページ数や表紙の有無も確定させます。
デザインの雰囲気、フォントやカラーパレットをあらかじめ決めておくと、後半で迷わず統一感を出せます。使う写真や素材は最初に整理しておくと、読み込みや差し替えがスムーズです。
最後に、印刷会社の入稿規定や仕上がりの条件を確認しておくと、後からサイズやトンボの再調整が不要になります。余裕をもって準備すると安心です。
用紙サイズと塗り足しの目安
用紙サイズは完成サイズ(仕上がり寸法)で決めます。冊子の見開きなら、左右両ページを合わせた幅で考えると配置がわかりやすくなります。印刷でカットされることを踏まえておきましょう。
塗り足しは通常3mmを確保するのが一般的です。背景や画像がページ端まで届くデザインの場合は、トリムラインより外側に余白を残さず塗り足してください。文字や重要な情報は、端から安全域を取って配置することを忘れずに。
解像度や裁ち落としを考えると、画像は余裕のあるサイズで配置したほうが安心です。仕上がりイメージを印刷会社の仕様に合わせて調整しておくと、差し替えや再入稿の手間が減ります。
見開きを単ページで作る理由
左右のページをつなげたデザインはきれいに見えますが、入稿時には単ページごとに扱われることが多いです。印刷や製本のプロセスでページが分かれて扱われるため、最終的には単ページで問題なくつながるように作る必要があります。
また、単ページで作ることでページ順やノンブルの管理がしやすくなります。差し替えや修正が発生したときにも、対象ページだけを直せば済むので作業が速く終わります。
ページを単体で確認できると、裁ち切りやセンターのずれを発見しやすくなります。これにより印刷後の仕上がりをイメージしやすくなります。
PDFでの書き出しで確認する項目
PDFに書き出したら、まずページ順とページ数が合っているかを確認します。次にトンボや塗り足しが正しく反映されているかをチェックします。
色については、モニターと印刷で差が出ることがあるので、可能なら印刷用設定で書き出して確認しましょう。フォントが埋め込まれているか、文字化けや置き換わりがないかも重要な確認項目です。
また、解像度の低い画像がないか、ズレやはみ出しがないかもチェックしてください。問題が見つかったら元ファイルに戻って修正し、再度書き出します。
印刷前の確認チェックリスト
印刷前には次の項目を順に確認してください。
- 用紙サイズとページ順が合っているか
- 塗り足し(3mm)があるか
- 重要な文字が安全域内に収まっているか
- 画像の解像度が十分か(後ほど解説します)
- フォントが埋め込まれているか
- トンボや裁ち落としの表示が正しいか
チェックは複数回行うと安心です。誤りが少しでもあると、印刷後に修正が大きな手間になります。落ち着いて一つずつ確認しましょう。
制作前に整えておく設定
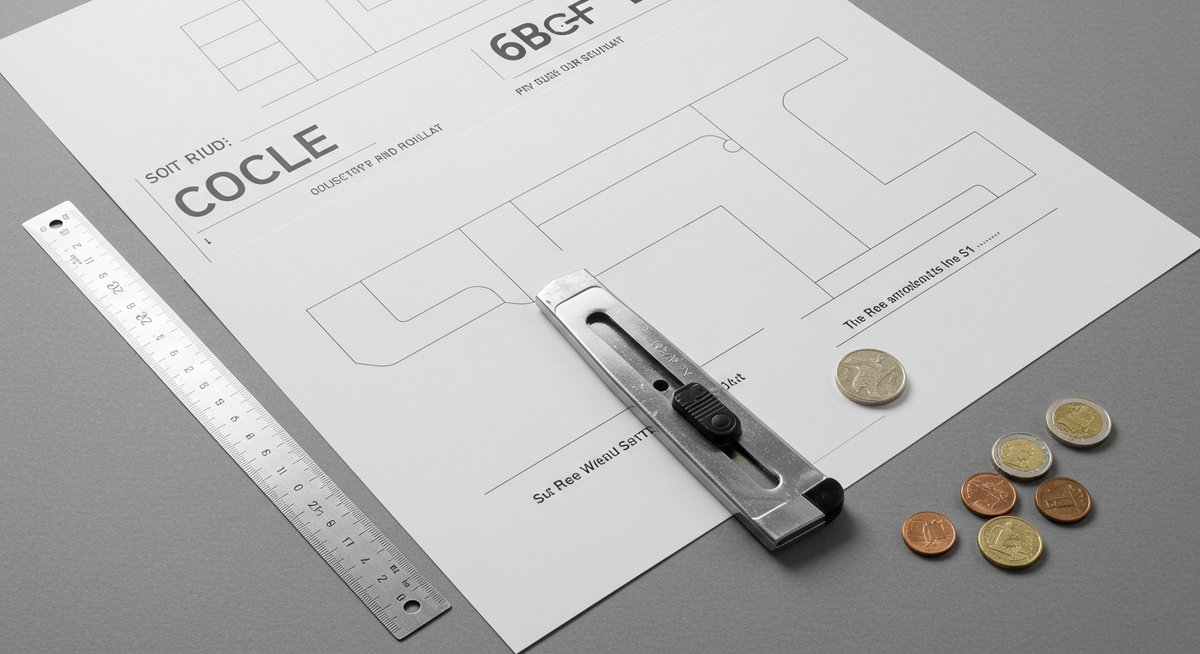
制作を始める前にCanvaでの基本設定を整えておくと、作業がぐっと楽になります。サイズや単位、ページ数の考え方など、後戻りを減らすための準備をしておきましょう。ここでは失敗を避けるための設定項目を順に説明します。
用紙サイズを完成サイズで決める
まずは仕上がりの用紙サイズを決めてください。冊子の仕上がり寸法でキャンバスを作ると、カットやマージンの調整がしやすくなります。見開きで作る場合は左右を合わせた幅で考えるのではなく、基本は単ページの完成サイズで考えるとトラブルが少ないです。
印刷会社の規格や希望する仕上がりに合わせて設定することで、後でサイズ変更が必要になる手間を避けられます。余白や塗り足しの設定もこの段階で想定しておきましょう。
単位をmmに変更する方法
Canvaではデフォルトがpx表示のことが多いので、mmに変えて扱うと印刷向けの作業が楽になります。画面上の設定やキャンバスのオプションから単位を切り替えられる場合があるので、設定画面を確認してください。
mm単位にすることで、塗り足しやトンボの寸法を正確に扱えます。これにより印刷会社とのやり取りもスムーズになります。慣れるまでは実際の定規と照らし合わせると安心です。
ページ数は4の倍数にする理由
冊子の多くは製本工程で折り加工を行うため、ページ数を4の倍数にする必要があります。これを無視すると、白紙ページができたり製本トラブルの原因になります。最初にページ数を決めるときは、このルールを守っておきましょう。
もしページが足りない場合は、差し込みページや奥付で調整する方法があります。余裕をもってページを設けると、後から内容を足しやすくなります。
塗り足しは3mmを確保する
印刷・裁断時のズレを見越して、端まで伸ばす背景や画像は外側に余白をつけず、トリムラインよりさらに3mm外側まで伸ばしておきましょう。これが塗り足しです。
文字やロゴなど重要な情報は塗り足しエリアに入れないでください。トリム時に切れてしまう可能性があります。デザインは中心寄りに配置して、安全域を確保しておくのが大切です。
画像解像度は300dpiを目安に
印刷向けの画像は高解像度が求められます。目安として300dpiを意識しておくと、細部まできれいに出力できます。スマホやウェブ用の小さい画像をそのまま使うと、印刷で粗く見えることがあります。
大きな写真を縮小して使う場合は比較的安全ですが、拡大して使うのは避けてください。必要に応じて写真のサイズやトリミングを調整しておくと安心です。
フォントの埋め込み可否を確認する
使用するフォントが印刷用PDFに埋め込めるか確認してください。埋め込み不可のフォントは別のフォントに置き換わることがあり、レイアウトが崩れる原因になります。Canva内のフォントは通常問題なく埋め込まれますが、外部フォントをアップロードした場合は規約や埋め込み設定を確認しましょう。
埋め込み不可の可能性がある場合は、一覧にある互換フォントに差し替えると安心です。
Canvaでレイアウトを作る手順

ここからは実際の作業手順です。キャンバスの準備からガイドの設定、画像や文字の扱い方までをわかりやすく説明します。手順を順番に行えば、トラブルを減らしてスムーズに進められます。
カスタムサイズでキャンバスを作る
Canvaで新規作成する際は「カスタムサイズ」を選び、先に決めた完成サイズを入力してください。向き(横開き/縦開き)もここで設定します。塗り足し分はキャンバスに含めず、別でガイドを引く方法がおすすめです。
ページごとにキャンバスを作るため、単ページのサイズで設定することを忘れないでください。これにより、入稿時のトラブルを避けられます。
見開きは単ページで順番に作る
見開きのつながりを確認しながら作りたいときでも、最終的には単ページで順番に作業します。左右のつながりを考えながらデザインしたら、ページを分けて作っていきましょう。
ページが増える場合はテンプレートの複製やページの並び替え機能を使うと効率的です。順番を入稿用に整えてから書き出すと間違いが少なくなります。
ガイドを引いて安全域を確保する
Canvaではガイド線を使って安全域を確保しましょう。中心やマージン、塗り足しラインをガイドで表示すると、文字や重要な要素が切れにくくなります。特にセンターライン付近の要素は注意が必要です。
ガイドを元に要素を配置すると、ページ間のつながりも自然になります。画面上で確認しながら微調整してください。
画像はフレームでサイズを揃える
画像をフレームに入れると、トリミングや位置調整がしやすくなります。複数の写真を同じサイズで揃えたいときは、同じフレームを複製して取り替えるだけで統一感が出ます。
画像の余白や配置もフレームで管理すると、後から差し替えたときにズレが少なくなります。解像度に注意しながら使ってください。
文字は読みやすさを優先して調整する
本文や見出しの文字は読みやすさを優先してサイズや行間を調整してください。ページの流れを止めないように、改行や段落の取り方にも気を配りましょう。
太字や色の使い分けで視線を誘導すると読みやすくなりますが、過度に装飾しないでバランス良く配置することが重要です。
テンプレートや複製で作業を効率化する
Canvaのテンプレートやページ複製機能を活用すると制作が速くなります。似た構成のページはテンプレートをベースにすることで統一感が保てます。
複製してからテキストや画像を差し替えると、余分な調整を減らせます。作業の最後に全体を見直して微調整を行ってください。
印刷用データの書き出しと入稿の流れ

デザインが完成したら、印刷用データの書き出しと入稿の手順に沿って進めます。書き出し設定や入稿規定を守ることで、仕上がりのトラブルを減らせます。ここでは順番に注意点を示します。
PDFでダウンロードする手順
Canvaで「ダウンロード」→「PDF印刷(高品質)」を選んで書き出します。塗り足しやトンボのオプションがあればチェックを入れてください。複数ページを一括でPDFにする際は、ページ順に気を付けて書き出しましょう。
ダウンロード後はPDFビューアで順番や表示崩れがないかを必ず確認してください。
塗り足しとトンボを設定する方法
書き出し時に塗り足し(bleed)とトンボ(crop marks)のオプションを有効にします。これにより印刷会社が裁断しやすくなり、端のズレを最小限にできます。設定が無い場合は、キャンバス上で余裕を見て配置してから書き出してください。
トンボや塗り足しは印刷の基準となるため、正しく反映されているかを確認することが重要です。
フォントが埋め込まれているか確認する
PDFを書き出したら、フォントが埋め込まれているか確認します。埋め込まれていないと別フォントに置き換わり、レイアウトが崩れることがあります。ビューアのプロパティや印刷会社からの確認でチェックしてください。
埋め込み不可のフォントを使っている場合は、使用するフォントを変更するか、印刷会社と相談して対応を決めてください。
RGBとCMYKで色が変わる点に注意する
画面はRGB表示が基本ですが、印刷はCMYKで仕上がります。色の再現に差が出ることがあるため、特に鮮やかな色やグラデーションは注意が必要です。印刷会社のカラープロファイルに合わせるか、試し刷りで色味を確認すると安心です。
色の違いを抑えるには、できるだけ落ち着いたトーンを選ぶと失敗が少なくなります。
ページ順とノンブルの付け方
PDFは印刷会社がそのまま製版することが多いので、ページ順を入稿仕様に合わせて並べておきましょう。ノンブル(ページ番号)は見やすい位置に配置して、表紙や裏表紙の有無に応じて調整します。
見開きで見せたい写真やデザインがある場合は、見開き構成が崩れないように中央付近の要素を避けて調整してください。
印刷会社の入稿規定を必ず確認する
入稿前に印刷会社のデータ規定を確認してください。受け付けるファイル形式や塗り足しの指定、フォントの扱い、カラーモードなど詳細は会社によって異なります。規定に沿うことで再入稿や追加料金のリスクを減らせます。
不明点があれば事前に問い合わせて確認すると安心です。
試し刷りで色とトリミングを確認する
可能であれば試し刷りを依頼して、色味とトリミングを確認してください。画面と印刷では違いが出やすいので、実物で最終チェックを行うと安心です。
試し刷りによって微調整が必要な箇所が見つかることがあるため、余裕を持ってスケジュールを組んでおくとよいでしょう。
Canvaで見開きを作るときに覚えておくこと
見開きを作るときは、ページのつながりと安全域の確保を常に意識してください。左右のデザインが自然につながりつつ、重要な情報が裁断で失われないように配置することがポイントです。
作業は順序だてて進め、書き出し前に必ずPDFで全体を確認しましょう。印刷会社の規定に従って入稿すれば、仕上がりのズレやトラブルを減らせます。落ち着いて一つずつチェックしていけば、満足できる冊子が作れます。









