会社のブログを書きたくない時の原因とやる気を高める具体策
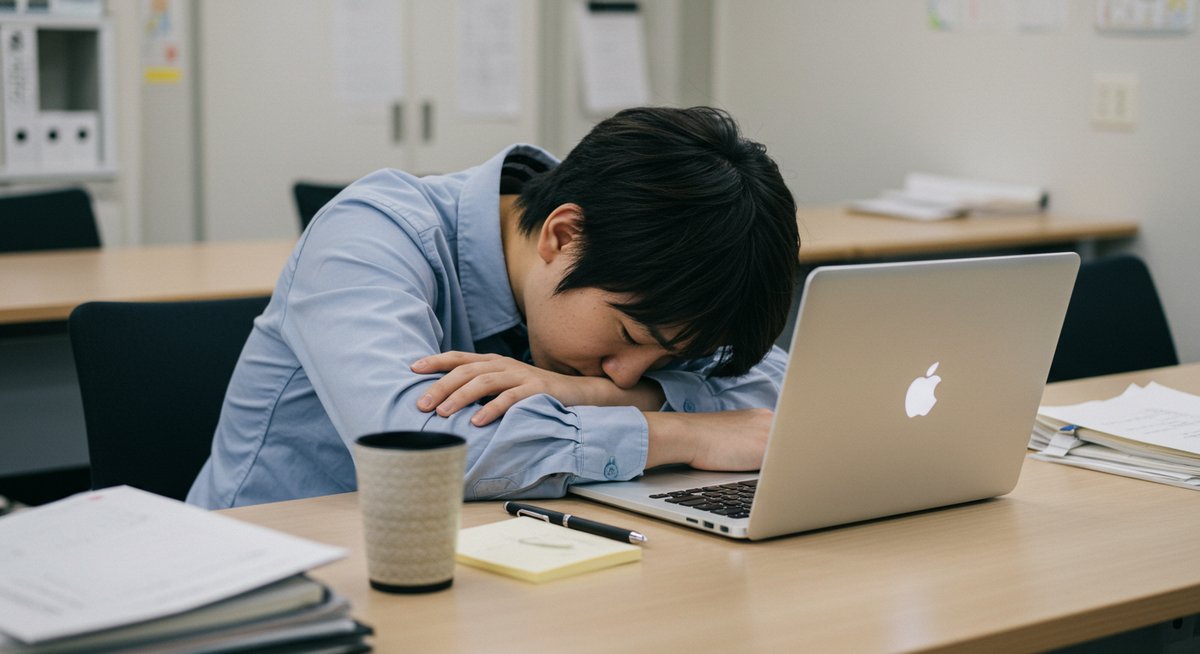
会社のブログを書きたくないと感じる主な理由

会社のブログ執筆に消極的になる理由は、人や組織によってさまざまです。ここでは代表的な悩みやストレスの要因について解説します。
経営層と社員の温度差によるモチベーションの低下
経営層が意欲的に推進しても、現場の社員は「なぜ自分たちが書くのか」と疑問を感じることがあります。この温度差が続くと、どうしてもモチベーションが下がりがちです。
経営層は「会社の認知度アップのため」と考えていても、社員一人ひとりは日々の業務に追われており、ブログ執筆が負担に感じられる場合があります。結果として、ブログが「やらされ感」のある業務になり、前向きな気持ちで取り組めなくなります。
この違いを埋めるには、経営層がブログの目的や期待する効果をわかりやすく伝え、社員の声もきちんと拾い上げることが大切です。
業務との関連性を見いだせないことがストレスに
ブログを書くことが普段の業務と直接関係しないと感じると、社員はなぜ自分がやらなければならないか分からず、ストレスを抱えてしまうことがあります。
たとえば、営業や開発といった本来の業務の合間にブログを書く場合、「本当に必要なのか」「本業に支障が出るのでは」といった不安も出てきます。また、ブログの内容が業務と結びついていないと、執筆自体が単なる“作業”になってしまい、価値を感じられなくなることが多いです。
業務との関連性を高めるためには、担当者の経験や日常業務の気づきを記事に反映させたり、自分の仕事がどのように社外や社内に役立っているかを意識できるようなテーマ選びも有効です。
何を書けばいいのかわからない悩みの存在
「ブログを書け」と言われても、具体的にどのような内容にすればよいか悩むことは多いです。ネタ探しが難航し、書き出しで手が止まってしまう方も少なくありません。
この悩みの背景には、「会社のブログだから」と構えてしまい、失敗したくないという気持ちや、社内外に発信することへのプレッシャーもあります。さらに、「業界の専門知識が足りないから情報発信できる自信がない」と感じる場合もあるでしょう。
こうしたときは、身近な業務のエピソードや日々のちょっとした気づきを言葉にするだけでも十分です。テーマが定まっていない状況を乗り越えるには、他の社員やチームと話し合いながらアイデアを出し合うことが効果的です。
会社のブログを続けるメリットとその意義

会社ブログの運用は続けることで初めて価値が生まれます。ここでは続けることで得られる具体的な効果や意義を紹介します。
社内外への信頼やブランド力の向上
継続的な情報発信は、会社の姿勢や価値観を社内外に伝える機会になります。更新が続いているブログは、外部から見て「活動している企業」として評価されやすいです。
たとえば、商品やサービスの開発過程、社員の日常、社内イベントの様子などをブログに載せることで、社内の雰囲気や企業文化が伝わります。これが新規採用や取引先からの信頼感にもつながります。また、既存顧客にとっても「この会社は安心できる」と思ってもらうきっかけになります。
ブログを通じて、企業の考え方や取り組み姿勢をわかりやすく伝えることが、ブランドイメージの向上にも役立ちます。
社員自身のスキルアップや成長につながる効果
ブログ運用は、個々の社員のスキルアップにも良い影響をもたらします。文章を書く経験は、論理的な思考や情報整理力の向上につながります。
また、自分の業務を振り返ったり、他の人にわかりやすく伝える工夫をすることで、伝達力やプレゼンテーション力も自然に鍛えられます。これらのスキルは日々の業務にも生きるため、継続するほど大きな成長が期待できます。
社内でお互いのブログ記事を読むことで、社員同士のコミュニケーションも活性化し、より良いチーム作りにもつながります。
マーケティングや集客におけるブログの役割
ブログはインターネット検索を通じて、見込み客との新しい接点を生み出す役割を担っています。SEO効果も期待できるため、会社の知名度向上やお問い合わせ増加にもつながります。
たとえば、業界の動向や自社の製品・サービスについて分かりやすくまとめた記事は、ネット上で検索したユーザーが目にする機会が増えます。これが資料請求や相談へ導く入口になることも多いです。
また、定期的にブログを更新している会社は「情報発信に積極的」と受け止められやすく、信頼や関心を高めるポイントになります。
社員ブログ運用時に気を付けるべきポイント

社員がブログ運用をする際には、快適に書けるような体制や配慮が必要です。注意しておきたいポイントを具体的にまとめます。
無理なノルマや強制が逆効果になる理由
「毎週必ず1本」など厳しいノルマを課すと、かえって執筆が苦痛になりやすいです。無理に量を求めても、質の低下や精神的な負担が大きくなります。
強制的な運用は、モチベーションの低下や「やらされ感」を生み、長続きしない原因になります。ブログを書く目的や意義を社員が理解できるように伝えた上で、自主的な参加を促す工夫が重要です。
たとえば、「月1回まで」など柔軟な仕組みにしたり、チームで分担するなど、無理のない体制を目指しましょう。
プライバシーや個人情報の保護に配慮する重要性
ブログ運用では、社員や顧客の名前、住所、写真など、個人情報が不用意に公開されないよう注意が必要です。
たとえば、社内イベントの様子を写真付きで紹介する場合、写っている人の許可を得ることや、個人が特定できないよう配慮することが大切です。社員のフルネームや連絡先、顧客情報などは原則として掲載を避けるべきです。
プライバシーに関するルールを社内で共有し、守ることで、安心して執筆ができる環境を作りましょう。
誤解を招かない表現やテーマ選びの工夫
会社のブログは多くの人が閲覧するため、内容や言葉遣いには注意が必要です。誤解を招く表現や、会社のイメージを損なう内容は避けましょう。
たとえば、業界の専門用語を使う場合はわかりやすい説明を加えたり、主観的な意見を事実として断言しないことが重要です。また、時事ネタや社会問題に触れる際は、会社として公式な立場かどうかを確認し、慎重に言葉を選ぶ必要があります。
テーマ選びの際には、複数名で内容を確認し合う仕組みを作ることで、リスクを減らすことができます。
会社のブログを前向きに書くための対策とヒント

ブログ執筆への苦手意識を和らげ、前向きに取り組むための具体的な対策や工夫を紹介します。
テーマや内容のアイデアを共有しやすくする方法
「何を書けば良いかわからない」問題を解消するには、テーマやネタを共有できる仕組みが有効です。日々の業務や社内の出来事を、気軽にメモやチャットでアイデアとして出し合いましょう。
たとえば、テーマ出しのための会議を月1回開いたり、アイデアを共有するシートや掲示板を用意すると、多様な視点が集まりやすいです。以下のような共有方法もおすすめです。
・テーマアイデアを集める共用シートを作成
・チャットツールで気軽に話題を投稿
・参考になる他社ブログを定期的に紹介
このようにアイデアのハードルを下げることで、ネタ切れの不安も減らすことができます。
執筆しやすい体制やサポート環境の整備
ブログを書くことが負担にならないよう、執筆サポートや時間的配慮があると安心です。たとえば、原稿の下書きをチェックする担当者や、内容の相談に乗るメンターを設ける方法があります。
また、執筆用のガイドラインやマニュアルを用意すると、初めて書く人も安心して取り組めます。時間配分についても、業務時間内に執筆できるよう調整したり、まとまった時間を確保する仕組みづくりが有効です。
サポート体制や役割分担を明確にすることで、社員同士が無理なく協力し合いながらブログ運用を続けられます。
書きたくない気持ちを和らげるインセンティブや工夫
執筆のハードルを下げるためには、ちょっとした楽しみや報酬があると気持ちが和らぎます。ブログ執筆に対するインセンティブを検討しましょう。
たとえば、社内で「アクセス数が多かった記事を表彰」「記事を書いた人のランチ代サポート」など、成果や努力を認める機会を作るのも良い方法です。以下のような工夫も効果的です。
| 工夫例 | 内容 |
|---|---|
| 表彰制度 | 優れた記事や頑張った人を社内で表彰 |
| ちょっとしたプレゼント | 執筆者にドリンク券やお菓子を贈る |
| 執筆後のフィードバック会 | 良かった点を共有してモチベーションUP |
小さな達成感やポジティブな雰囲気を大切にすることで、執筆の心理的な負担を軽減できます。
まとめ:会社のブログ運用で悩みを解決し効果を高めるために
会社ブログ運用にはさまざまな悩みや課題がついてまわりますが、目的や意義を明確にし、サポート体制を整えることで、多くの効果を得ることができます。
社員の負担にならないよう配慮しつつ、テーマの共有やインセンティブの工夫を取り入れることで、前向きな気持ちでブログ運用に取り組めます。続けることで信頼やブランド力の向上、社員のスキルアップ、集客力向上など、多くのメリットにつながるため、一歩ずつ取り組んでみてください。









