h1 h2 h3タグがSEOに与える影響と見出しタグの正しい使い方を解説

Webサイトやブログの記事を作成するとき、SEO対策やユーザーに分かりやすい情報提供を重視している方も多いのではないでしょうか。特に見出しタグ(h1、h2、h3)は、検索エンジンにも読者にも内容を伝えるうえで重要な役割を持っています。
しかし、「見出しタグの使い分けがよく分からない」「SEOで本当に効果があるの?」といった疑問や悩みもよく聞かれます。
このページでは、見出しタグの正しい使い方やSEOでの効果、実践的なテクニックまで、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。
h1 h2 h3見出しタグの基本とSEOでの重要性
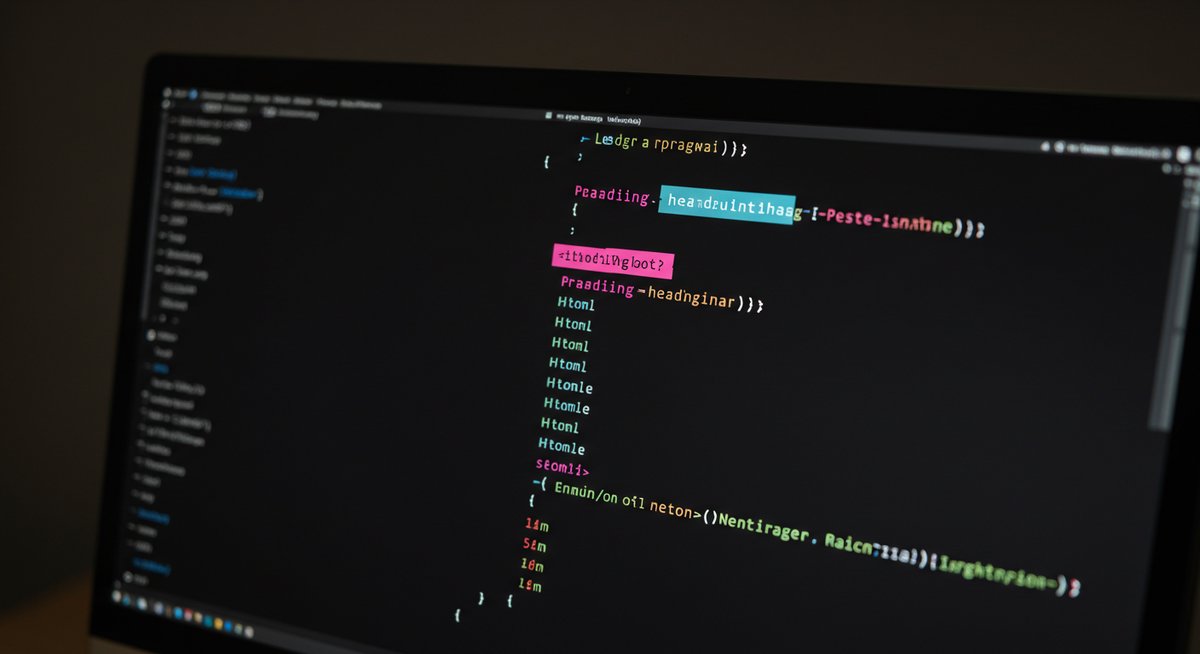
見出しタグは、サイトや記事を構造的に分かりやすく整理するために欠かせない要素です。SEOの観点からも、正しい使い方が検索順位に影響します。
h1 h2 h3タグの役割と違い
h1、h2、h3タグは、それぞれ記事の中で異なる役割を担っています。h1タグは最上位の見出しとしてページ全体のテーマやタイトルを示し、h2タグはh1の下の大見出し、h3タグはさらにその下の中見出しとして使われます。
たとえば、1つの記事の流れは以下のように整理されます。
- h1:記事のタイトル(例:「SEO初心者のための基礎知識」)
- h2:大きな章立て(例:「SEOとは?」)
- h3:その章の中の細かい項目(例:「検索エンジンの仕組み」)
このように階層ごとに整理することで、記事の全体像がつかみやすくなるだけでなく、検索エンジンにも内容が伝わりやすくなります。
SEOにおける見出しタグの効果
見出しタグは、Googleなどの検索エンジンがページの内容を理解する手がかりになります。特にh1やh2は、そのページがどんなテーマを扱っているかを伝える重要な指標です。
また、見出しに適切なキーワードを含めることで、検索エンジンからの評価も得やすくなります。ただし無理に詰め込むのではなく、自然な文章の流れを意識した見出しにすることが大切です。
検索エンジンが見出しタグから読み取る内容
検索エンジンは、見出しタグの構造からコンテンツの主題や重要ポイントを把握します。たとえば、h1に「SEO対策の基本」とあれば、そのページはSEO対策について説明していると判断します。
また、h2やh3を見て記事の詳細な構成も読み取ります。これにより、ユーザーが求める情報がどこにあるかも推測できます。検索エンジンに正確な情報を伝えるためにも、見出しタグの使い方は非常に重要です。
ユーザー体験向上における見出しタグの働き
見出しタグはSEOだけでなく、読み手の体験(ユーザー体験)を向上させる役割も持っています。見出しが整理されていると、知りたい情報がすぐに見つかりやすくなります。
さらに、スマートフォンやタブレットでも見出しタグが正しく使われていると、スクロールしながら内容をざっと把握しやすくなります。たとえば、長い記事でも見出しをたどれば要点がすぐにつかめるため、離脱を減らす効果も期待できます。
h1タグの使い方と最適化のポイント

記事のタイトルやページのテーマを示すh1タグは、SEOで特に重視される要素です。適切な使い方や注意点を知ることで、見やすく、評価されやすいページ作りにつながります。
h1タグとtitleタグの違い
h1タグとtitleタグはどちらもページのタイトルを示しますが、役割は異なります。titleタグはブラウザのタブや検索結果に表示されるものであり、SEOへの直接的な影響も強い要素です。
一方で、h1タグはあくまでページ内で最も重要な見出しとして、本文の内容を簡潔に示します。両方の内容は似ていても問題ありませんが、まったく同じにする必要はありません。ページ内での役割を意識して使いましょう。
| タグ | 役割 | 主な表示場所 |
|---|---|---|
| title | 検索結果・タブ | 検索結果、ブラウザのタブ |
| h1 | ページの見出し | 記事本文の上部 |
1ページに1つだけh1タグを使う理由
h1タグは、そのページのテーマや内容を示す「主見出し」です。そのため、1ページにつき1つだけ使うのが基本とされています。複数使うと、どの内容が主題なのか検索エンジンもユーザーも分かりにくくなってしまいます。
また、h1タグが複数あるとSEO評価が分散したり、情報が整理されていない印象を与える場合もあります。どうしても複数のテーマを扱いたい場合は、それぞれをh2やh3などの下位見出しにして、構成を工夫しましょう。
h1タグに画像を使う場合の注意点
h1タグにはテキストで主題を示すのが理想です。しかし、デザインの都合で画像を使いたい場合もあるでしょう。その場合は、代替テキスト(alt属性)をしっかり設定し、画像が表示されない環境でも内容が伝わるようにしましょう。
また、画像だけだと検索エンジンが内容を正確に把握できませんので、なるべくテキストを併用したり、画像の下に説明文を加えるなどの工夫をおすすめします。
h1タグの具体的な設定例
h1タグの具体的な使い方を示します。たとえば、SEOに関する記事の場合、下記のような見出しを設定できます。
- h1:SEO対策の基本と実践ポイント
- h2:SEOとは何か
- h2:効果的なキーワード選定方法
- h2:コンテンツ作成のポイント
このように、まずh1で記事全体のテーマを明確にし、h2以下で詳細な内容を展開します。h1は短く分かりやすい表現を意識しましょう。
h2 h3タグの適切な使い分けとルール

h2やh3タグは、記事内の内容をさらに細かく整理するために活用します。正しい使い分けや配置ルールを押さえておくことで、読みやすく分かりやすい記事構成になります。
階層構造を意識したh2 h3タグの配置
記事を分かりやすく整理するためには、見出しタグの階層構造を守ることが大切です。h2はh1の下位、h3はh2の下位という順番で使うことで、情報が整理され、全体の流れもスムーズになります。
たとえば、
- h1:SEOの基礎
- h2:SEOの重要性
- h3:企業にとってのメリット
- h3:個人ブログにおける影響
- h2:キーワード選定
- h3:選定のコツ
このように階層を意識すれば、情報が整理され、読者も全体像を把握しやすくなります。
h2 h3タグは何度使ってもOKか
h2やh3タグは、必要に応じて何度でも使うことができます。たとえば、1つの記事内で複数のテーマを扱う場合、それぞれをh2で分け、さらに詳細説明にはh3を使うことで、より分かりやすい構成になります。
むしろ、長い記事で見出しが少なすぎると情報が整理されず、読みづらくなる場合もあります。適切な場所で見出しタグを使い、内容を小分けにして展開しましょう。
h2 h3タグの順番と論理的な記事構成
h2とh3タグは、必ずh1→h2→h3という順番で使うことが基本です。見出しの順番が逆になったり飛んだりすると、検索エンジンや読み手にとって分かりにくい記事になってしまいます。
たとえば、h2の直下にいきなりh4やh3が続くのは避け、必ず1つ上の階層から順を追って構成しましょう。論理的な流れを意識すれば、情報が伝わりやすくなります。
| 見出しの順序 | 正しい使い方 | 誤った使い方 |
|---|---|---|
| h1→h2→h3 | ○ | ×(h1→h3→h2など) |
h2 h3タグに含めるべきキーワードの考え方
h2やh3タグには、その章や項目で取り上げる話題やキーワードを意識的に入れることが望ましいです。ただし、キーワードばかりを詰め込むのではなく、自然な流れの中で違和感なく使いましょう。
また、検索されやすいワードや、ユーザーの疑問に沿ったフレーズを含めることで、SEO効果だけでなくユーザーにとっても分かりやすい記事になります。キーワード選定には、実際に検索する言葉や関連語を意識してみてください。
見出しタグを活用したSEO対策の実践テクニック
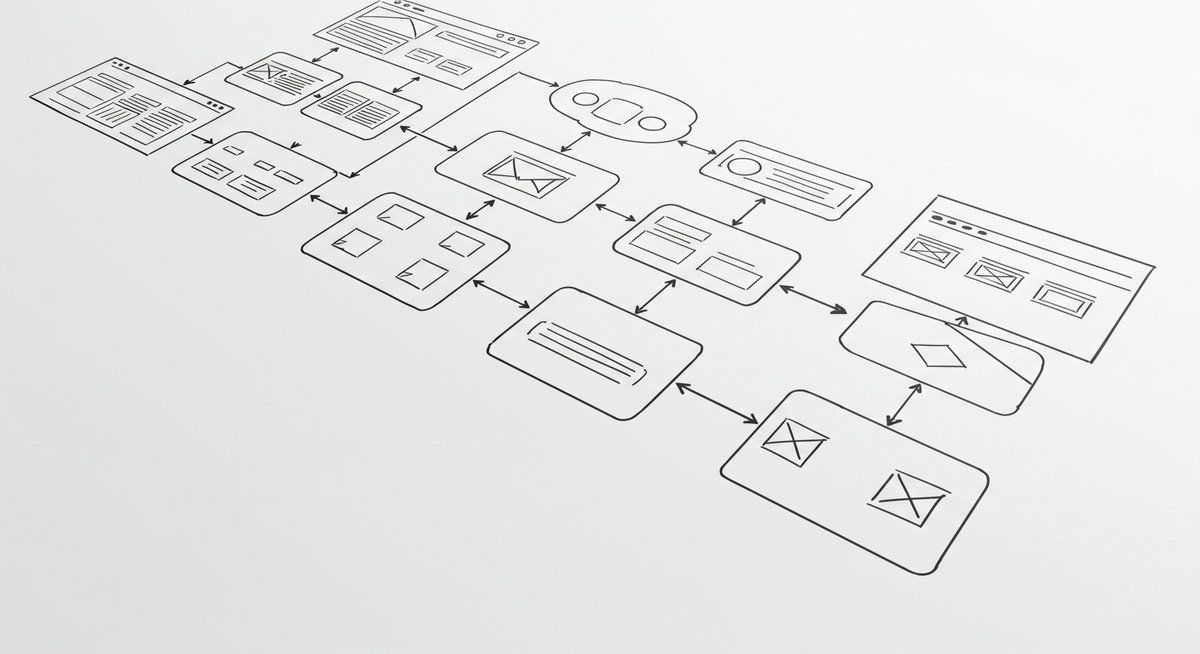
見出しタグをただ使うだけでなく、SEO効果を意識した工夫を取り入れることで、より検索エンジンやユーザーに評価される記事になります。
簡潔で分かりやすい見出しの作り方
見出しは短く、内容が一目で分かるように作ることが大切です。長すぎる見出しや複雑な表現は、ユーザーの離脱を招くおそれがあります。
見出しのポイントは次の通りです。
- 20〜30文字以内を目安にする
- この記事で何を伝えているか明確にする
- 専門用語を多用しすぎない
これらを意識すると、見出し自体がユーザーの興味を引き、記事の内容も理解しやすくなります。
見出しタグと目次の連動で可読性アップ
見出しタグを使って目次を自動生成すれば、記事全体の流れや構成が一目で分かるようになります。特に長い記事では、目次から各見出しへのリンクを設けることで、読みたい部分へすぐ移動できる点が便利です。
たとえば、次のような流れになります。
- 目次作成ツールやプラグインで自動生成
- 見出しタグに沿った階層構造の目次
- クリックで各見出しにジャンプできる
この仕組みを活用すると、ユーザーの利便性も高まります。
見出しタグにアンカーテキストを設置する効果
見出しタグにアンカーテキスト(リンク先の目印となるテキスト)を設けることで、記事内リンクや目次との連動が可能になります。これにより、ユーザーが知りたい情報へ素早く移動できるのが利点です。
また、検索エンジンもアンカーリンクの情報を参考にコンテンツ構造を把握します。内部リンクの工夫はSEOにも有効です。
hタグの装飾やデザインのポイント
見出しタグは内容だけでなく、デザイン面でも工夫することで読みやすさが向上します。たとえば、h2やh3見出しの文字サイズや色を変えたり、余白を多めに取るなどの方法があります。
ただし、装飾が過剰だと逆に読みづらくなったり、ページの表示速度が遅くなる場合もあるため注意が必要です。読みやすさとデザイン性のバランスを考えた装飾を心がけましょう。
h1 h2 h3タグを使う際の注意事項とよくある失敗
見出しタグを使う際には、SEO効果だけでなく、ユーザー体験や記事全体の読みやすさも意識することが重要です。よくある失敗例や注意ポイントをまとめます。
キーワードの詰め込み過ぎに注意
見出しタグにSEOキーワードを多く入れすぎると、不自然な文章になりやすく、かえって読みにくくなります。検索エンジンも「キーワードの詰め込み」を評価しないため、適度な使用を心がけましょう。
自然な文章の流れを大切にしながら、必要な場所にだけキーワードを配置するのがポイントです。読者に伝わりやすい見出しを優先してください。
見出しが長すぎる場合の対処法
見出しが長くなりすぎると、内容が伝わりづらくなります。30文字程度を目安にまとめ、どうしても長くなってしまう場合は、要点を絞って2つの見出しに分ける方法も有効です。
また、重要なキーワードを前半にもってくる、余計な説明や装飾語を省くなどの工夫も取り入れてみましょう。
hタグだけで記事を構成しない理由
記事が見出しタグばかりで構成されていると、本文が薄くなり、情報量が十分に伝わりません。また、検索エンジンにとっても内容が少ないページと判断される可能性があります。
見出しの下には必ず本文を加え、内容を補足・説明するようにしましょう。見出しと本文のバランスが取れている記事が理想的です。
アクセシビリティを考慮した見出しタグの設定
見出しタグはアクセシビリティ(誰でも情報を得やすい状態)の観点からも重要です。音声読み上げツールや支援技術を使うユーザーは、見出し構造を頼りに内容を把握します。
見出しの順序を適切に守る、テキストが分かりやすい表現であること、装飾が過剰にならないことなどに注意を払いましょう。
まとめ:h1 h2 h3見出しタグを正しく活用してSEO効果を最大化しよう
見出しタグの基本からSEO対策での実践的な使い方、注意点まで解説しました。見出しタグを正しく使うことで、検索エンジンにもユーザーにも分かりやすい記事を作成できます。
階層や順序、キーワードの使い方などポイントを押さえ、過度な装飾やキーワードの詰め込みを避けるなど、バランスの取れたページ作りを心がけてください。結果として、SEO効果とユーザー体験の向上につなげることができます。









