h1タグを複数使うとSEOにどう影響するのか最新ルールと正しい設置方法を解説
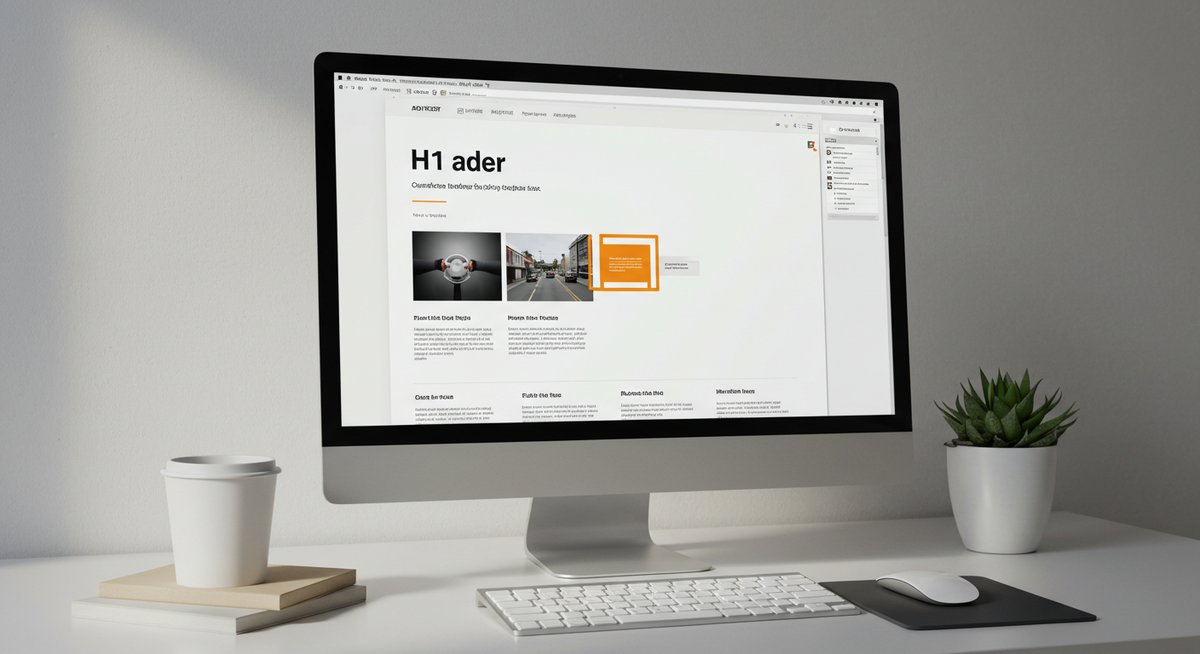
Webサイトを運営していると、「h1タグを複数使ってもいいのか」「SEOではどんな影響があるのか」と悩む方が多いのではないでしょうか。特に、SEO対策やWeb集客で成果を求めている場合、h1タグの正しい使い方は押さえておきたいポイントです。
本記事では、h1タグを複数使った場合のSEOへの影響や、ユーザーや検索エンジンに与える印象、実務での注意点やトラブル回避方法まで、初心者にもわかりやすく解説します。正しいルールを理解し、より効果的なWeb集客につなげましょう。
h1タグを複数使う場合のSEOへの影響と基本ルール
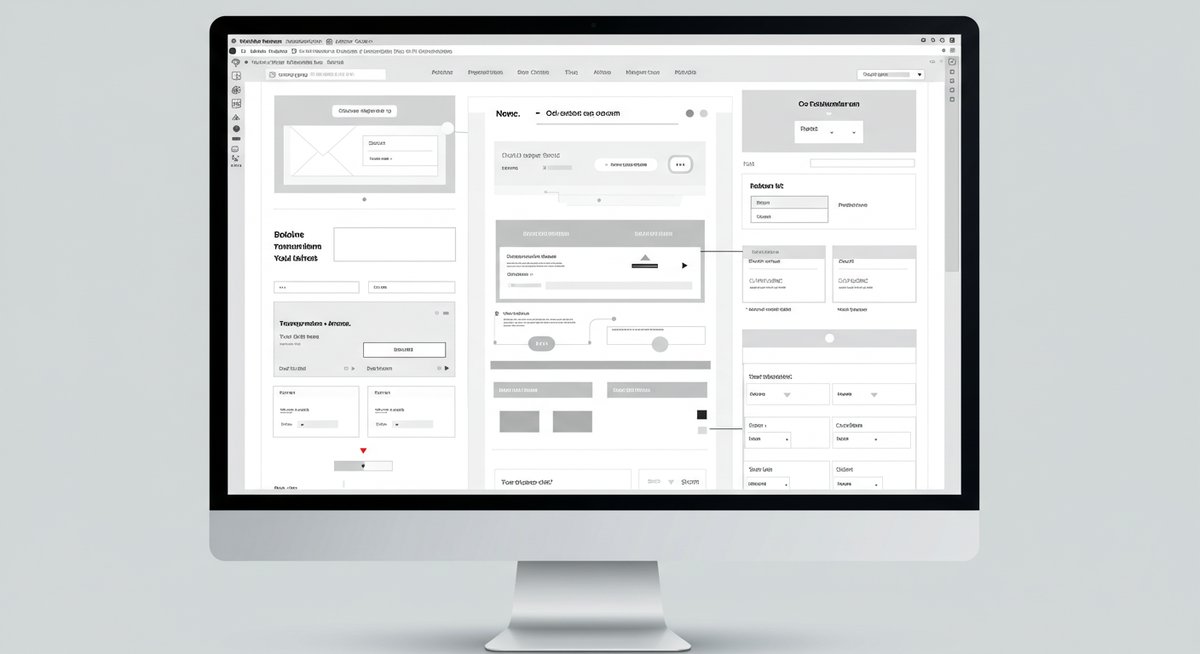
h1タグはページの主題を伝える大切な要素です。しかし、複数設置した場合、どのような影響があるのか気になる方も多いでしょう。
h1タグを複数配置したときの検索エンジンの認識
検索エンジンはh1タグを「そのページの主なテーマ」として認識します。ページ内に複数のh1タグがある場合、どれが本当の主題なのか判断しにくくなるため、検索エンジン側で正しい評価がされにくくなる恐れがあります。
たとえば、ページ内にh1タグが3つあり、それぞれ異なる内容だった場合、どの情報を重視すべきなのか迷ってしまい、最終的にSEO上の評価が分散してしまう場合があります。また、過去に比べて検索エンジンの解析能力は高まっていますが、h1タグの使い方が適切でないとページの意図が伝わりづらくなることもあります。
h1タグが複数あるとユーザーに与える印象
ユーザーは見出しを頼りにページの内容を把握します。h1タグが複数存在すると、「どの情報が一番大切なのか」が直感的に分かりづらくなり、ページ全体の印象や読みやすさが損なわれる可能性があります。
また、スマートフォンのような小さい画面では、複数のh1タグが強調されることで、画面の見やすさや情報の整理が難しくなる場合もあります。特に、初めて訪問したユーザーにとっては、主題が曖昧なサイトという印象を与えてしまうでしょう。
Google公式見解と最新のアルゴリズム動向
Googleは公式に「h1タグは複数使ってもペナルティにはならない」と発表しています。ただし、ページの主題を明確に伝えるための使い方を推奨しており、h1タグを乱用するとSEO上のメリットは得られにくくなります。
最近の検索エンジンは文脈や構造をより重視する傾向があります。h1タグの数よりも、「主題を明確に示せているか」「論理的な見出し構造になっているか」が重要です。無理にh1タグを一つに制限する必要はなく、ページの内容や設計意図に沿って適切に使うことが推奨されています。
1ページに複数h1タグを使う場合の注意点
どうしても複数のh1タグを使いたい場合は、それぞれのh1タグが異なる主題を表さないよう工夫が必要です。たとえば、レイアウトやデザイン上の都合で使う場合は、コンテンツの主題に混乱が生じないように意識しましょう。
また、主要なh1タグが一つ存在し、他のh1タグは補助的な見出しやデザイン要素として使われていないか確認してください。検索エンジンやユーザーが迷わないように、ページの構造がシンプルで明確になるよう心がけることが重要です。
h1タグと他の見出しタグとの違いと役割
h1タグはページ全体の主題を示す役割を持ち、h2やh3タグはその下位のトピックや内容の区切りを表します。サイトの内容を階層的に整理し、情報の流れを分かりやすく伝えるために見出しタグを使い分けることが大切です。
下記の表に、代表的な見出しタグの役割をまとめました。
| タグ | 主な役割 | 用途例 |
|---|---|---|
| h1 | ページの主題 | 記事タイトル |
| h2 | 主題の項目や大見出し | 各段落の見出し |
| h3 | h2の補足や小見出し | 詳細説明やサブトピック |
h1タグ複数設置時に避けるべき落とし穴

複数のh1タグを設置すると、思わぬトラブルや評価の低下につながることもあります。よくある失敗例や注意点をまとめました。
クローラーとユーザー両方で混乱が生じるケース
クローラー(検索エンジンの情報収集ロボット)は、ページ内の見出し構造から内容を解析します。h1タグが複数存在し、それぞれが違うテーマを示している場合、クローラーはどれを主題と判断すべきか迷ってしまいます。
また、ユーザーにとっても同じです。主題が複数表れていると、どの内容が最重要なのか直感的に把握しにくく、ページ全体の理解が難しくなります。結果として、離脱率が上がるなど、ユーザー体験の低下を招きやすくなります。
h1タグの内容が重複する場合のリスク
h1タグが複数あり、内容がほとんど同じだった場合、検索エンジンは重複コンテンツとみなすことがあります。重複が多いとSEO評価が分散し、最終的に検索順位が伸びにくくなる恐れがあります。
また、同じ文言が何度も表示されることで、ユーザーにも不自然な印象を与えてしまいます。重要なキーワードや主題は、一つのh1タグで的確に伝えるようにしましょう。
ロゴやデザイン要素でh1タグを使う場合の注意
ロゴ画像やヘッダー部分のキャッチコピーにh1タグを使うケースもありますが、デザイン目的だけでh1タグを使用すると、ページの主題が曖昧になります。特に、ロゴと記事タイトルの両方にh1タグを設定してしまい、意図しない主題分散が起きることもあります。
デザインの都合上、ロゴにh1タグを使いたい場合は、そのページの内容や目的に応じて、どちらか片方だけに設定するか、CSSで見た目だけ装飾する方法を選択しましょう。
h1タグを見出し装飾目的で乱用する弊害
見出しの文字サイズや太字を簡単に調整できるため、h1タグを装飾目的だけで使うケースがあります。しかし、この方法は検索エンジンとユーザーの両方に混乱を与えます。
装飾はCSSなどのデザインコードで対応し、見出しタグは本来の意味に沿って使いましょう。SEOやユーザビリティの観点からも、用途に応じた使い分けが、結果的にWeb集客の強化につながります。
正しいh1タグの使い方と実装ポイント
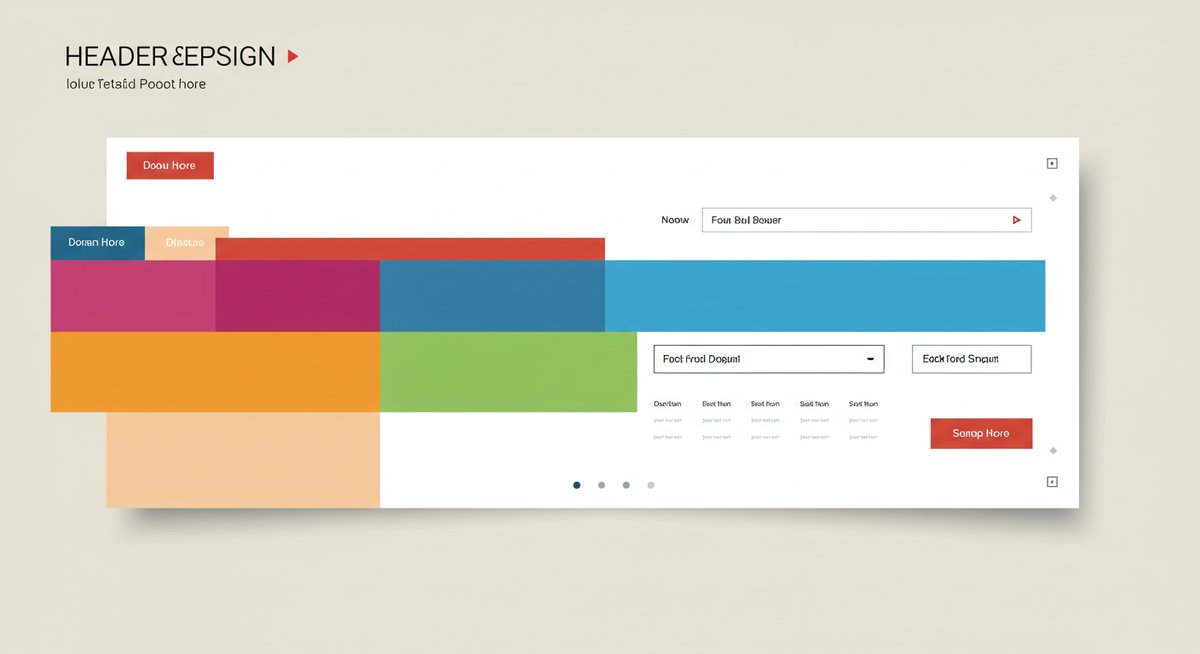
SEOとユーザビリティ向上のために、h1タグは正しく使う必要があります。具体的な作り方や設計方法を紹介します。
ページの主題を表現するh1タグの作り方
h1タグには、そのページ全体をひとことで表す言葉やフレーズを入れるのが基本です。たとえば、記事なら「〇〇の選び方」や「〇〇とは」といった形がわかりやすいでしょう。
主題が明確なh1タグは、ユーザーがページに訪れたときに「何が書かれているページか」をすぐに理解できるメリットがあります。検索エンジンにとっても、ページ内容を判断しやすくなるため、SEOにもつながります。
h1タグはできるだけ1ページ1つを推奨する理由
h1タグが複数あると主題が分散するため、ページのテーマが曖昧になります。1ページ1つのh1タグにまとめることで、検索エンジンやユーザーの混乱を防ぎ、ページの意図を伝えやすくなります。
また、見出しタグを階層的に整理しやすくなり、サイト全体の構造も明瞭になります。これにより、SEOの内部施策やユーザー体験改善にもつながります。
h1タグに自然にSEOキーワードを含めるコツ
h1タグにSEOキーワードを盛り込みたい場合は、不自然にならないよう注意が必要です。キーワードをそのまま詰め込むのではなく、ページ内容に即した形で使うと、検索エンジンからも評価されやすくなります。
例えば、下記のような工夫が有効です。
- キーワードを文中の自然な位置に配置する
- 無理な繰り返しは避ける
- 補足語(選び方・活用法など)と組み合わせる
このような形で、ユーザーにも馴染みやすい見出しを意識しましょう。
順序を守ったhタグ構造の設計方法
見出しタグは、h1→h2→h3のように順序を守って使うのが基本です。h1タグの下にh2、さらにその下にh3を配置することで、ページ内容が整理され、ユーザーも目的の情報を探しやすくなります。
順序が乱れていると、情報のつながりが分かりにくくなり、SEOやユーザビリティにも悪影響を及ぼします。下記の箇条書きを参考に、適切な見出し構造を意識しましょう。
- h1:ページ主題
- h2:主題の大きな項目
- h3:さらに細かいトピックや説明
h1タグ記述時の最適な文字数と簡潔な表現
h1タグは長すぎず、簡潔に書くことが大切です。理想的な文字数は30文字以内を目安にすると、検索エンジンやユーザーが内容を把握しやすくなります。
また、要点を押さえて短くまとめることで、ページタイトルや検索結果にも違和感なく表示されます。余分な装飾語や長文は避け、伝えたい主題が一目で分かる表現を選びましょう。
h1タグ複数利用時の実務的な対策と応用
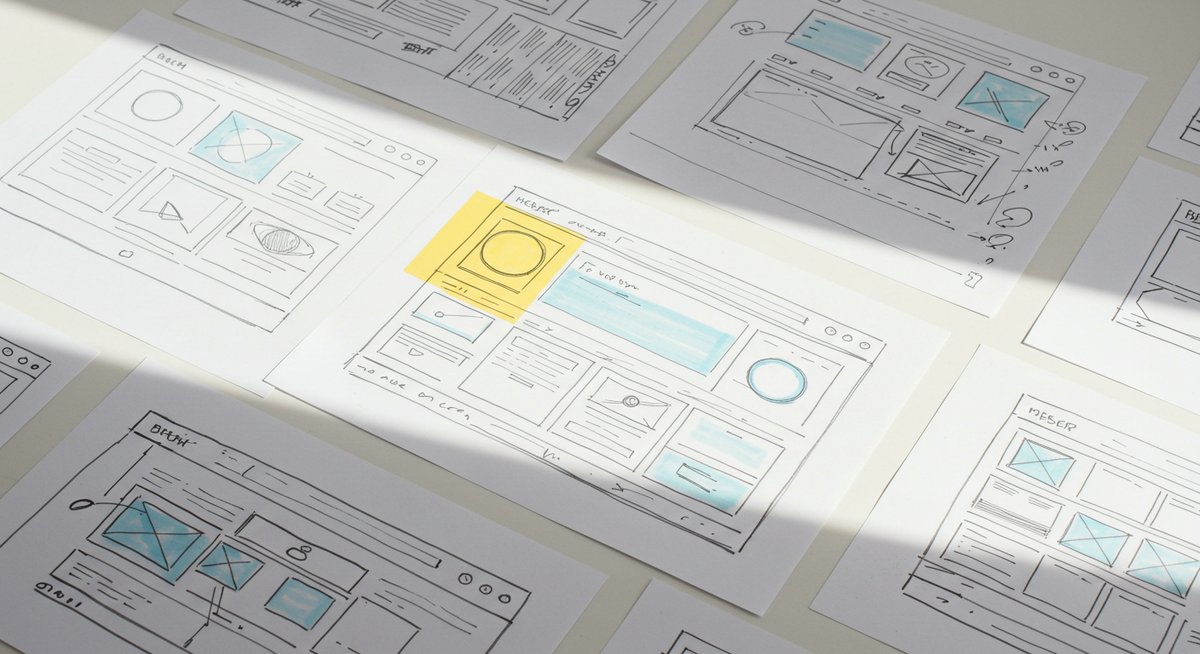
実際の現場では、システムやテンプレートの都合でh1タグが複数になってしまうこともあります。そんな場合の対処法や工夫を解説します。
すでにh1タグが複数あるサイトの修正手順
まずは、全ページのh1タグをチェックし、どこに複数のh1タグが使われているか把握しましょう。その後、主題を示すh1タグ以外は、h2やh3に変更するのが基本です。
大規模なサイトの場合は、次の手順が参考になります。
- サイト全体でh1タグの使用箇所を洗い出す
- ページごとに主題を明確にする
- 主題以外のh1タグはh2、h3へ変更
- 見出しの階層もあわせて修正
- 必要に応じて再クロールを依頼
このように、順序を守りながら丁寧に修正していきましょう。
WordPressやCMSでh1タグが複数になる場合の対応
WordPressやCMSでは、テーマやプラグインの仕様で自動的にh1タグが増えてしまうこともあります。ロゴやウィジェットにh1タグが設定されていないか確認し、不要なものはh2やh3に変更します。
テンプレートを編集できない場合は、専用のプラグインやカスタマイズ機能を活用して、見出しタグの構造を整えましょう。また、テーマのアップデート時にh1タグが増えていないか、定期的なチェックもおすすめです。
h1タグとtitleタグの違いと正しい使い分け
h1タグはページ内に表示されるメインの見出し、titleタグはブラウザのタブや検索結果に表示される要素です。どちらも主題を示しますが、用途や表示場所が異なります。
| タグ名 | 表示される場所 | 主な役割 |
|---|---|---|
| h1タグ | ページ本文 | ページ主題の明示 |
| titleタグ | ブラウザ・検索結果 | サイトやページタイトルの表示 |
titleタグにはサイト名も含めることが多いですが、h1タグは主題のみを簡潔に記載するのが基本です。
アクセシビリティやユーザビリティ向上の観点からの工夫
h1タグの正しい使い方は、アクセシビリティやユーザビリティにも直結します。特に視覚障がいのある方は、ページ構造を支援技術で読み取るため、h1タグが主題として機能しているかが重要です。
また、適切な見出し構造により、ユーザーが素早く目的の情報にたどり着きやすくなります。文字の視認性や順序の分かりやすさにも配慮し、すべてのユーザーにとって使いやすいページを目指しましょう。
h1タグに関するよくある疑問と最新情報
h1タグにまつわる疑問や、最近のSEO動向に関するポイントを整理しました。
h1タグを使わなかった場合のSEOへの影響
h1タグをページ内で使わない場合、検索エンジンに主題が伝わりにくくなるため、SEO評価が下がる可能性があります。ただ、必ずしもペナルティになるわけではありませんが、推奨される設計とは言えません。
ユーザーにとっても、ページ構造が分かりづらくなり、目的の情報を探しにくくなることがあります。主題となる部分は必ずh1タグでマークアップするのが望ましいでしょう。
h1タグを複数使っても良い具体的なケース
複数のh1タグが許容されるのは、ページ内に複数の大きなセクション(たとえばニュース記事一覧や、完全に独立したコンテンツブロック)が存在する場合です。
ただし、各セクションが独立しており、それぞれが個別の主題を持つ場合に限ります。一般的なブログ記事や商品ページでは、h1タグは一つにまとめるのが基本です。
画像にh1タグを使う場合のalt属性の扱い
画像をh1タグで囲う場合、alt属性には画像の内容を簡潔に説明するテキストを入れます。alt属性が正確だと、検索エンジンにも主題が伝わりやすくなります。
たとえば、「会社ロゴ画像」をh1タグにした場合、alt属性には「〇〇株式会社 ロゴ」など、意味が明確なテキストを設定しましょう。これにより、画像が表示できない環境でも主題が伝わります。
h1タグにキーワードを詰め込みすぎるリスク
h1タグに多くのキーワードを詰め込むと、不自然な文章になりやすく、ユーザーの読みやすさが損なわれます。また、検索エンジンも「キーワードの乱用」とみなし、評価を下げる可能性があります。
キーワードは1つ、多くても2つまでに絞り、自然な文章になるよう意識しましょう。コンテンツの質を重視することが、長期的なSEO効果にもつながります。
まとめ:h1タグ複数設置時のSEO配慮と最適なWeb集客のために
h1タグはページの主題を明確に伝える重要な要素です。複数設置は必ずしも間違いではありませんが、主題が曖昧になったり、評価が分散したりするリスクもあります。
SEOやユーザー体験を意識して、h1タグはできるだけ1ページに1つ、主題が分かりやすい形で使いましょう。適切な見出し構造と表現で、Web集客の効果を高めてください。









