インタビュー記事のテンプレートを活用する方法と成功事例から学ぶポイント

集客やSEO対策を考えるとき、オリジナルなコンテンツ作成が欠かせません。しかし、何から始めればよいか悩んだり、継続的に質の高い記事を作るのが難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。
特にインタビュー記事は、読者に新鮮な視点や価値を伝えるうえで有効ですが、構成や進め方に迷うこともあります。この記事では、インタビュー記事テンプレートの活用方法や準備のポイント、効率よく読者の心を掴むコツまで分かりやすく解説します。
インタビュー記事テンプレートの基本と活用シーンを理解しよう

インタビュー記事テンプレートは、記事作成に悩む方にとって心強いサポートとなります。まずはその基本や活用シーンについて確認しましょう。
インタビュー記事テンプレートとは何か
インタビュー記事テンプレートとは、インタビュー形式の記事を効率的に作成するための「記事の型」です。一般的には、質問と回答が見やすく並ぶ構成や、エピソードを時系列で紹介する形が用意されており、初心者でも分かりやすく利用できます。
このテンプレートを活用することで、記事全体の流れが自然になり、読者にも内容が伝わりやすくなります。また、テーマや目的に合わせて一部をアレンジすることで、独自性のあるコンテンツに仕上げることも可能です。テンプレートは作業効率だけでなく、品質安定にも役立ちます。
どんな場面でテンプレートが役立つか
インタビュー記事テンプレートは、さまざまな場面で効果を発揮します。たとえば、自社サイトで社員や顧客の声を紹介したいとき、採用ページで働く人のリアルな声を伝えたいとき、商品開発秘話などを発信したいときなどです。
また、外部パートナーとのコラボ企画、専門家へのインタビュー記事など、幅広いジャンルで活用できます。定期的に異なる対象へのインタビューを行う場合にも、毎回構成をゼロから考える手間が省け、記事作成のスピードアップにつながります。
テンプレートを使うメリットと効果
テンプレートを使う最大のメリットは、作業効率の向上と記事品質の安定です。決まったフォーマットがあることで、見出しや質問文、導入部の文例などを短時間で組み立てられます。慣れていない方でも抜け漏れが起きにくくなります。
さらに、読みやすいレイアウトやストーリー展開が用意されているため、読者にも分かりやすい記事に仕上がります。SEO対策としても、情報が整理されていることで検索エンジンからの評価が上がりやすくなります。継続的に記事を更新したい場合、テンプレートは非常に便利なツールです。
#### テンプレート利用の主な効果
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| 作業効率化 | 構成を考える時間を短縮できる |
| 品質安定 | 読みやすい記事を毎回作成しやすい |
| SEO向上 | 情報整理されているため検索性が上がる |
成功事例から学ぶインタビュー記事の活用方法
実際にテンプレートを活用した企業やメディアでは、社内外への情報発信力が大きく向上しています。たとえば、採用サイトでは社員インタビューのテンプレートを用いることで、求職者が知りたい情報を的確に伝えられ、応募数の増加につながった例もあります。
また、商品やサービスの開発秘話、顧客インタビューなどを定期的に掲載することで、ファンづくりやブランドイメージの向上に役立つケースが多くみられます。テンプレートを柔軟にカスタマイズすることで、各現場の個性や魅力も引き出せることがポイントです。
インタビュー記事の主な形式と特徴別テンプレート

インタビュー記事にはいくつかの書き方があり、内容や目的に合わせて適切なテンプレートを選ぶことが大切です。ここでは主な形式と特徴を紹介します。
Q&A形式のインタビュー記事テンプレート
Q&A形式は、質問(Question)と回答(Answer)を交互に並べるオーソドックスな構成です。読者が知りたいことに絞って情報を整理しやすく、読みやすさも高いのが特徴です。たとえば「なぜこの仕事を選びましたか?」という質問に、対象者が自分の経験を答えるというようなシンプルな形になります。
この形式は、複数のインタビューを同じテンプレートでまとめやすく、比較もしやすいというメリットがあります。特に、採用ページや社内報、顧客インタビューに適しています。ただし、質問が単調にならないよう、ストーリー性やエピソードを適度に盛り込む工夫も大切です。
#### Q&A形式の簡易テンプレート例
| 項目 | 内容例 |
|---|---|
| Q1 | 現在の仕事を選んだきっかけは? |
| A1 | 大学時代の経験が影響しました |
| Q2 | 仕事のやりがいは? |
| A2 | お客様からの感謝の声が励みです |
モノローグ形式のテンプレートの使い方
モノローグ形式は、インタビュー対象者が自分の言葉で語るような記事構成です。第三者の解説を最小限にし、「私がこの仕事を始めた理由」「体験談」など、ストーリーを語る形が中心となります。
この形式は、対象者の個性や想いをダイレクトに伝えたい場合に効果的です。たとえば、社長メッセージやサービス誕生秘話、特定の体験談などが該当します。記事全体の流れや見出しはテンプレートを参考にしつつ、自由度高く表現できる点が魅力です。文章が長くなりがちなため、要点を小見出しで分けて整理すると、読みやすさが向上します。
ルポ形式のテンプレートと活用ポイント
ルポ(ルポルタージュ)形式は、現場の雰囲気やインタビュー当日の様子をレポート風にまとめる記事です。たとえば、工場見学やイベント取材など、体験したままを臨場感たっぷりに伝えたい場合に活用されます。
この形式では、記者の感想や観察が加わることで、読者が現場を疑似体験できます。構成としては、「現場到着」「インタビュー開始」「印象的な発言」「まとめ」など、時系列で流れを追うテンプレートが適しています。写真や表と組み合わせると、より分かりやすくなります。
形式別に押さえておきたい注意点
どの形式にも共通して、内容が一方的にならないよう注意が必要です。Q&A形式では、質問が羅列になりすぎないよう意図を明確にし、モノローグ形式では読者が共感できるストーリー性を盛り込みましょう。
また、ルポ形式では事実と感想を混同せず、客観的な視点も忘れないことが大切です。どのテンプレートを使う場合でも、対象者や読者のニーズに合わせて細部を調整すると、より魅力的な記事になります。
#### 形式別チェックポイント
| 形式 | 注意点 |
|---|---|
| Q&A | 質問の意図が明確か |
| モノローグ | 読み手が共感しやすい内容か |
| ルポ | 事実と感想を分けて書いているか |
インタビュー記事作成前に必要な準備とポイント

良質なインタビュー記事を作成するには、事前準備が欠かせません。目的や対象者の理解、構成の設計が成果を左右します。
インタビューの目的設定とターゲット決定
インタビューを始める前に、記事の目的やターゲット読者を明確にしましょう。たとえば、新商品を紹介したいのか、働く人の魅力を伝えたいのかによって、聞くべき内容や記事のトーンが変わります。
ターゲットが20代の就職希望者であれば、キャリア形成や仕事への思いを中心に、30代子育て世代向けならワークライフバランスや働きやすさを重視した質問を考えてみましょう。目的と読者像が定まることで、ぶれないインタビュー記事が作成できます。
対象者へのリサーチと事前コンタクト
インタビュー対象者について事前に調べ、経歴や実績、過去の発言などを把握しておくことが大切です。事前リサーチにより、より具体的な質問や深掘りが可能になります。
また、インタビュー前には簡単な連絡や打ち合わせを行い、当日の流れや質問の概要を共有しましょう。相手が安心して話せる雰囲気を作ることで、自然なやりとりが生まれやすくなります。
質問リストやストーリーラインの組み立て
インタビューをスムーズに進行するため、あらかじめ質問リストを用意しておきましょう。基本的な質問(自己紹介や経歴)から、深掘りしたいテーマへと流れるストーリーラインを意識するとまとまりやすくなります。
質問は多すぎず、余白を持たせるのがポイントです。予想外の話題やエピソードが出てきた場合にも柔軟に対応できるよう、必須質問と補足質問を分けてリスト化しておくと安心です。
#### 質問リストの例
| 質問例 | 目的 |
|---|---|
| どんな経歴か | 対象者の人物像を伝える |
| 転機となった出来事 | 体験談やストーリーを引き出す |
| 今後の目標 | 読者へのメッセージを明確にする |
テンプレート選定とカスタマイズのコツ
目的や伝えたい内容に合わせて、最適なテンプレート形式を選びましょう。Q&A形式がベストな場合もあれば、モノローグやルポ形式のほうが適している場合もあります。
テンプレートはそのまま使うのではなく、記事ごとにタイトルや質問内容、見出しを調整し、独自のストーリーや個性を盛り込むことが大切です。読者や対象者の特徴に合わせて柔軟にカスタマイズすることで、より魅力的な記事になります。
インタビュー当日から記事執筆までの流れ
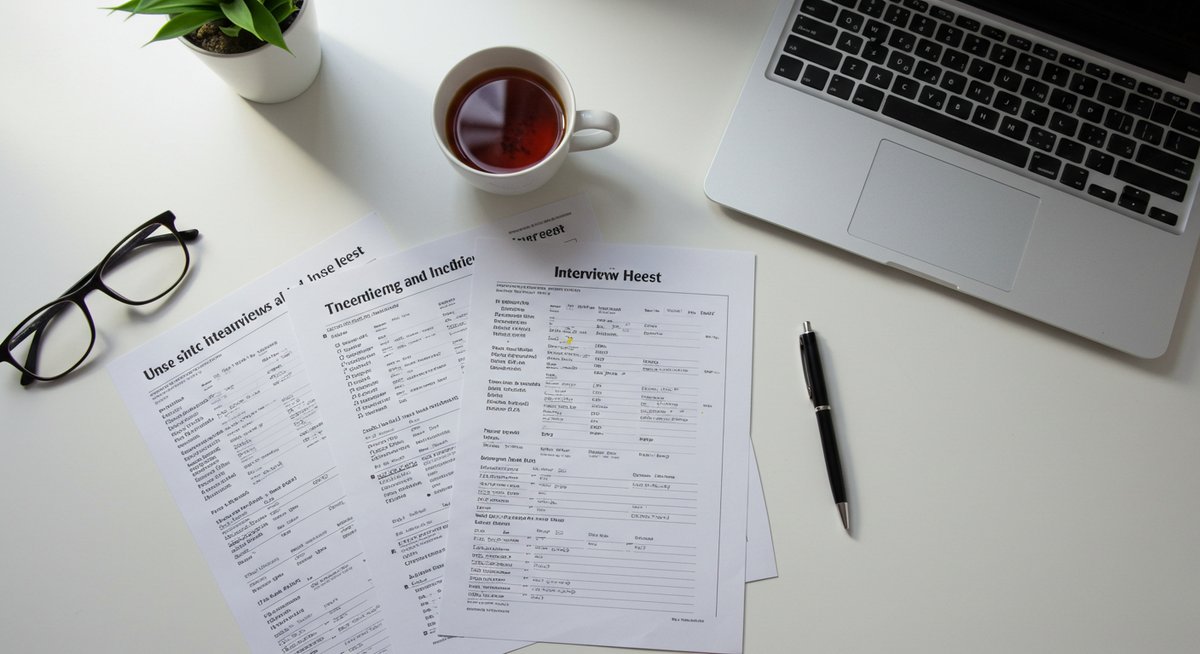
インタビュー当日から記事の完成までには、いくつかの重要な段階があります。一つひとつ丁寧に進めることで、充実した記事を実現できます。
アイスブレイクでリラックスした雰囲気を作る
インタビューの冒頭では、緊張をほぐすために軽い雑談や共通の話題からスタートするのが効果的です。たとえば、天気や近況の話、現場の雰囲気について触れることで、相手も話しやすくなります。
リラックスした状態が作れれば、自然な発言や本音を引き出しやすくなります。アイスブレイクは形式的なものではなく、相手の表情や反応を見ながら行うのがポイントです。
会話の録音録画とメモの取り方
インタビュー中は録音や録画を活用すると、後から発言の正確な内容を確認でき便利です。録音する場合は、事前に相手の許可を取りましょう。
一方で、重要なポイントや気づきをその場でメモしておくことも大切です。録音だけに頼ると、インタビュー後に要点を見失いがちなので、発言の要点や印象に残ったキーワードは、簡潔にメモしておくと整理しやすくなります。
発言の要点整理と具体例の引き出し方
インタビュー後は、録音データやメモをもとに、発言の要点を整理しましょう。話が広がった部分や印象的なエピソードをピックアップし、記事の構成に活かします。
また、抽象的な話題が多い場合は「具体的な例を教えてください」と追加質問することで、読者がイメージしやすい内容にできます。要点をまとめる際は、インタビューの流れやストーリーが途切れないよう注意しましょう。
記事執筆時に意識すべき構成と編集ポイント
記事を執筆する際は、導入・本編・まとめといった基本的な構成を意識し、内容が分かりやすく流れるよう編集します。特に、読者がどこで興味を持つか、どこで理解しやすくなるかを意識した見出しや段落分けが重要です。
冗長な表現や繰り返しは避け、必要な情報を過不足なく盛り込むことがポイントです。インタビュー対象者の発言は、なるべくそのままのニュアンスで掲載し、編集の手を加える際も意味が変わらないよう配慮しましょう。
読者を惹きつけるインタビュー記事テンプレート活用術
インタビュー記事は、テンプレートを上手に活用することで、読者の興味を引きやすいコンテンツへと仕上げられます。ここでは具体的な工夫のポイントを紹介します。
タイトルやリード文で興味を引く方法
タイトルやリード文は、記事の印象を大きく左右します。タイトルは、インタビュー対象者の特徴や強み、読者が得られる価値を簡潔に伝えることが重要です。「〇〇が語る、仕事のやりがい」など、具体性のある表現が効果的です。
リード文(冒頭の導入部)では、インタビューの背景や読みどころを簡単にまとめ、読者が続きを読みたくなるような問いかけやエピソードを盛り込みましょう。冗長になりすぎないよう、150字~200字程度を目安に整理します。
ビジュアルやキャプチャの効果的な使い方
文章だけでなく、写真やイラスト、グラフなどのビジュアル要素を効果的に組み合わせることで、記事の説得力や分かりやすさが向上します。たとえば、インタビュー中の表情や現場の様子が伝わる写真を掲載すれば、読者の関心も高まります。
また、発言内容を図やキャプチャで補足することで、情報の理解を助けることができます。ただし、ビジュアルが過剰になると読みづらくなるため、全体のバランスを考えて配置しましょう。
プロフィールや背景情報の盛り込み方
インタビュー対象者のプロフィールや経歴、背景情報は、記事全体に信頼感や説得力を与えます。記事冒頭や適切な場所に、簡単な表や箇条書きでまとめると効果的です。
読者にとっては、「どんな人が語っているのか」が分かることで、内容への共感や興味が深まります。経歴や実績だけでなく、趣味や人柄を伝える情報も加えると、親しみやすい印象になります。
#### プロフィール表の例
| 名前 | 経歴 | 趣味 |
|---|---|---|
| 佐藤 健 | IT企業で10年勤務 | 写真撮影 |
まとめ部分で伝えるべき要点と余韻の作り方
記事のまとめ部分では、インタビューの主なポイントや読者へのメッセージを簡潔に伝えます。内容を振り返りつつ、今後に期待できる展開や、対象者からの一言コメントを加えると、読後感が良くなります。
また、読者に「自分も挑戦してみたい」「もっと知りたい」と思ってもらえるような余韻を残す表現を意識しましょう。まとめ部分が丁寧に作られていると、記事全体の印象もより良くなります。
まとめ:インタビュー記事テンプレートで質と効率を両立するコツ
インタビュー記事テンプレートを活用することで、効率的に質の高い記事を作成できます。形式や目的に合わせて柔軟にカスタマイズし、事前準備や取材の流れを丁寧に進めることが成功のポイントです。
テンプレートは作業を時短するだけでなく、情報の整理や構成の明確化にも役立ちます。読者のニーズに寄り添い、分かりやすく魅力的なインタビュー記事を目指して、今回紹介したポイントをぜひ活用してみてください。









