JANコードの取得方法を最短でわかりやすく解説|申請から印刷・管理までの流れ
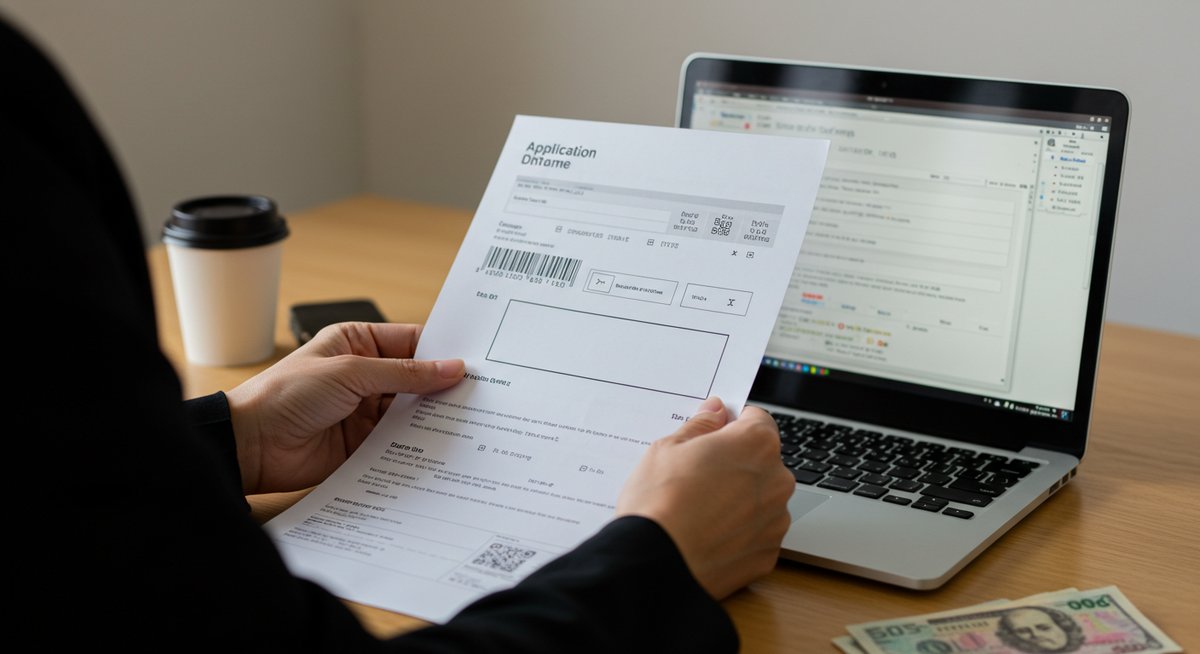
商品にJANコードを付けたいけど、どこから始めればよいか迷っていませんか。この記事では申請から管理まで、今日から始められる流れをわかりやすくまとめます。書類準備や費用、よくある失敗とその回避法まで順を追って説明しますので、初めての方でも落ち着いて手続きを進められます。
janコードの取得方法を今日から始められる流れ

申請全体の工程を短くまとめる
JANコード取得は大きく分けて申請準備、申請手続き、コード発行、コードの割り当て・印刷準備、運用開始の5つの工程です。まずは必要書類を確認して、事業者情報を整理します。次にGS1(日本では一般社団法人流通システム開発センターなど)への申請フォームに必要事項を入力し、登録料を支払います。
申請が受理されると事業者コードが発行され、各商品に割り当てるためのアイテムコードを自社で決められます。チェックデジットの算出とJANシンボルの作成を行い、ラベルやパッケージに印刷して流通先へ登録します。最後に在庫管理やEC連携の設定を済ませれば完了です。全体を把握して順を追えば、手続きの抜け漏れが少なくなります。
かかる日数と費用の目安
申請から事業者コード発行までの所要時間は、申請内容や支払い方法によりますが、通常は数日から数週間が目安です。オンライン申請で不備がなければ比較的早く処理されますが、書類不備や追加確認が入ると延びることがあります。
費用は初回の登録料と年ごとの基本料金が必要です。金額は組織の種類や規模により異なりますが、個人事業主や小規模事業者向けの低価格帯プランもあります。さらに、JANシンボルの作成や印刷費用、バーコード作成ソフトや外注費も考慮してください。見積もりを事前に取り、初期費用とランニングコストを分けて計算すると資金計画が立てやすくなります。
よくある失敗例と避け方
よくある失敗は、申請情報の誤記入、必要書類の不足、既存コードとの重複などです。申請情報は法人名・住所・代表者名・電話番号など正確に記入し、登記事項証明書や本人確認書類を事前に用意してください。
アイテムコードの設計をうっかりすると後で番号が足りなくなったり、重複してしまうことがあります。社内で管理ルールを決め、記録を残すことが重要です。印刷時のバーコードサイズや配置基準に従わないと読み取りエラーが発生するため、印刷会社と仕様を共有して確認しましょう。
今すぐ始めるための最初の一歩
まずは自社の情報と必要書類をそろえることから始めてください。会社名や所在地、代表者名、事業の概要が分かる書類を用意し、申請先の公式サイトで必要事項と料金を確認します。オンラインでの申請が可能であればアカウント登録を行い、申請フォームに入力する準備をしておきます。
同時に社内でアイテムコードの付け方や管理方法の方針を決めると、その後の作業がスムーズになります。最初の一歩を踏み出せば、あとは案内に沿って一つずつ進められます。
申請前に準備することと確認項目

個人でも申請できるか
個人事業主でも申請は可能です。ただし、申請時には事業としての連絡先や氏名、住所などを明確にする必要があります。法人と比べて料金体系や割当数に違いがある場合があるので、申請先の案内を確認してください。
個人の場合は本人確認書類や開業届の写しなど、事業であることを示す書類の提出が求められることがあります。将来的に法人化する予定がある場合は、そのタイミングで再登録や情報変更が必要になる点も意識しておくとよいでしょう。
必要書類の一覧と準備方法
通常求められる書類は以下のとおりです。
- 申請者の身分証明書(運転免許証など)
- 法人の場合は登記事項証明書
- 事業を示す書類(開業届や請求書のサンプルなど)
- 代表者の印鑑または署名
これらはスキャンしてオンラインで提出するか、郵送で送る場合があります。提出前に書類の有効期限や名称が正しいかを確認し、読みやすい状態で用意してください。コピーの取り方や押印の有無など細かな指示がある場合は、それに従って整えます。
登録料と更新料の違い
登録料は初回に支払う金額で、事業者コード発行のための費用です。更新料は年次でかかる維持費に相当し、コードを有効に保つために支払います。金額や支払頻度は申請先の規定により異なるため、事前に詳細を確認してください。
支払い方法も複数あり、クレジットカードや銀行振込、請求書払いなどが選べる場合があります。登録料と更新料を区別して予算を立て、支払期日を忘れないよう管理しましょう。
事業者コードの割当数の確認方法
事業者コードに対して割り当てられるアイテムコードの桁数や数は、申請時に選ぶプランによって異なります。申請先のガイドラインや契約書に記載されているので、申請前に確認してください。
商品点数が多い場合は余裕を持った割当数を選ぶとよいです。不足する場合は追加申請や上位プランへの変更が必要になるため、販売計画を基に見積もりを行い、将来の拡張を考慮して決めてください。
GS1事業者コードの登録手続きの進め方

申請フォームの入力で注意する点
申請フォームには会社情報や連絡先、事業内容、希望するコードの種類などを入力します。誤字脱字があると手続きが止まることがあるので、入力後に必ず見直してください。法人番号や登記名義は公的書類と同じ表記に揃えることが重要です。
担当者のメールアドレスは通知が届くため、普段使っているものを登録しましょう。複数の担当者がいる場合は連絡先を補足欄に記載しておくと、問い合わせ時にスムーズです。また、アイテムコードの割当方針についてもあらかじめ記載しておくと、後の運用が楽になります。
登録申請料の支払い方法
支払い方法はオンライン決済や銀行振込、請求書払いなどが選べます。オンライン申請でカード決済が使える場合は手続き完了が早くなることが多いです。振込を選ぶ場合は振込先や期日を確認し、入金後の連絡を忘れないようにしてください。
領収書や支払い完了の証明は保管しておきます。将来の更新料や変更手続きの際に参照することがあるため、整理しておくと安心です。
申請後の処理と通知までの流れ
申請が受理されると、申請内容の確認や審査が行われます。書類に不備がなければ事業者コードが発行され、メールや郵送で通知されます。通常は数日〜数週間かかりますが、時期や申請件数によって変動します。
通知には事業者コードの他、利用上の注意や次の手続きについての案内が含まれることが多いです。届いた情報は社内で共有し、アイテムコードの付番作業や印刷準備に進んでください。
申請が却下された場合の対応
却下理由は申請情報の不備や書類の不足、申請条件を満たしていないことなどが考えられます。まずは通知に記載された理由を確認し、必要書類を整えたり誤記を修正して再申請してください。疑問点があれば申請窓口に直接問い合わせて、具体的な修正方法を確認すると時間短縮になります。
再申請の際は前回の指摘事項を反映し、同じミスを繰り返さないようチェックリストを用意しておくとよいでしょう。
JANコードの作成と印刷に必要な手順

アイテムコードの決め方の基本
アイテムコードは事業者ごとに管理する部分で、商品ごとに一意になるように設定します。先頭桁や桁数は事業者コードの仕様に合わせて決め、カテゴリごとに範囲を割り当てると管理が楽になります。製品ラインやサイズ違い、色違いなどは末尾の数値で区別する方法が一般的です。
混乱を防ぐために命名規則を文書化し、担当者に共有してください。変更履歴を残しておくと、過去のコードと照合する際に便利です。
チェックデジットの計算方法
チェックデジットはJANコードの最後の1桁で、誤読を検出するために使います。計算は決まったアルゴリズムに従って行います。手計算でも求められますが、オンラインの計算ツールやバーコード作成ソフトを使うと簡単です。印刷前にチェックデジットが正しいか確認することが重要です。
チェックデジットが間違っていると読み取り機でエラーが出るため、必ず確認作業を入れてください。
JANシンボルの印刷基準と配置
バーコードのサイズや余白(クリアゾーン)、解像度など、印刷基準は厳格に定められています。小さすぎると読み取りに失敗し、余白が不足すると周囲のデザインに干渉して読み取れないことがあります。パッケージ上の配置は平面で読み取りやすい場所を選んでください。
印刷前にテスト印刷を行い、実機でスキャンしてから量産に進むと安心です。印刷業者と基準を共有してチェックしてもらいましょう。
ラベルや包装への印刷条件
印刷する素材によってはバーコードが歪む場合があります。光沢紙や箔押し、曲面包装は読み取りに影響を与えるため、適切な印刷方法とインクを選んでください。耐摩耗性や温度変化に強いインクを使うと品質が保てます。
包装に直接印刷する場合は、印刷位置を固定し、データのズレが無いよう工程管理を行います。大ロットではサンプルチェックを必ず入れてください。
既存番号との重複を防ぐ方法
自社で付与するアイテムコードは重複を避けるために一元管理することが大切です。社内データベースやスプレッドシートで既存番号を管理し、検索機能を活用して新たな番号が未使用であることを確認します。
複数部門で付番する場合は、担当者ごとに割り当て範囲を決め、定期的な監査で重複がないか確認するルールを設けてください。
取得後の管理と運用で活用する方法
コード管理のおすすめルール
コードは発行日や商品情報、担当者名を記録しておくと追跡しやすくなります。管理台帳を用意し、変更履歴や廃番情報も残してください。データベース化すると検索や絞り込みが楽になり、在庫管理や販売分析にも活用できます。
定期的に監査を行い、重複や誤登録がないかチェックする体制を整えることが重要です。
ECサイトや流通への登録手順
ECサイトや流通業者への登録では、JANコードと商品情報(商品名、サイズ、色、重量、寸法など)を正しく紐付ける必要があります。各プラットフォームの登録フォームに従い、画像や説明文も用意してください。
UPCやGTINなど他形式が求められる場合は変換や対応を確認し、必要に応じてデータを整備します。登録後は商品ページでバーコードが正しく表示されるかをチェックします。
在庫管理での活用例
JANコードはピッキングや棚卸し、入出庫管理で役立ちます。バーコードスキャナを使えば処理速度が上がり、人的ミスを減らせます。ロット管理や賞味期限管理とも組み合わせると、より正確な在庫管理が可能になります。
データを分析して回転率の低い商品を洗い出し、発注計画に反映させることもできます。
複数商品の一括管理方法
多数の商品を扱う場合は、SKUとJANコードを組み合わせたデータベースで一括管理すると効率が良くなります。CSVでの一括登録や更新機能を使えば、変更作業を自動化できます。
バーコード生成ソフトや在庫管理システムと連携させることで、登録・印刷・在庫更新の流れをスムーズにできます。
janコード取得はこの手順でスムーズに進む
ここまでの流れを順に進めれば、初回の申請から運用まで無理なく進められます。まずは必要書類をそろえ、申請先の案内に沿って登録を行い、事業者コード発行後はアイテムコードの付番や印刷準備を進めてください。運用面では管理ルールを整え、在庫や販売と連携させることでJANコードの利点を十分に生かせます。









