オウンドメディアのCVR平均はどれくらい?業界別の傾向や向上の具体策を徹底解明

集客や売上アップのためにオウンドメディアを運営しているものの、コンバージョン率(CVR)が伸び悩んでいる、と感じていませんか。どのくらいのCVRが適切なのか、また他社と比べて自分たちの成果がどうなのか、気になる方も多いでしょう。
この記事では、CVRの基本から業界ごとの平均値、CVR改善の具体策や成功事例まで、実践的な内容を丁寧に解説します。自社メディアの成果を正しく評価し、今後の施策に役立てたい方はぜひご一読ください。
オウンドメディアのCVR平均を正しく理解するために

オウンドメディアのCVR(コンバージョン率)は、サイト運営の効果を測る重要な指標です。しかし、平均値や業界ごとの差など、正しく理解できていないケースも多く見受けられます。
CVRとは何かをわかりやすく解説
CVRとは、Webサイトを訪れたユーザーのうち、何パーセントが目的のアクション(コンバージョン)を達成したかを示す指標です。ここでいうコンバージョンは、商品購入や資料請求、会員登録、問い合わせなど、サイトごとに異なります。
たとえば、100人がサイトを訪問して5人が資料請求をした場合、CVRは5%となります。CVRは、集客の質やサイトの使いやすさ、コンテンツの訴求力など、さまざまな要素の総合的な成果を表すため、サイト改善の際に非常に重視される数字です。
オウンドメディアのCVRの計算方法
オウンドメディアのCVRは、次の計算式で求められます。
- CVR(コンバージョン率)=コンバージョン数 ÷ サイト訪問数 × 100
たとえば月間1,000人が訪問し、30人が問い合わせフォームから送信した場合、CVRは「30÷1,000×100」で3%となります。この計算式を使えば、どのタイミングで、どのページが成果に寄与しているかを把握できます。
なお、計測する期間やコンバージョンの定義はサイトごとに異なることも多いです。比較するときは、同じ条件で算出することが大切です。
業界ごとのCVR平均値の違い
オウンドメディアのCVRは、業界やビジネスモデルによって大きく異なります。購買や申込のハードルが高い商品・サービスほど、一般的にCVRは低くなる傾向があります。
たとえばBtoB(企業向け)の資料請求やお問い合わせはCVRが1%程度というケースが多く、一方でBtoC(一般消費者向け)のECサイトでは3~5%程度になることもあります。同じCVRでも業界によってその評価は変わるため、自社業界の平均値を知っておくことが重要です。
コンバージョンポイントによるCVRの差
オウンドメディアでは、設定するコンバージョンの種類によってCVRに差が生じます。たとえば「会員登録」や「メールマガジン登録」など、比較的手軽な行動はCVRが高くなりやすいです。
一方、「商品購入」や「有料サービスの申し込み」など、ユーザーにとってリスクや負担が大きいアクションはCVRが低くなることがあります。自社のCVR評価を行う際は、どのコンバージョンポイントを基準にするかを明確にしておくことが大切です。
オウンドメディアにおけるCVRの重要性
オウンドメディアのCVRは、単なる数値ではありません。どれだけ多くの人がサイトを訪れても、成果につながらなければ意味が薄れてしまいます。
CVRを改善することで、広告費やSEO施策の費用対効果を高めることができます。既存のアクセスからより多くの成果を生み出せるため、限られたリソースで大きな成果を出したい企業にとって欠かせない指標といえます。
オウンドメディアのCVR平均値と業界別傾向
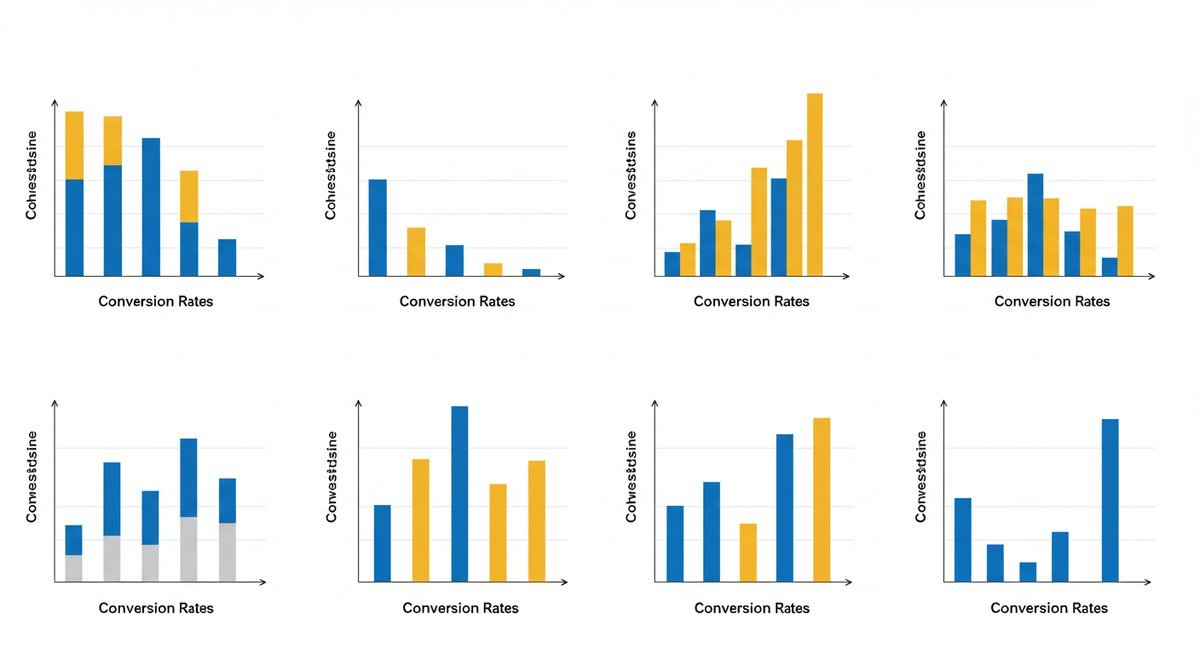
CVRの平均値がどの程度なのかは、業界やビジネスモデルによって大きく変わります。自社の現状を正しく把握するためにも、全体の傾向を知っておくと役立ちます。
BtoBとBtoCで異なるCVRの特徴
BtoBサイトは、個人向けに比べてコンバージョンに至るまでの検討期間が長く、意思決定者も複数いるため、CVRが低くなる傾向があります。実際、BtoBオウンドメディアの主要コンバージョン(問い合わせや資料請求)のCVRは0.5~2%ほどが一般的です。
一方、BtoCサイトは、購入や登録などのアクションが直感的に選ばれやすい傾向があり、比較的CVRが高くなることが多いです。ただし、商品の単価やブランド力によってもCVRは変動しやすいため、単純な比較ではなく、自社の業態やターゲットに即した分析が必要です。
主要業界ごとのCVR平均値ランキング
主要な業界ごとのCVR平均値は以下の通りです。あくまで参考値となりますが、目標設定の際の一助となります。
| 業界 | 平均CVR(目安) | 主なコンバージョン例 |
|---|---|---|
| EC(物販) | 2~5% | 購入・カート追加 |
| 不動産 | 0.5~1.5% | 資料請求・来店予約 |
| 金融・保険 | 1~3% | 見積もり・相談申込 |
| BtoBサービス | 0.5~2% | 問い合わせ・資料請求 |
業界によっては、同じ業種でも商品単価・サービス内容によって平均値は前後します。定期的に自社の計測値を見直すことが大切です。
CVR平均値の目安と基準値
一般的に、オウンドメディアのCVRは1~3%が一つの目安とされています。しかし、業界やサイトの目的によってこの基準は変わります。
たとえば「新規会員登録」や「無料資料請求」の場合、3%を超えるCVRを目指す企業もあれば、高額商材の販売では1%前後でも十分な成果と見なされることもあります。基準値を決める時は、他社比較も参考にしつつ、自社のKPIや事業目標に沿って設定しましょう。
コンバージョン地点によるCVRの違い
オウンドメディア内には、複数のコンバージョン地点が存在することも多いです。例えば、記事ページから直接商品ページへ誘導する場合と、問い合わせフォームへの誘導ではCVRが大きく異なります。
- 記事→商品購入:1~3%
- 記事→無料登録:3~7%
- 記事→お問い合わせ:0.5~2%
CVRを分析する際は、どの地点を評価対象とするか明確にし、同じ条件でデータを比較することが重要です。
競合メディアと自社メディアのCVR比較
自社のCVRを把握したうえで、競合他社のオウンドメディアと比較することも効果的です。競合よりCVRが低い場合は、導線やコンテンツに課題が潜んでいる可能性があります。
ただし、競合の正確な数値は開示されていないことが多いため、公表されている事例や業界平均、または外部調査会社のデータを活用するのが現実的です。競合比較を行う際は、サイト規模やコンバージョンの定義が異なる点に注意しましょう。
オウンドメディアのCVRを向上させる具体策

CVRの数値は、ちょっとした改善でも大きく変化します。ここでは、実際に取り組みやすいCVR向上施策を具体的に紹介します。
コンテンツの質とターゲティングの最適化
ユーザーにとって価値ある情報を届けることが、CVRを高める第一歩です。読者の悩みに寄り添った具体的な解決策やノウハウを提供しましょう。
また、ターゲットとなるユーザー像(ペルソナ)を明確に設定し、その人たちに響くコンテンツを作成することも大切です。たとえば、年代や職業、興味関心に合わせて文章のトーンや掲載する事例を変えることで、伝わりやすさが大きく向上します。
導線設計と回遊性の強化
ユーザーが自然とコンバージョンにたどりつけるよう、サイト内の導線を設計しましょう。記事下やサイドバーに関連コンテンツやCTA(行動喚起)を配置することで、自然な流れを作ることができます。
回遊性を高めるためには、内部リンクの設置も重要です。おすすめ記事や人気記事へのリンクを設けたり、「次に読むべき記事」をレコメンドすることで、サイト滞在時間が延び、CVR向上につながります。
CTAボタンと入力フォームの改善ポイント
CTAボタンの文言やデザイン、設置場所を工夫すると、CVRの向上が期待できます。「無料」「簡単」「今すぐ」など、ユーザーにメリットが伝わる言葉を選びましょう。
入力フォームも、項目数を絞ったり入力しやすい順序にしたりと工夫が必要です。たとえば、必須項目だけに絞ったシンプルなフォームにすることで、離脱を減らせます。エラーメッセージや入力補助もCVR改善には効果的です。
マイクロコピーやABテストの活用
マイクロコピーとは、フォームやボタン付近に表示される短い説明文のことです。たとえば「個人情報は厳重に管理します」といった一言で、安心感を与え離脱防止につながります。
また、ABテストを実施し、ボタンの色や文言、表示位置など細かな違いがCVRにどう影響するか確かめることも有効です。小さな改善を積み重ねながら、最適なパターンを見出していくことが重要です。
LPOとEFOによる成果最大化手法
LPO(ランディングページ最適化)やEFO(入力フォーム最適化)は、CVR向上に直結する施策です。ランディングページでは、ファーストビューでユーザーの心をつかむ構成や、信頼感を高める実績紹介などを意識しましょう。
EFOでは、項目ごとのガイド表示や、入力内容の自動補完など、ユーザーの負担を減らす工夫がポイントです。これらを組み合わせて実施することで、順調にCVRを高めることができます。
CVRが伸び悩む原因とすぐできる改善チェックリスト

CVRが思うように上がらない場合には、原因を特定し、すぐに取り組める改善策をチェックしましょう。
ユーザー目線の不足がもたらす影響
サイト運営者側の視点だけでコンテンツや導線を作ると、ユーザーの本当の悩みや使い勝手に気づかないことがあります。たとえば専門用語が多すぎたり、情報が整理されていない場合、離脱の原因となります。
実際のユーザーがどう感じるかを定期的にヒアリングしたり、アンケートを行うことで、サイト改善のヒントが得られます。ユーザー目線を徹底することが、CVR改善の大きな第一歩です。
サイト構成やコンテンツのミスマッチ
ターゲットユーザーのニーズと、実際に用意されているコンテンツやサイト構成がずれていると、CVRは思うように上がりません。たとえば初歩的な情報を求める人に専門的な内容ばかりを提示しても、成果にはつながりにくいです。
コンテンツの質だけでなく、ナビゲーションの分かりやすさや、重要な情報へのアクセスしやすさも見直しましょう。初訪問者にも分かりやすいサイト設計が重要です。
競合状況や市場トレンドの変化
競合他社のメディアや商品・サービス内容の変化、市場全体のトレンドの変化に気づかず、旧来のままの内容を提供し続けると、CVRが下がることがあります。
定期的に競合調査を行い、自社の強みや独自性が十分に訴求できているかを確認しましょう。また、最新のキーワードや話題を盛り込むことも有効です。
タグ設定や計測ミスへの注意点
Googleアナリティクスやコンバージョンタグの設置ミスにより、正しいCVRが計測できていないケースも少なくありません。特にサイトリニューアルや新機能追加時は注意が必要です。
定期的にタグの動作テストや、複数の解析ツールによるクロスチェックを行い、計測ミスを防ぎましょう。数字の信頼性を高めることが改善活動の前提となります。
KPI設定と効果測定のポイント
KPI(重要業績評価指標)を明確に設定しないまま施策を進めてしまうと、効果が分かりにくくなります。CVRをKPIの一つに据え、定期的な進捗確認と目標の見直しを行いましょう。
また、短期的な数値だけでなく、リードの質や顧客化率といった“その先”の指標もあわせてウォッチすることが重要です。成果を正確に評価し、柔軟に改善策を加えていく体制を整えましょう。
CVR分析と改善に役立つおすすめツール
CVRの分析や改善には、専用ツールの活用が有効です。ここでは、代表的なツールやその選び方をまとめました。
GoogleアナリティクスでのCVR分析
Googleアナリティクスでは、コンバージョンごとのCVRや、ページごとの成果を細かく分析できます。目標設定を行い、訪問経路や流入チャネルごとの数値も可視化可能です。
たとえば「どのページからの流入が最もCVRが高いのか」「どのデバイスで成果が出ているのか」など、さまざまな角度から分析できるため、改善点の特定に役立ちます。
ヒートマップツールを使ったユーザー行動の可視化
ヒートマップツールを使うと、ユーザーがどこをクリックしているか、どこまでスクロールして読んでいるかが一目で分かります。これにより「よく見られている部分」「離脱ポイント」などが可視化できます。
たとえば、CTAボタンの位置が目立たない場合や、重要な情報が下の方にあって見られていない場合など、サイト改善に直結する気づきを得ることができます。
ABテストやLPOツールの活用法
ABテストツールやLPO(ランディングページ最適化)ツールを使うことで、ボタンの色やテキスト、ページレイアウトの違いがCVRにどれほど影響するかを実証できます。
複数パターンを同時に公開し、ユーザーの反応を計測しながら最適なパターンを選定できるため、感覚だけでなくデータに基づいた改善が可能です。
マーケティングオートメーションツールの導入メリット
マーケティングオートメーション(MA)ツールを使えば、ユーザーの属性や行動履歴にもとづいた最適な情報配信が自動化できます。これにより、見込み顧客へのアプローチ精度が高まり、CVRの向上につながります。
メール配信やセグメントごとのパーソナライズ施策、スコアリング機能など、リードの育成やCVR改善に役立つ機能が豊富です。導入を検討してみるのも良い方法です。
外部コンサルティングや支援サービスの選び方
自社だけでは行き詰まりを感じた場合、外部の専門家に相談するのも一つの選択肢です。コンサルティング会社やWeb施策支援サービスを利用することで、第三者視点からの分析や、具体的な改善提案が受けられます。
選ぶ際は、業界経験や実績、施策提案の具体性などを比較しましょう。初回の無料相談や実績公開がある会社を選ぶと安心です。
成功事例から学ぶオウンドメディアCVR改善のヒント
実際にCVR改善に成功した事例を知ることで、自社に取り入れられるヒントが見つかります。ここでは分野ごとの代表的な事例を紹介します。
BtoB企業の問い合わせ増加事例
あるBtoB企業では、資料請求フォームの入力項目を7個から3個に減らし、マイクロコピーで「1分で完了」と明記したことで、CVRが1.2%から2.0%へと大幅に向上しました。
また、よくある質問をフォームの横にまとめて掲載したことで、安心感が増し、離脱率が減少した点も効果的でした。ユーザーの心理的負担を減らす工夫が奏功しています。
BtoCサイトの購入率アップ事例
BtoCのECサイトでは、商品ページのレビュー表示や、限定キャンペーンのバナー追加によってCVRを高めた事例が見られます。利用者の声を積極的に紹介したことで、購買への後押しが強まりました。
さらに、決済方法の多様化やスマートフォン対応の強化も、成果向上に寄与しています。購入に至るまでの“障壁”を一つひとつ取り除くことが大切です。
動画やSNS連携によるCVR向上事例
動画コンテンツを記事やランディングページに導入したことで、サービス内容の理解度が上がり、CVRが上昇した例があります。特に、使い方紹介やお客様の声を動画で伝えることで、安心してコンバージョンできる環境が整いました。
また、SNS連携により、キャンペーンや新着情報をタイムリーに拡散し、再訪問やリピーターからのCVR向上につなげたケースもあります。
フォーム改善だけで成果が伸びた事例
ある企業では、フォームの入力補助機能を充実させたことで、途中離脱が大幅に減少しました。郵便番号自動入力やリアルタイムのエラーチェックなど、細かな使い勝手への配慮が成果向上につながっています。
また、入力後すぐに「完了まであと2ステップ」と表示することで、ユーザーにゴールが近いことを伝え、モチベーションを維持できました。
コンテンツリニューアルによるCVR改善事例
古くなった記事を最新情報に書き換えたり、図解や表を追加して分かりやすくした結果、CVRが2倍以上になった事例も報告されています。特に、SEOキーワードも見直し、検索経由の質の高い流入を増やすことで、成果につながりました。
コンテンツの定期的なリニューアルと、ユーザー目線での情報整理は、CVR改善の基本施策のひとつです。
まとめ:オウンドメディアのCVR平均値を活用して成果を最大化しよう
オウンドメディアのCVRは、業界やコンバージョン内容によって大きく異なります。自社の現状と業界平均値を比較し、的確な目標設定を行うことで、施策の成果を正しく評価できます。
効果的な改善策を実践し、定期的な分析と見直しを繰り返すことで、限られたアクセスから最大限の成果を引き出すことが可能です。今回紹介したツールや成功事例もぜひ参考に、貴社のメディア運営に役立ててください。









