サービスドミナントロジックとは何か?企業に必要な価値共創の考え方を事例から学ぶ

集客やマーケティングを考えるとき、「売れる仕組み」をどう作ればよいか悩む方は多いものです。特に、商品やサービスが溢れる現代では、従来のやり方だけでは差別化が難しくなりました。
そんな中で注目されているのが「サービスドミナントロジック」という考え方です。これは、モノではなく体験や価値の共有に焦点を当てた考え方で、今多くの企業が取り入れ始めています。
ここでは、サービスドミナントロジックの基本や特徴、導入事例、ビジネスで活用する方法、そして今後の課題まで、やさしく分かりやすく解説していきます。
サービスドミナントロジックとは何かを分かりやすく解説

近年注目を集める「サービスドミナントロジック」は、商品ではなくサービスや体験を大切にするマーケティングの新しい考え方です。
サービスドミナントロジックの基本的な考え方
サービスドミナントロジックは、商品やサービスを通じて「顧客と一緒に価値を生み出す」という発想が特徴です。これまでの「モノを売る」考え方では、商品を作ってお客様に届けることが中心でした。しかしサービスドミナントロジックでは、商品そのものではなく、商品やサービスを通じて得られる体験や価値を重視します。
たとえば、あるカフェが「美味しいコーヒー」と「くつろげる空間」を提供しているとしましょう。ただコーヒーを売るだけでなく、「お客様が心地よく過ごせる時間」を一緒に作り出すことこそが、本当の価値だと考えます。そのため、企業と顧客がコミュニケーションを深めながら、互いに価値を作りあげていく点が大きなポイントです。
サービスドミナントロジックが注目される背景
サービスドミナントロジックが注目される背景には、消費者ニーズの多様化と、商品が簡単に比較されやすくなったことがあります。インターネットの普及により、情報はすぐに手に入り、どの商品も似たようなものに見える時代になりました。
そのため、単に「良いモノ」を作るだけでは選ばれにくくなっています。こうした中、顧客一人ひとりの体験や満足度を重視し、企業と顧客が一緒になって価値を生み出すサービスドミナントロジックが、多くの企業で注目されるようになったのです。また、SNSなどを通じて顧客の声が直接企業に届くようになったことも、この流れを加速させています。
グッズドミナントロジックとの主な違い
サービスドミナントロジックとよく比較されるのが「グッズドミナントロジック」です。これは、モノそのものに価値があると考え、良い商品を作って販売することを重視する従来の考え方を指します。簡単に違いをまとめると、下表のようになります。
| 比較項目 | グッズドミナントロジック | サービスドミナントロジック |
|---|---|---|
| 価値の中心 | 商品そのもの | 顧客との体験・共有 |
| 企業と顧客の関係 | 一方通行(売り手→買い手) | 双方向(共に価値を創造) |
| 価値の生まれる場所 | 工場や店舗 | 顧客との接点や利用場面 |
このように、サービスドミナントロジックは「売って終わり」ではなく、購入後も含めて顧客とつながり続け、一緒に価値を作っていくという点が大きな違いです。
サービスドミナントロジックの提唱者とその歴史
サービスドミナントロジックは、アメリカのマーケティング研究者スティーブン・L・バルゴとロバート・F・ラッシュによって2004年に提唱されました。彼らは、従来の「モノ中心」の考え方から「サービス中心」の考え方へと大きく発想を転換しました。
この理論が発表されたことで、世界中の企業やマーケターたちが「ただ商品を作るだけでは市場で勝てない」と考え直すきっかけになりました。日本でも近年、この考え方を取り入れる企業が増えています。サービスドミナントロジックは日々進化しており、今後さらに多くの業界で重要視されていくでしょう。
サービスドミナントロジックの特徴とメリットを理解する
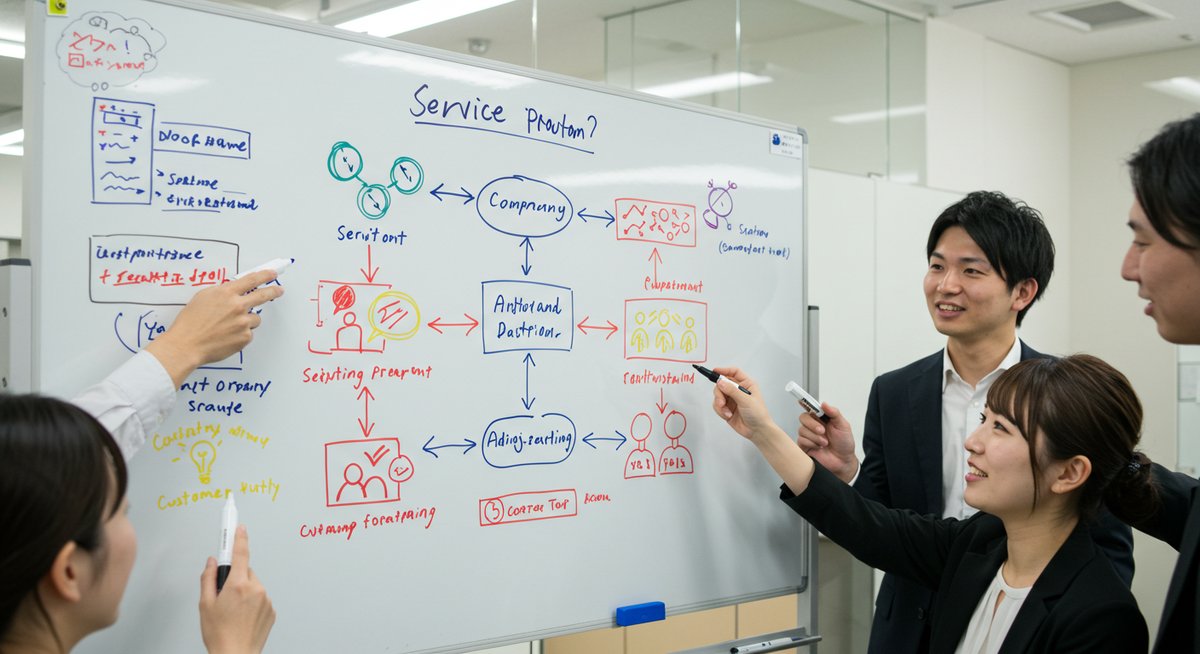
サービスドミナントロジックには、体験や共創に重きを置く独自の特徴があり、企業にも顧客にも多くのメリットがあります。
使用価値と経験価値にフォーカスする理由
サービスドミナントロジックでは、商品そのものの価値よりも「使われる場面」や「得られる体験」に目を向けます。たとえば、ドリルを買う人は本当にドリル自体が欲しいのではなく、「壁に穴を開けるという体験」や、その先にある「便利さ」を求めています。
この考え方を取り入れることで、企業は単なる販売だけでなく、顧客の生活や仕事の中でどんな価値が生まれているかを見つめなおすことができます。結果として、より満足度の高いサービスや商品改善につながりやすくなります。
顧客との価値共創がもたらす効果
サービスドミナントロジックによって、企業と顧客が一緒に価値を作り上げる仕組みが生まれます。これにより、顧客は自分もサービスの一部を担っていると感じるようになり、より深い満足感や愛着を持つようになります。
具体的には、顧客の意見や提案を積極的に取り入れたり、コミュニティを作って交流を促進したりすることで、商品やサービスが顧客の要望に近づきやすくなります。その結果、リピート率や口コミの増加など、企業にとっても大きな効果が期待できます。
サービスドミナントロジックが企業にもたらすメリット
サービスドミナントロジックを取り入れることで、企業には多くのプラス面が生まれます。代表的なメリットを整理すると、以下の通りです。
- 顧客満足度の向上
- 他社との差別化がしやすくなる
- リピーターやファンの増加
- 長期的な信頼関係の構築
- 新しい事業やサービスアイデアの創出
このように、企業の成長につながる好循環が生まれやすくなります。特に、リピート客やファンの存在は、安定した売上や企業イメージの向上にも大きく貢献します。
サービスドミナントロジックを導入する際の注意点
サービスドミナントロジックの導入にはいくつか注意が必要です。まず、顧客とのコミュニケーションやフィードバックをしっかり行う体制を整えなければ、価値共創が思うように進まないことがあります。
また、従業員の意識や組織文化の変革も重要です。体験やサービスを重視する考え方が社内に浸透していない場合、形だけの導入で終わってしまうリスクがあります。導入時には、現場の声を聞きながら徐々に進めていくことが大切です。
サービスドミナントロジックの実践事例を紹介

実際にサービスドミナントロジックを取り入れている企業の事例を見ることで、理解がより深まります。ここでは代表的な5社の取り組みを紹介します。
無印良品の素のままポテトチップスに見る共創
無印良品は、顧客と一緒に商品を開発する取り組みを積極的に行っています。たとえば「素のままポテトチップス」は、SNSや公式サイトでお客様からの意見を集め、それをもとに商品化した例です。
顧客の声を開発段階から取り入れることで、「自分も商品作りに関われた」という実感を与えることができました。このように、顧客との共創を通じて、より愛着のある商品を生み出しています。
NIKEのNike Run Clubが実現する顧客体験
NIKEが展開する「Nike Run Club」は、ランニングの記録やコミュニティ機能を備えたアプリです。単なるランニングシューズの販売にとどまらず、「ランニングを楽しむ体験」をサポートしています。
アプリを通じて自分の成長を実感したり、他のユーザーとつながることができるため、NIKEブランドへの愛着が強まります。このように、商品を使う「体験」そのものを総合的に支える仕掛けが、サービスドミナントロジックの好例といえるでしょう。
Amazon Kindleによる電子書籍プラットフォーム
Amazon Kindleは、本を読むだけでなく、読書体験に多くの工夫を加えています。たとえば、しおり機能やハイライト、他の読者の感想を共有できるなど、単なる電子書籍端末以上の「体験価値」を提供しています。
さらに、作家と読者が直接やりとりできる場や、読者の声を反映した機能追加なども積極的です。こうした価値共創の姿勢が、Kindleの独自性となっています。
LEGO IDEASが生み出すファンとのコラボレーション
LEGOは「LEGO IDEAS」というプラットフォームを通じて、ファンが自分で考えた作品アイデアを投稿できる場を設けています。人気投票で一定数の支持を集めたアイデアは、実際に商品化される仕組みです。
この仕組みによって、LEGOファンは単なる消費者ではなく、「一緒に商品を生み出す仲間」として関わることができます。これがブランドへの愛着を高め、長期的なファンづくりにもつながっています。
ブリヂストンのリトレッドタイヤサービス
ブリヂストンは、タイヤの表面だけを張り替えて再利用する「リトレッドタイヤサービス」を展開しています。このサービスは、顧客の走行データや使用状況に合わせて最適なタイヤ管理を提案するなど、単なる「タイヤ販売」以上の価値を提供します。
顧客はコスト削減や環境負荷の軽減といったメリットを感じられ、ブリヂストンは長期的な信頼関係を構築できます。このように、利用後も続く関係性がサービスドミナントロジックの特徴です。
サービスドミナントロジックをビジネスに活かす方法

サービスドミナントロジックをビジネスで活かすためには、顧客理解や組織づくりなど、いくつかの重要な取り組みが必要です。
顧客理解を深めるためのアプローチ
顧客を深く理解するためには、まず「誰が」「どのように」自社の商品やサービスを利用しているのかを把握することが大切です。そのための具体的な方法には、次のようなものがあります。
- アンケートやヒアリングを定期的に実施する
- SNSや口コミ、レビューから顧客の声を収集する
- 顧客の行動データを活用し、利用パターンを分析する
こうしたデータをもとに、顧客がどんな価値を求めているのかを読み解くことで、より的確な商品やサービス改善につなげることができます。
顧客情報を整理し戦略に活用するステップ
顧客情報をうまく活用するには、まず情報を整理・分類し、その上で戦略にどう生かすかを考えることが必要です。主なステップは以下の通りです。
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 顧客情報の収集 | アンケート・Web解析など |
| 2 | 顧客データの整理・分類 | 属性や行動ごとにグループ化 |
| 3 | 分析と戦略立案 | ニーズや傾向を見極めて施策を練る |
このように段階ごとに進めることで、単なる数値に終わらせず、具体的な施策や改善案へとつなげていくことができます。
顧客からのフィードバックを活かしたサービス改善
顧客からのフィードバックは、サービスドミナントロジックを実践する上で欠かせません。たとえば、苦情や要望を丁寧に受け止め、素早く改善策を打ち出すことで、顧客との信頼関係が深まります。
また、ポジティブな意見も積極的に取り入れることで、企業の強みや新しい価値をさらに磨くことができます。こうした双方向のコミュニケーションを大切にしていくことが、継続的なサービス向上につながります。
価値共創を推進する組織づくりのポイント
サービスドミナントロジックを生かす組織づくりには、社員一人ひとりが「顧客と一緒に価値を作る」という意識を持つことが大切です。まずは、現場の声を重視し、従業員同士が意見を出し合える風通しの良い環境をつくりましょう。
また、顧客と直接関わる場面を増やしたり、社員が顧客の声や利用シーンを知る機会を設けたりすることも有効です。こうした積み重ねによって、組織全体で価値共創を推進する力が育まれます。
サービスドミナントロジックの今後と課題
サービスドミナントロジックを取り巻く環境は日々変化しており、今後の成長のためにはいくつかの課題や工夫が求められています。
変化する市場環境とサービスドミナントロジックの役割
市場環境が変化し続ける現代において、サービスドミナントロジックは企業に柔軟な対応力をもたらします。顧客ニーズや競争環境がめまぐるしく変わる中、常に顧客の体験や価値を見直し続けることが求められます。
この考え方を採り入れることで、企業は単なる「商品売り」から脱却し、長期的な関係や新たな市場創出につなげやすくなります。今後はより幅広い業界で、その重要性が増していくでしょう。
本来の事業軸を見失わないための工夫
サービスドミナントロジックを追求するあまり、企業が本来の軸や強みを見失ってしまうこともあります。顧客の声を重視しすぎて、経営方針がぶれてしまうケースも珍しくありません。
そのため、サービスドミナントロジックを実践する際は、自社のミッションや価値観を共有し続けることがポイントです。顧客の意見を取り入れながらも、ぶれない軸を持ち続けるバランスが大切です。
データ活用のリスクと限界を知る
顧客データの活用は非常に便利ですが、個人情報の管理やプライバシーへの配慮が欠かせません。データを重視しすぎるあまり、数値だけに頼った判断や、顧客の本当の気持ちを見落とすリスクも考えられます。
データはあくまで一つの参考情報として活用し、現場の声や直感も大切にしましょう。情報管理体制の強化や、社員教育も重要なポイントになります。
企業間ネットワークで広がる価値共創の未来
今後は、企業同士がつながって新しい価値を生み出す「企業間ネットワーク」がますます注目されるでしょう。異業種や競合他社と協力することで、これまでにないサービスや体験が生まれる可能性も広がります。
こうしたネットワークづくりは、自社だけでは解決できない課題への対応や、市場の拡大にもつながります。今後のサービスドミナントロジック実践において、重要なテーマとなるでしょう。
まとめ:サービスドミナントロジックで未来のビジネスを切り拓く
サービスドミナントロジックは、商品売りから価値共創へとビジネスの視点を変える考え方です。顧客体験を重視し、企業と顧客が一緒に価値を作ることで、長期的な関係や新しい市場の開拓が可能となります。
変化の激しい時代だからこそ、サービスドミナントロジックを取り入れ、自社の強みや個性を活かしたビジネス展開が今後ますます大切になっていくでしょう。









