シンボルマークデザインの基本とブランド価値を高める秘訣とは

シンボルマークは、企業やサービスのイメージを伝える大切な要素です。しかし、どのようにデザインすれば良いのか、何に気をつければブランドの魅力が伝わるのか、悩む方も多いのではないでしょうか。
この記事では、シンボルマークデザインの基礎から、良いデザインを作る条件、依頼時のポイントまで、分かりやすく解説します。初心者の方でも実践しやすいコツや注意点をまとめましたので、ぜひご参考にしてください。
シンボルマークデザインの基本を知ろう
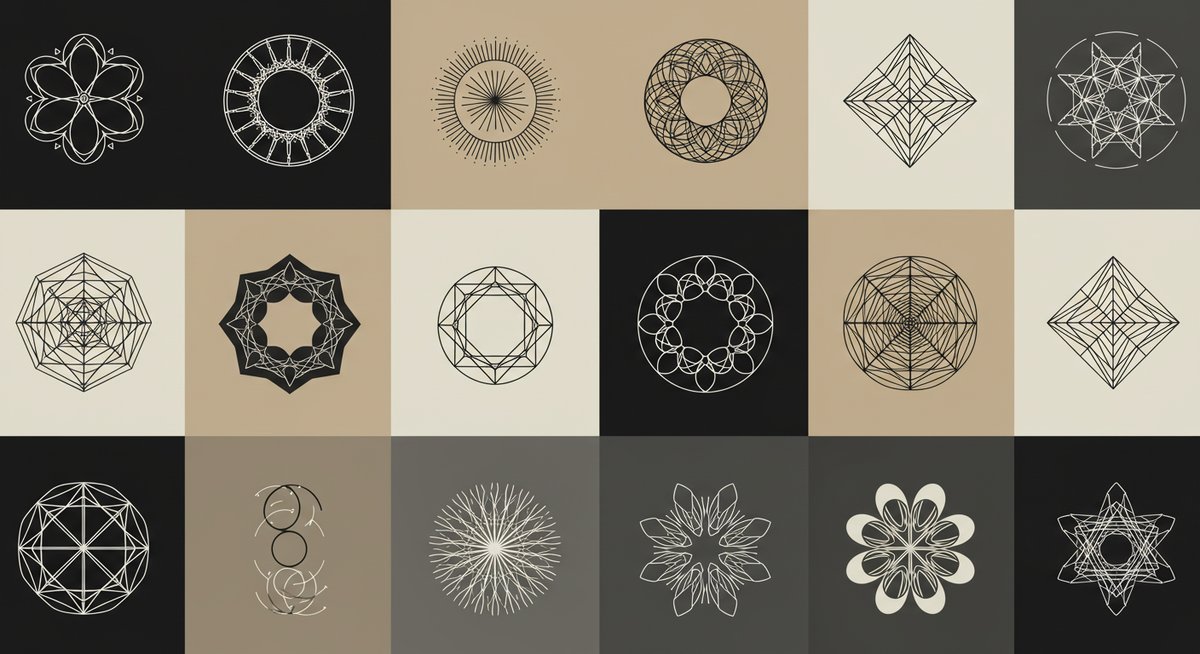
シンボルマークはブランドの顔となる存在です。まずは、基本的な役割や種類について確認していきましょう。
シンボルマークとロゴタイプの違い
シンボルマークとロゴタイプは、どちらもブランドを象徴するデザインですが、その役割や表現方法に違いがあります。
シンボルマークは「図形」や「アイコン」としてブランドを象徴するもので、動物や植物、抽象的な形などが多く採用されます。一方、ロゴタイプは社名や商品名など、文字そのものをデザインしたものです。たとえば、有名な企業の「マーク」と「文字ロゴ」が並んでいる場合、マーク部分がシンボルマーク、文字がロゴタイプです。両者を組み合わせて使うことで、より強くブランドを印象付けることができます。
シンボルマークが果たす役割
シンボルマークは、企業やサービスの個性を直感的に伝える役割を担っています。名刺やウェブサイト、広告など、さまざまな媒体で一貫したイメージを与える効果があります。
また、視覚的なインパクトが強いため、短時間でブランドを認識してもらいやすいことも特長です。覚えやすいマークは、多くの人に親しまれやすく、長く使われ続ける傾向にあります。
覚えておきたいデザインの流れ
シンボルマークを作る際には、いくつかのステップを踏むことが大切です。以下の流れが一般的です。
- テーマやコンセプトを明確にする
- ラフスケッチでアイデアを出す
- デザインを絞り込み、仕上げる
- 使用シーンに応じて調整する
この流れを意識することで、より完成度の高いシンボルマークが生まれやすくなります。
ブランドイメージとシンボルマークの関係
シンボルマークは、ブランドが持つ「イメージ」や「価値観」を視覚的に表現します。
たとえば、安心感を重視する企業では、柔らかな曲線や落ち着いた色を使用することが多いです。一方、革新やスピード感をアピールしたい場合は、シャープな形や鮮やかな色が選ばれます。このように、シンボルマークのデザインとブランドの方向性が一致していることが、信頼感や統一感に繋がります。
良いシンボルマークデザインの条件

良いシンボルマークを作るには、いくつかのポイントを押さえることが必要です。ここでは、代表的な条件を解説します。
シンプルさと視認性の重要性
シンプルなデザインは、一目で内容が伝わりやすく、多くの人に覚えてもらいやすい特徴があります。
複雑な要素を詰め込みすぎると、縮小したときや遠目で見たときに認識しにくくなってしまいます。特にスマートフォンやSNSアイコンなど、小さなサイズで使う機会が増えた現代では、視認性の高さが大切です。下記のチェックポイントを参考にしましょう。
| チェック項目 | YES/NO |
|---|---|
| 一目で内容が伝わるか | |
| 小さくしても見やすいか | |
| 色数が多すぎないか |
独自性と印象に残る工夫
他のブランドと似ているデザインは、印象が薄れやすく、記憶に残りにくい傾向があります。
独自性を出すためには、自社の特徴や理念をしっかりとデザインに落とし込むことが大切です。たとえば、形や色、アイコン化するモチーフに独自の視点を加えることで、より「そのブランドらしさ」を表現できます。記憶に残る工夫として、シンプルながらも少し個性的なアクセントを入れるのも効果的です。
多様な媒体で使える汎用性
シンボルマークは、名刺やウェブサイト以外にも、商品パッケージや看板、SNSアイコンなど、さまざまな場所で使われます。
色や形が複雑すぎる場合、モノクロ印刷や小さなサイズだと再現しにくくなることがあります。そのため、どの媒体でも一貫したイメージを保てる汎用性が求められます。作成時は、用途に応じてカラーバージョンやモノクロバージョンを用意しておくと安心です。
ブランドストーリーを表現する方法
シンボルマークにブランドの物語や想いを込めることで、より多くの人に共感してもらいやすくなります。
たとえば、創業地の名産をモチーフにしたり、企業理念を象徴する形にしたりと、ブランドの逸話や背景を盛り込んだデザインが効果的です。デザイン案を説明する際に、「なぜこの形や色なのか」と理由を明確に伝えることで、説得力が増します。
シンボルマークデザインの作り方とコツ

実際にシンボルマークを作るときの手順やポイントを詳しく解説します。初めての方でも取り組みやすい方法をご紹介します。
テーマやコンセプトの決め方
最初に、どのようなブランドイメージを伝えたいかを明確にしてからデザインに取りかかるのが大切です。
自社の強みや大切にしている価値観、ターゲットとなる顧客像などを書き出してみましょう。たとえば、「安心感」「先進性」「親しみやすさ」など、伝えたいイメージのキーワードを整理することで、デザインの方向性が定まります。コンセプトが揺らがないように、関係者と認識を合わせることも忘れないようにしましょう。
競合リサーチと差別化ポイント
似た業界や業種のシンボルマークを調べて、どのようなデザインが使われているかを知ることは欠かせません。
競合のデザインを分析することで、自社がどの部分で違いを出せるかが見えてきます。たとえば、色使いやモチーフ、形状など、少しの工夫で他社との差別化が可能です。自社らしさを損なわず、かつ他と被らないデザインを目指しましょう。
アイデアスケッチから仕上げまでの流れ
アイデアを紙に描いてみることで、頭の中のイメージが整理されやすくなります。最初はラフスケッチで良いので、思いついた案をどんどん描いてみましょう。
いくつかの案を絞り込んだら、デザインソフトで清書する流れが一般的です。その後、関係者と確認しながら微調整を重ね、最終的なデータを作成します。仕上げの段階では、実際に使うシーンを想定して、複数のサイズやバリエーションを用意しておくと安心です。
フォントやカラー選びのコツ
シンボルマーク単体で使うケースもあれば、ロゴタイプと組み合わせる場合も多いです。そのため、フォント選びや色使いも重要です。
フォントは読みやすさとブランドイメージの両立がポイントです。堅実さを出すなら明朝体やゴシック体、優しさを出したいなら丸みのあるフォントなど、イメージに合ったものを選びましょう。カラーは、ブランドカラーを基準にしつつ、2〜3色までに抑えるとまとまりやすくなります。
デザインでやってはいけないNG例と注意点

デザインで失敗しがちな事例や注意点を押さえておくと、トラブルや誤解を防ぐことができます。
他社デザインの模倣リスク
他社のデザインを参考にしすぎると、意図せず似てしまうことがあります。これにより、法的なトラブルやブランドイメージの低下を招く可能性があります。
特に有名ブランドと似たデザインは避けましょう。既存のマークと似ていないか、作成後に必ず確認することが大切です。オリジナリティを守るためにも、独自のコンセプトをしっかり打ち出しましょう。
複雑すぎるデザインの落とし穴
情報を詰め込みすぎると、見た目がごちゃごちゃして印象が弱くなってしまいます。
また、縮小した際に細部がつぶれてしまい、何のマークか分からなくなることもよくあります。デザインを進める際は、一度シンプルに戻してみるのも効果的です。
一時的な流行を追いすぎない
流行のデザインを取り入れすぎると、数年後に古く感じられるおそれがあります。
長く使い続けることを考えて、時代に左右されにくい普遍的なデザインを意識しましょう。どうしてもトレンド要素を入れる場合は、バランスよく取り入れることがポイントです。
使用シーンやサイズへの配慮不足
マークが使われる場所やサイズを想定しないまま制作すると、思わぬトラブルが起こることがあります。
特に、印刷物とデジタル両方で使う場合は、色や細部の再現性に注意が必要です。事前に使う媒体や用途をリストアップしておくと安心です。
シンボルマークデザインを依頼する際のポイント
自社で作るのが難しい場合は、プロのデザイナーや制作会社に依頼するのも有効です。依頼時に気をつけたいポイントをご紹介します。
デザイナーや制作会社の選び方
デザイナーや制作会社には、それぞれ得意分野や実績があります。自社の要望に合ったパートナーを選ぶことが大切です。
ポートフォリオや過去の事例を確認し、ブランドイメージに近いデザインを手掛けているかどうかもチェックしましょう。また、コミュニケーションがスムーズに取れるかも重要なポイントです。
依頼前に整理しておきたい情報
スムーズに依頼を進めるためには、事前に情報を整理しておくことが必要です。以下の項目をまとめておくと、イメージのズレを防ぎやすくなります。
- 会社やサービスの概要
- ブランドイメージや伝えたい想い
- 使用予定の媒体やサイズ
- 参考にしたいデザイン例
これらを簡単な資料にまとめておくと、デザイナーとの打ち合わせもスムーズです。
見積もりと費用の目安
シンボルマークの制作費は、依頼先や内容によって幅があります。相場を知っておくと、見積もりを比較しやすくなります。
| 依頼先 | 費用の目安 |
|---|---|
| フリーランス | 3万円〜15万円 |
| 制作会社 | 10万円〜30万円 |
費用だけでなく、納期や修正回数、納品データの内容も事前に確認しておくことが安心につながります。
修正や納品後のサポート体制
納品後にちょっとした変更や追加データが必要になることもあります。そのため、修正対応やアフターサポートの有無も事前に確認しておくと安心です。
サポート内容や範囲は依頼先によって異なるため、契約前にしっかり相談しましょう。また、納品データの形式や著作権の取り扱いについても確認しておくと、後々トラブルを防ぐことができます。
まとめ:シンボルマークデザインでブランド価値を高めよう
シンボルマークは、企業やサービスの「顔」として、ブランド価値を高める重要な役割を持っています。基本的なデザインの流れやポイントを押さえることで、より伝わるデザインが実現できます。
良いシンボルマークづくりは、シンプルさや独自性、媒体への汎用性、そしてそのブランドだけのストーリーを大切にすることがポイントです。プロに依頼する場合も、事前準備や依頼先選びを丁寧に行い、納得のいくデザインを目指しましょう。









