SOMとは何か?市場規模分析でわかるビジネス成長のカギ

ビジネスの成長や新規事業の立ち上げを考えた時、「自分たちのサービスはどれだけの市場規模にチャンスがあるのか」と悩む方が多いのではないでしょうか。膨大な市場の中で、自社がどれだけの規模を実際に狙えるのか見極めることは、事業計画や投資判断に欠かせません。
とくにSOM(サービス可能市場)は、現実的かつ実践的な将来予測に役立つ指標として注目されています。この記事では、SOMの定義や計算方法、ビジネスでの具体的な活用例などを分かりやすく解説し、実際に役立つ知識をお届けします。
SOMとは何か市場規模分析から見えるビジネスの可能性

自社のビジネスがどれだけの市場規模に挑戦できるかを把握することは、将来の成長戦略を考えるうえで重要です。SOMの基本からその意義を丁寧に説明します。
SOMの定義と意味
SOM(Serviceable Obtainable Market)は、日本語で「自社が実際に獲得可能な市場規模」と訳されることが多い言葉です。これは、理論上の最大市場ではなく、自社のサービスや商品が現実的に提供できる範囲を指します。
たとえば、飲食店であれば「商圏内の潜在顧客数」から「営業時間や座席数、認知度などを考慮し、実際に集客できる人数」までを絞り込んだ数字がSOMとなります。SOMを知ることで、理想と現実のギャップを把握し、無理のない成長計画を立てやすくなります。
TAM SAM SOMの違いと関係性
市場規模分析には、TAM・SAM・SOMという三つの指標がよく使われます。TAM(Total Addressable Market)は理論上の最大市場、SAM(Serviceable Available Market)は自社のサービスが対応できる市場、そしてSOMが最も現実的な「獲得可能な市場規模」を示します。
下記の表にまとめます。
| 指標 | 意味 | 範囲 |
|---|---|---|
| TAM | 市場全体の最大規模 | 最も広い |
| SAM | サービス提供可能な市場 | 中程度 |
| SOM | 実際に獲得可能な市場 | 最も狭い |
このように、TAMからSAM、そしてSOMへと段階的に絞り込むことで、現実的な事業目標を設定しやすくなります。
SOMが注目される理由
SOMが注目されるのは、将来的な計画だけでなく、今何ができるかに焦点を当てているからです。理論上の最大市場規模ではなく、自社のリソースや販売体制、競合状況などを反映した現実的な数字を知ることができます。
また、投資家や関係者への説明でも、SOMの明確な根拠を示すことで、説得力のある事業計画となります。事業の進捗に応じてSOMの数値を見直すことで、状況に合わせた柔軟な戦略も立てやすくなります。
市場規模分析におけるSOMの重要性
多くの企業が市場規模分析を行う際、SOMを重視するのは、投資判断やリソース配分を適切に行うためです。全体市場(TAM)だけを参照してしまうと、過剰な期待や無謀な計画になりがちです。
SOMを正確に見積もることで、目標達成に必要な具体的なアクションや、現実的なリスクも明確にできます。とくに新規事業やスタートアップにおいては、限られたリソースで最大の成果を上げるための指針として、SOM分析が欠かせません。
SOMの計算方法と実践的な手順
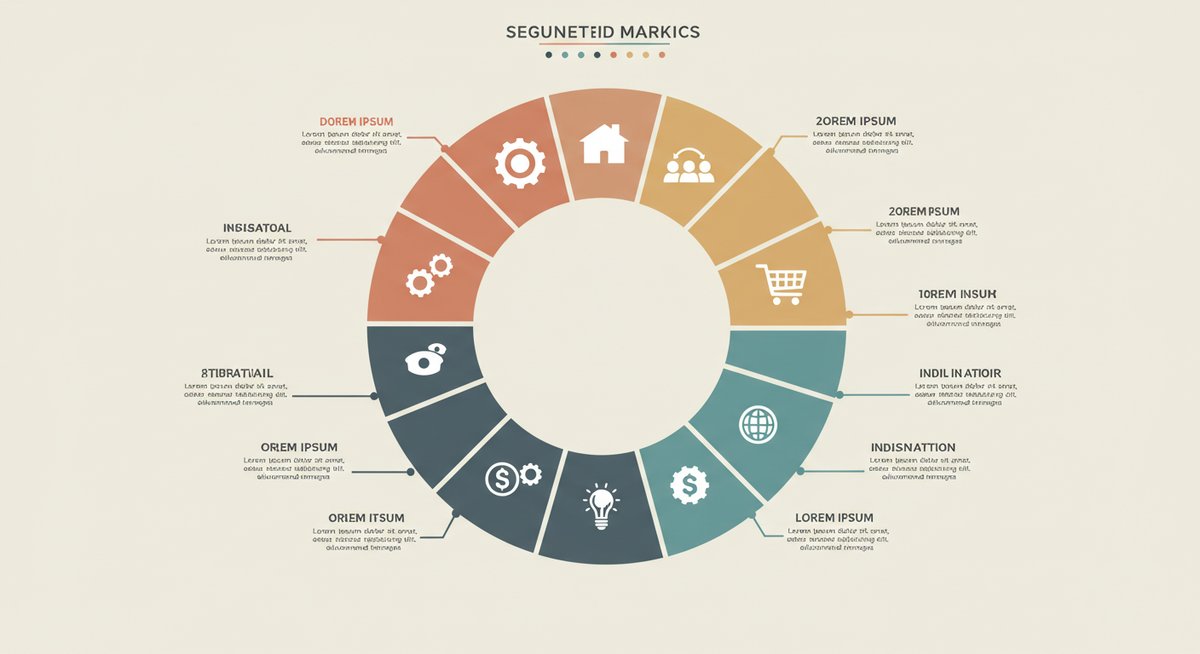
SOMを数値として算出するには、いくつかのアプローチと工夫が必要です。ここでは代表的な計算手法とそのポイントを紹介します。
トップダウンアプローチによる算出
トップダウンアプローチでは、まずTAM(市場全体)から出発し、その中から自社の対象となる範囲(SAM)、さらに実際に獲得できる範囲(SOM)へと順番に絞り込みます。公的データや業界レポートを利用し、全体の市場規模を把握することから始めるのが一般的です。
たとえば、飲食業界全体の市場規模が1兆円あるとして、自社の業態やエリア、営業時間などを考慮し、「自社が1年間で対応できるのは5億円規模」といった具体的な数字を導き出します。段階的に条件を加えていくことで、現実に即したSOMを算出できます。
ボトムアップアプローチの具体例
ボトムアップアプローチは、現場で得られる具体的なデータから積み上げてSOMを計算する方法です。自社の販売実績、顧客数、営業可能な範囲などの現状データをもとに、「これから新規獲得できそうな顧客数」や「平均取引額」などを掛け合わせていきます。
たとえば、1店舗あたり月に新規顧客を100人集められると仮定し、平均単価が3000円、年間12カ月運営すれば、「100人×3000円×12か月」で年間売上の最大値を推計します。こうした積み上げ式のアプローチは、既存ビジネスに近い場合や、地道な拡大戦略を考える際に役立ちます。
フェルミ推定を活用したSOM分析
フェルミ推定は、手元に詳細なデータがない場合でも、論理的な仮定をもとに大まかな市場規模を計算する方法です。たとえば、「ある地域の人口」や「想定される利用率」など、複数の仮定を掛け合わせて数字を導きます。
たとえば、「東京都内の20代女性の半数が月1回カフェを利用する」と仮定し、人口統計データをもとにSOMを見積もることもできます。フェルミ推定は、事業初期や前例の少ない新規サービスの市場規模を検討する際に有効です。
計算に必要なデータと参考資料
SOMを正確に計算するためには、信頼できるデータが欠かせません。主な情報源は、政府統計や業界団体のレポート、各種市場調査会社のデータなどです。自社の販売実績や、競合の事例、顧客アンケート結果なども補助資料として活用できます。
下記に代表的な情報源をまとめます。
| 情報源 | 内容 | 利用シーン |
|---|---|---|
| 政府統計 | 公的な市場規模データ | 業界全体の把握 |
| 民間調査会社 | 詳細な業界レポート | トレンド分析 |
| 自社データ | 実績や顧客動向 | ボトムアップ算出 |
信頼性の高いデータを組み合わせて利用することで、より現実的なSOMが導き出しやすくなります。
SOMを活用する具体的なビジネスシーン

SOMを理解し活用することで、事業成長のさまざまな場面で判断の根拠が明確になります。ここでは代表的な活用シーンをご紹介します。
新規事業立ち上げ時の活用法
新規事業を始める際、SOMを算出しておくことで「どれくらいの規模を目指せるのか」が明確になります。初期の事業計画でSOMを重視すると、目標設定やリソース配分が現実的になります。
また、サービス提供エリアや想定するターゲット層が変わればSOMも変化します。事業の仮説検証や、進捗確認の指標としても活用でき、リスクの予測や対策も立てやすくなります。
投資家への事業説明におけるSOMの使い方
投資家に事業を説明する場面では、SOMの根拠や算出方法をしっかり示すことが信頼につながります。TAMやSAMだけでは「規模感」が大きすぎて現実味に欠けるため、SOMを明確に示すことで事業の具体性を伝えやすくなります。
たとえば、数年後の売上計画を示す時、「なぜその数字なのか」をSOMの算出ロジックとともに説明し、説得力を高めることができます。投資家はリスクやリターンを冷静に見ているため、SOMの具体性が重要視されます。
事業計画や市場戦略での応用事例
SOMは、事業計画の目標設定や市場戦略にも応用できます。たとえば、エリア拡大や新たなプロモーション戦略を検討する際に、「これらの活動がSOMのどの部分に影響するか」を分析します。
また、複数のサービスや商品ごとにSOMを算出することで、成長余地の大きい分野を特定しやすくなります。こうしたデータは、社内の意思決定や新たな投資判断にも役立ちます。
M&Aや企業価値評価における活用ポイント
M&A(企業買収・合併)や企業価値の評価を行う時も、SOMは重要な指標です。なぜなら、買収先や提携先が「実際にどれだけの売上を伸ばせるか」を予測するために、SOMを参考にするからです。
売上や利益の将来予測だけでなく、「その市場規模がどれほど現実的か」を裏付ける材料として、SOMが重視される傾向にあります。想定よりもSOMが小さい場合は、過剰な期待を避ける判断材料にもなります。
SOM分析を成功させるためのポイントと注意点

的確なSOM分析を行うには、いくつかのコツと注意点があります。実務でのポイントを押さえておきましょう。
正確な市場定義のポイント
SOMを計算する際は、市場の定義をまず明確にすることが大切です。「どの地域・どの顧客層を対象にするのか」「どういったニーズに応えるのか」まで具体化しないと、精度の高い分析は難しくなります。
たとえば、単に「美容業界」とするよりも、「都市部に住む20~40代女性向けネイルサロン」と絞り込むことで、現実的なSOMが見えてきます。定義の曖昧さは、分析結果のぶれや誤解につながるので注意が必要です。
事業フェーズや業界特性に合わせた指標選び
SOMの算出方法や使う指標は、事業フェーズや業界によって異なります。たとえば、スタートアップ初期では潜在顧客数の見積もりが重視されますが、成長段階では既存顧客データや実績が重視されます。
また、製造業とITサービス業では、ターゲット市場の広さや競争環境が異なるため、SOMの算出ロジックも合うように調整が必要です。業界特性をよく理解したうえで指標を選びましょう。
他の指標(TAM SAM)とのバランス
SOMだけに注目するのではなく、TAMやSAMとのバランスも意識しましょう。たとえば、TAMやSAMが極端に大きいのにSOMが小さい場合、成長の余地や戦略の再考が求められることがあります。
逆に、SOMがSAMやTAMに比べて大きすぎる場合、分析が楽観的すぎる可能性もあります。三つの指標を比較することで、自社の事業計画が現実的かどうか客観的にチェックできます。
SOM分析でよくある誤解と失敗例
SOM分析でよくある失敗は、「根拠があいまいな数字を使ってしまう」ことです。希望的観測だけで見積もると、事業計画が現実離れしたものになりやすいです。
また、「市場の定義が広すぎて、実際には到達できない範囲まで含めてしまう」のも注意点です。SOMは、現実に獲得できる部分だけに絞るべき指標です。客観的なデータや根拠をもとに算出する姿勢が大切です。
SOMを活用した企業の成功事例
ここでは、SOMの考え方を活用して成長や市場拡大を実現した企業の具体例を紹介します。
海外スタートアップによる成長ストーリー
米国の配車アプリ大手は、市場分析を行う際、まず全世界の移動市場(TAM)を見積もりました。しかし、実際に自社が最初に狙えるのは都市部の若年層(SOM)だけと考え、対象エリアやプロモーションを限定しました。
その後、実績やノウハウを蓄積しながらサービスエリアを徐々に拡大。段階的にSOMを広げることで、リスクを抑えつつ成長を実現した好例です。
国内企業の市場拡大事例
日本の健康食品メーカーも、SOMを重視した成長戦略を展開しました。最初は「健康志向の30~50代女性」を主なターゲットとし、その中で通信販売を中心に市場を絞り込みました。
実際の購買データや反響をもとにSOMを再計算し、販売チャネルやターゲット層を徐々に拡大。結果、少しずつ売上を伸ばし、既存市場から新たな市場へと事業の幅を広げています。
SaaS企業におけるSOM設定の実例
SaaS(クラウド型サービス)企業の場合、SOMの設定は提供可能な機能やサポート体制、ターゲット企業規模ごとに細かく分けて行われます。たとえば、「中小企業向けの顧客管理ソフト」として、従業員数や業種によってSOMを分類します。
初期はサポート体制が限定的だったため、全国の一部業界だけに絞ってサービスを展開。段階的なアップグレードやサポート範囲の拡大とともに、SOMも拡大してきました。
投資判断の現場で活きるSOMの使い方
ベンチャーキャピタルや事業会社が投資判断を行う際、SOMの現実性は重視されます。たとえば、あるスタートアップ企業への投資検討では、経営者が示したSOMの根拠をもとに、現状の営業力や競争状況まで細かく検証しました。
将来の成長可能性だけでなく、「初期段階で実際にどれだけ売上が見込めるか」をSOMから判断し、追加投資や成長支援の方針を決めた事例もあります。
まとめ:SOMを理解し市場機会を最大化するために必要な視点
SOMは、単なる市場の数字ではなく、事業の現実性や成長可能性を見極めるための大切な指標です。TAMやSAMとの違いを正しく理解し、自社に合った現実的な市場規模を見積もることが、堅実な成長戦略につながります。
今後、事業計画や新サービスの立ち上げ、投資判断などさまざまな場面でSOM分析を取り入れることで、自社の強みを活かしながら、より確かな一歩を踏み出せるでしょう。データに基づく判断と、柔軟な見直しを心掛けていきましょう。









