ブログのカテゴリーの作り方を徹底解説!初心者でも迷わず記事を整理できる方法

ブログカテゴリーの役割と基本の考え方

ブログのカテゴリーは、記事を分かりやすく整理し、読者が情報を探しやすくするために欠かせないものです。SEOの観点からも重要です。
ブログカテゴリーで記事を整理するメリット
ブログカテゴリーを使うことで、記事が体系的に整理され、訪問者が求める情報に素早くたどり着けます。たとえば、料理ブログなら「レシピ」「食材」「調理道具」といったカテゴリーがあれば、読者は目的の記事を探しやすくなります。カテゴリーごとに記事をまとめることで、サイト内の巡回もスムーズになり、滞在時間の向上にもつながります。
また、カテゴリーごとにまとまりが生まれることで、ブログ全体の専門性を伝えやすくなります。これにより検索エンジンにもテーマが明確に伝わり、SEOの強化にも役立ちます。さらに、カテゴリー別の最新記事リストや人気記事リストなども設置しやすくなるため、関連する情報を自然におすすめすることも可能です。
カテゴリーとタグの違いを理解する
カテゴリーは記事の大まかな分類に使われる一方、タグは記事の内容をさらに細かく補足するためのものです。たとえば「レシピ」というカテゴリーに入れた記事に、「パスタ」「時短」などのタグを付けることで、同じタグの記事同士を横断的にまとめることができます。
カテゴリーは原則として一記事一つに絞る場合が多く、サイト構造を整理する役割があります。一方、タグは複数付与でき、記事の特徴や関連性を補う役割を持っています。カテゴリーとタグの違いを意識して使い分けることで、より見やすいブログを作ることができます。
カテゴリーの階層構造とその活用法
カテゴリーは階層ごとに細かく分けることができます。たとえば「レシピ」カテゴリーの下に「和食」「洋食」などをサブカテゴリーとして設けることで、より詳細な分類が可能になります。これにより、読者は自分の興味に合った記事をすぐに見つけやすくなります。
しかし、階層が複雑になりすぎると管理が大変になったり、読者が迷ってしまうこともあります。階層は2~3段階程度にとどめ、シンプルな構造を意識しましょう。以下のような形が参考になります。
| メインカテゴリー | サブカテゴリー | 例 |
|---|---|---|
| レシピ | 和食 | だし巻き卵 |
| レシピ | 洋食 | オムライス |
効果的なカテゴリーの作り方とポイント

効果的なカテゴリー設計は、ブログの魅力を高め、検索エンジンにも評価されやすくなります。具体的な方法を確認しましょう。
コンセプトやターゲットを明確にする
ブログのコンセプトやターゲット読者を明確にすることは、カテゴリー設計の出発点です。誰に向けたどんな情報を発信したいのかが決まれば、必要となるカテゴリーも自然と絞られてきます。たとえば、子育てブログなら「子育ての悩み」「おすすめグッズ」「育児体験談」など、読者に役立つテーマで分けると良いでしょう。
ターゲットの年齢層や関心ごとを想像しながら、「このカテゴリーで読者が知りたいことが網羅できているか」を意識することが大切です。読者目線を忘れずにカテゴリーを決めることで、有益な情報を届けやすくなります。
読者が直感的に理解できるカテゴリー名を選ぶ
カテゴリー名は、誰が見ても内容がイメージできるようにする必要があります。難しい言葉や抽象的な表現は避け、できる限りシンプルで具体的な言葉を選びましょう。たとえば「レシピ」「体験談」「お役立ち情報」など、直感的に分かりやすい名前がおすすめです。
カテゴリー名が分かりにくいと、訪問者が迷ってしまい、サイト内の回遊にも悪影響が出ます。下記のように、分かりやすさを基準に選ぶと良いでしょう。
| 良い例 | 分かりにくい例 |
|---|---|
| レシピ | いろいろ |
| 体験談 | 日常 |
検索キーワードを意識したカテゴリー設計
カテゴリー名を決める際には、検索されやすいキーワードを意識することもポイントです。たとえば「ダイエット方法」「簡単レシピ」など、読者がよく検索する言葉を使うことで、SEO効果も期待できます。
ただし、キーワードを詰め込みすぎると不自然な名前になってしまうことがあります。自然な形でキーワードを取り入れつつ、読みやすさとのバランスを大切にしましょう。事前に検索ボリュームを調べて、適切なワードを選ぶことも有効です。
カテゴリー分けで気をつけること
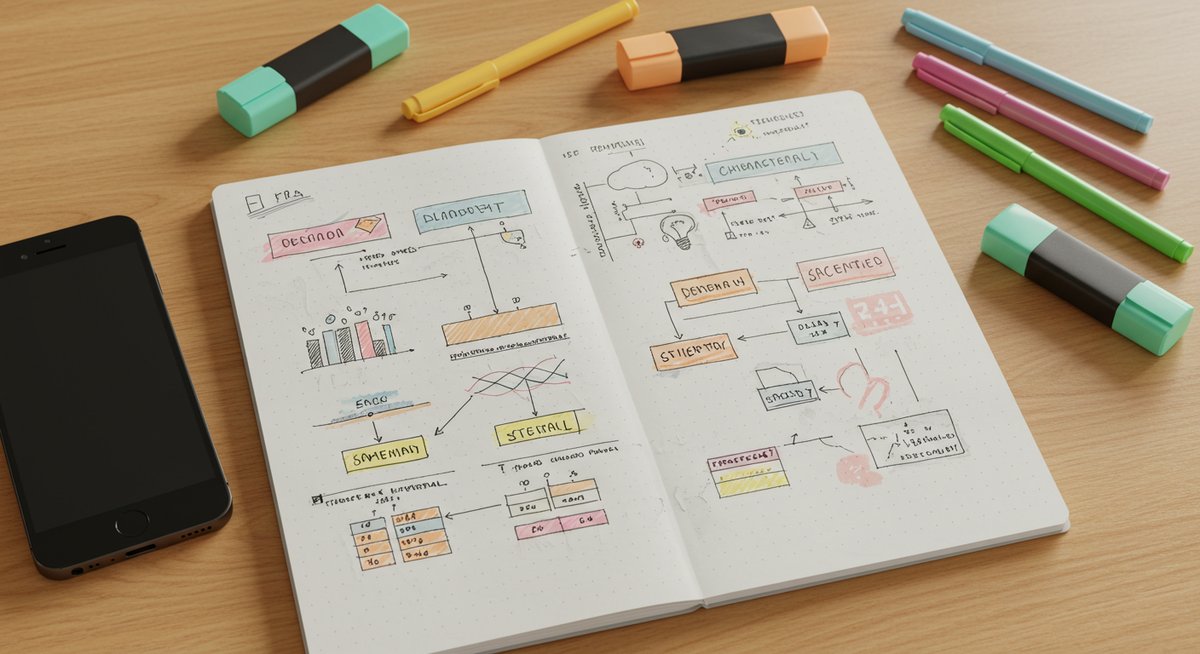
カテゴリー分けには注意点もあります。適切に設計することで、ブログ全体の使いやすさが向上します。
「その他」や未分類カテゴリーを作らない理由
「その他」や「未分類」といったカテゴリーは、できるだけ避けたいものです。このようなカテゴリーを設けてしまうと、記事の内容が伝わりにくくなり、読者が求める情報を見つけにくくなります。また、検索エンジンにもブログの構成が曖昧だと認識されやすくなるため、SEO面でも不利です。
どうしても分けられない記事が出てくる場合は、既存のカテゴリーを見直したり、新たに適切なカテゴリーを追加することを検討しましょう。記事が増えたら定期的に整理することも大切です。
カテゴリーの数や階層を増やしすぎないコツ
カテゴリーの数が多すぎたり、階層が深くなりすぎたりすると、管理が難しくなり、訪問者も迷いやすくなります。目安としては、メインカテゴリーは5~10個程度にまとめ、サブカテゴリーも必要最小限にとどめましょう。
カテゴリーを増やしたくなった場合は、「本当にその区分が必要か」「既存のカテゴリーで代用できないか」を再確認してみてください。シンプルな構造を意識することで、見やすく使いやすいブログになります。
1記事1カテゴリーの原則とその理由
1つの記事には原則として1つのカテゴリーだけを設定するのが基本です。複数のカテゴリーを設定すると、どの分類がメインなのかが分かりにくくなります。また、同じ記事が複数のカテゴリーに表示されることで、読者が混乱したり、SEOの評価が分散することもあります。
どうしても複数のテーマが関係する場合は、より細かいサブカテゴリーを用意したり、タグを活用しましょう。明確な基準を持ってカテゴリー分けすることが、ブログの品質向上につながります。
WordPressでのカテゴリー設定と活用方法

WordPressでは、カテゴリーの追加や編集が手軽に行えます。正しく使いこなすことで、より魅力的なブログ運営が可能です。
新しいカテゴリーの追加と編集方法
WordPressで新しいカテゴリーを追加するには、管理画面の「投稿」メニューから「カテゴリー」を選んで操作します。カテゴリー名や説明を入力し、「新規カテゴリーを追加」ボタンを押すだけで反映されます。また、サブカテゴリーを作りたい場合は、親カテゴリーを選択して登録します。
すでにあるカテゴリーの編集や削除も簡単です。カテゴリー一覧から編集したい項目を選び、名前や説明、スラッグ(URLの一部になる文字列)の変更ができます。定期的に見直して、使いやすい構成を保つことが大切です。
記事にカテゴリーを設定する手順
記事にカテゴリーを設定する場合、投稿画面の右側にあるカテゴリー欄から選択します。該当するカテゴリーにチェックを入れるだけで、記事が自動的に分類されます。新しいカテゴリーを追加したい場合も、同じ欄から作成できます。
カテゴリーの選定は、記事の内容をよく見直して最適なものを選ぶことが大切です。カテゴリー選びに迷った場合は、既存の記事とのバランスや、読者のニーズを意識して決めると良いでしょう。
カテゴリーの順番や表示場所のカスタマイズ方法
カテゴリーの順番や表示場所は、WordPressのウィジェット機能やプラグインを活用して調整できます。たとえば、サイドバーや記事下にカテゴリーリストを表示することで、読者が他の記事も見つけやすくなります。
カテゴリーの順番を変えたい場合は、ドラッグ&ドロップ操作ができるプラグインを導入する方法もあります。見せ方を工夫することで、ブログの回遊性や利便性が高まります。
まとめ:読者とSEO双方にメリットがあるカテゴリー作りのコツ
カテゴリー設計は、読者が情報を探しやすくなるだけでなく、検索エンジンからの評価にもつながります。シンプルで分かりやすい構造を意識し、定期的な見直しを行いましょう。
カテゴリー名は直感的で、検索キーワードも意識しながら決定することが重要です。1記事1カテゴリーの原則や、階層の深さにも注意しつつ、常に読者目線で最適な分類を心がけてください。読者にもSEOにも役立つブログ運営が実現できます。









