ですます調の一覧で迷わない!場面別に使い分ける文末表現とコツ
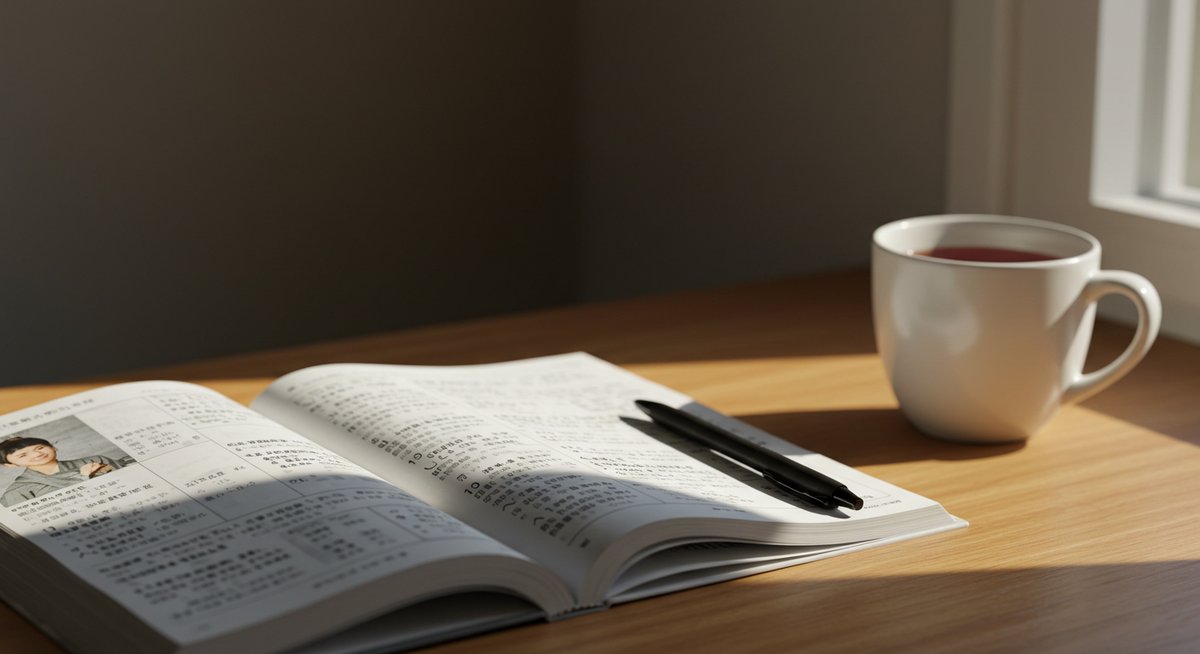
ですます調とだである調の違いと特徴を理解しよう
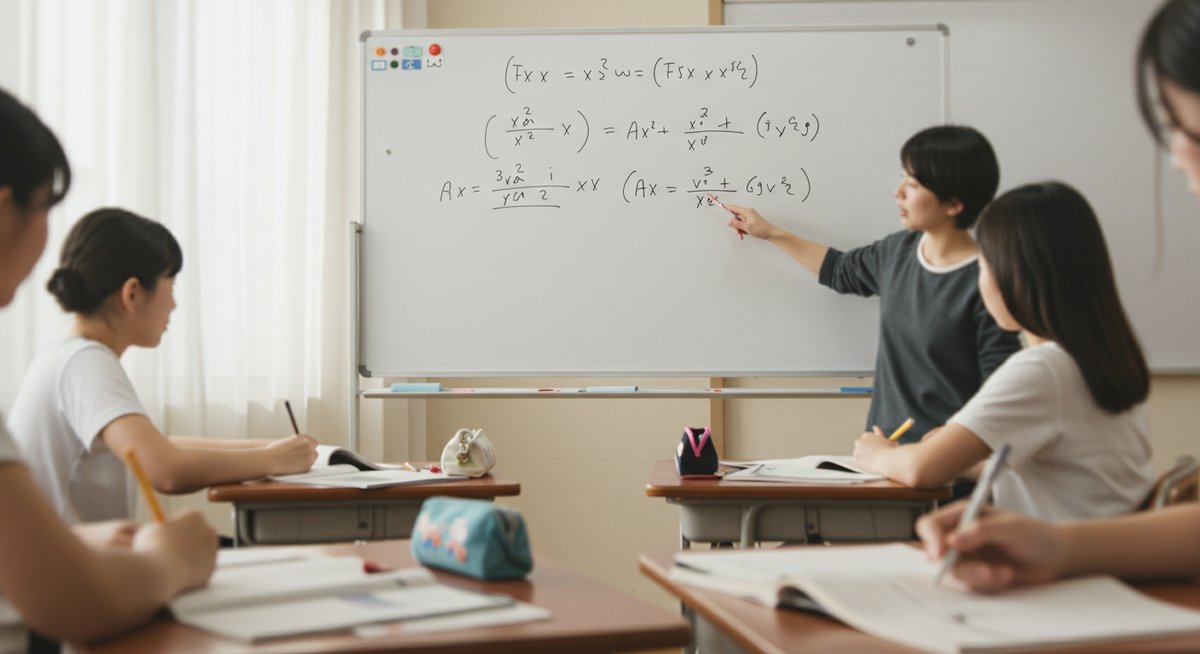
文章を書くうえで、「ですます調」と「だである調」のどちらを選ぶかは大切なポイントです。どちらにも特徴があるため、用途や読者に合わせて使い分けることが求められます。
ですます調の特徴と使われる場面
ですます調は、語尾が「です」「ます」となるため、全体的に柔らかく丁寧な印象を与えやすい文体です。話し言葉に近く、親しみやすさを感じてもらえるため、幅広い場面で使われています。
たとえば、ビジネスメールや取引先への連絡、学校のレポート、インターネットの記事など、多くの読者を意識した場面でよく利用されます。特に初対面の相手やフォーマルなやりとりでは、丁寧な印象を持ってもらいやすいです。加えて、説明文や案内文など、相手に配慮を示したい場面にも適しています。
箇条書きで主な特徴をまとめると、以下の通りです。
- 丁寧さや親しみやすさを伝えやすい
- 幅広い年齢層や立場に向けて使える
- ネットやビジネスなど多様な場面で利用される
だである調の特徴と使われる場面
だである調は、「だ」「である」で文章が終わる形を指します。論理的で簡潔な印象を与えやすく、客観的に情報を伝えたいときに使われることが多いです。
学術論文や報告書、マニュアルなど、事実やデータを明確に伝える必要がある場面に適しています。また、専門性の高い内容や公式な文書でもよく用いられます。ただし、読者によっては冷たく感じることもあるため、内容や読み手を意識した使い分けが重要です。
主な特徴を以下にまとめます。
- 簡潔で論理的な印象を与える
- 事実や客観性を重視する文書に向いている
- 専門性や信頼性を高めたい場面で利用される
どちらの文体を選ぶべきか判断するポイント
文体を選ぶときは、誰に向けて何を伝えるかを考えることが大切です。たとえば、読者が一般の方や幅広い世代の場合は、やわらかく丁寧なですます調が適しています。
一方、専門家や研究者向けで、情報の正確さや論理性が重視される場合はだである調が選ばれます。また、ウェブサイトなどでは、読者との距離感やコンテンツの内容によってどちらがふさわしいか判断します。
選択のポイントを表にまとめると、以下の通りです。
| 文体 | ふさわしい場面 | 印象 |
|---|---|---|
| ですます調 | メール、案内、一般的な文章 | 丁寧・親しみやすい |
| だである調 | 報告書、論文、マニュアル | 簡潔・論理的 |
ですます調の文末表現一覧とバリエーション
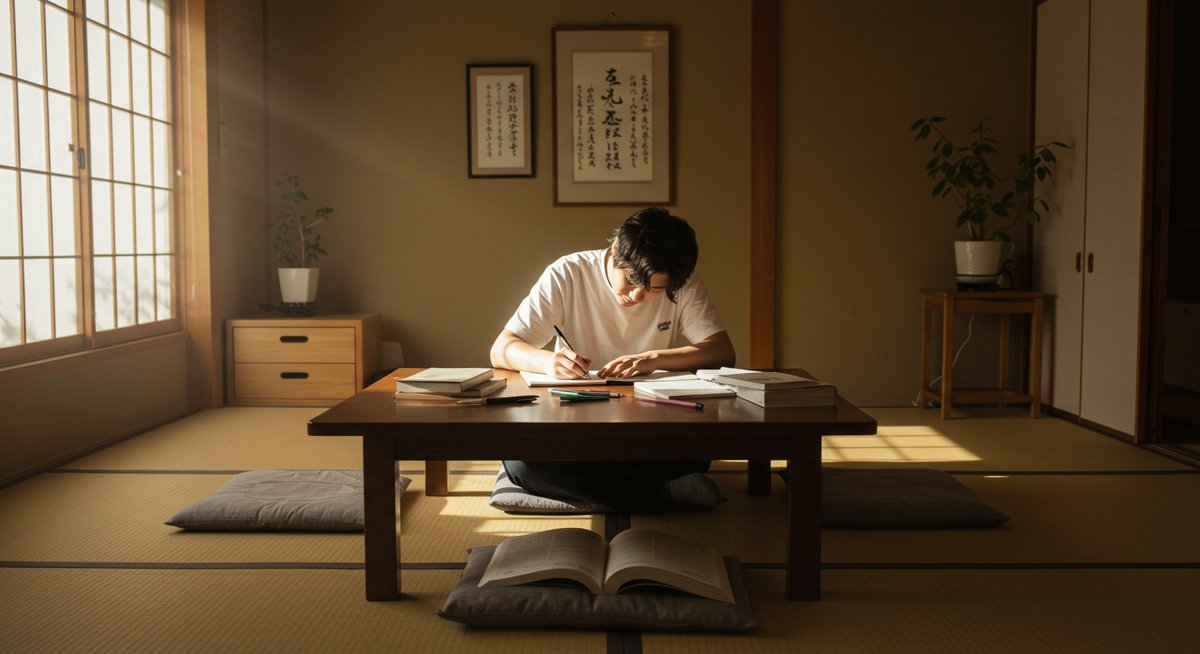
文章の印象は文末表現によって大きく変わります。ですます調にもさまざまな語尾があり、使い分けることで表現の幅が広がります。
断定や丁寧さを伝える基本の語尾
ですます調の基本となる語尾には、「です」と「ます」があります。これらは断定や事実を丁寧に伝える場面でよく使われ、相手に安心感を与える効果があります。
たとえば「本日は晴れです」「ご参加いただきます」など、事実や意思をそのまま伝えるときに便利です。また、「ございます」「しております」などの表現にすることで、より丁寧な印象をプラスできます。
以下に、代表的な語尾を一覧でまとめます。
| 語尾 | 用途 |
|---|---|
| です | 断定・説明 |
| ます | 動作・意思の表現 |
| ございます | さらに丁寧な表現 |
| しております | 継続的な行動や丁寧な表現 |
疑問や提案を表現する語尾の使い方
疑問を表現したい場合は、「でしょうか」「ますか」といった語尾がよく用いられます。これにより、相手に質問や確認を投げかけることができます。
たとえば「ご都合はいかがでしょうか」「ご確認いただけますか」といった表現です。また、提案や誘いを伝えるときは、「してみませんか」「いかがでしょう」などを使うと柔らかい印象を与えられます。
主な疑問や提案の語尾は以下の通りです。
| 語尾 | 使い方・例 |
|---|---|
| でしょうか | 丁寧な疑問、意見を求める |
| ますか | 直接的な質問 |
| してみませんか | 提案・勧誘 |
| いかがでしょう | 柔らかい確認・提案 |
否定や推測など他の語尾パターン
否定や推測、依頼などを表現するための語尾も豊富にあります。「できません」「ありません」などで否定を示し、「だと思います」「でしょう」などで推測や控えめな意思を伝えます。
また、「お願いいたします」「ご協力ください」などの依頼表現もよく使われます。こうした語尾を使い分けることで、文章のニュアンスを細かく調整できます。
主なパターンを以下にまとめます。
| 語尾 | 用途 |
|---|---|
| できません | 否定 |
| だと思います | 推測・控えめな意見 |
| お願いいたします | 丁寧な依頼 |
| ください | 一般的な依頼 |
文末表現を選ぶときの注意点と工夫

文末表現の選び方ひとつで、文章全体の印象が大きく変わります。統一感やバリエーションに注意を払うことで、より読みやすく伝わる文章に仕上がります。
文体の統一で文章の印象を整えるコツ
文章の途中で文体が混在してしまうと、読者に違和感が生じやすくなります。たとえば、同じ文章内で「ですます調」と「だである調」が入り混じると、まとまりがなくなります。
文章を書く際は、最初にどちらの文体で統一するか決めることが大切です。途中で切り替えが必要な場合は、見出しや章ごとに変えるなど工夫をしましょう。これにより、読者が内容に集中しやすくなります。
同じ文末表現の繰り返しを避ける方法
「です」「ます」だけが続くと、単調で退屈な印象になりがちです。同じ語尾が連続しないよう、文末表現を工夫して変化をつけましょう。
たとえば、「〜しております」「〜いたします」「〜となります」など、同じ内容でも語尾を変える方法があります。また、体言止めや接続詞を使って文章のリズムに変化をつけるのも効果的です。
以下のように組み合わせて活用できます。
- 〜です → 〜となります
- 〜ます → 〜いたします
- 〜しております → 〜しています
体言止めやあいまい表現の使い方
体言止めとは、名詞で文章を終える表現です。これを使うと、印象的に伝えたい部分や、文章に余韻を持たせたいときに効果的です。
また、「と思われます」「ようです」などのあいまいな語尾は、断定を避けて柔らかい印象を与えます。ただし、使いすぎると内容がぼやけてしまうため、必要に応じて使い分けることが大切です。
体言止めとあいまい表現の例を挙げます。
| 表現例 | 用途 |
|---|---|
| ご案内 | 体言止めで印象を強調 |
| と思われます | あいまいに伝える場合 |
| のようです | 推測や控えめな表現 |
シーン別にみる文末表現の使い分けと実践例
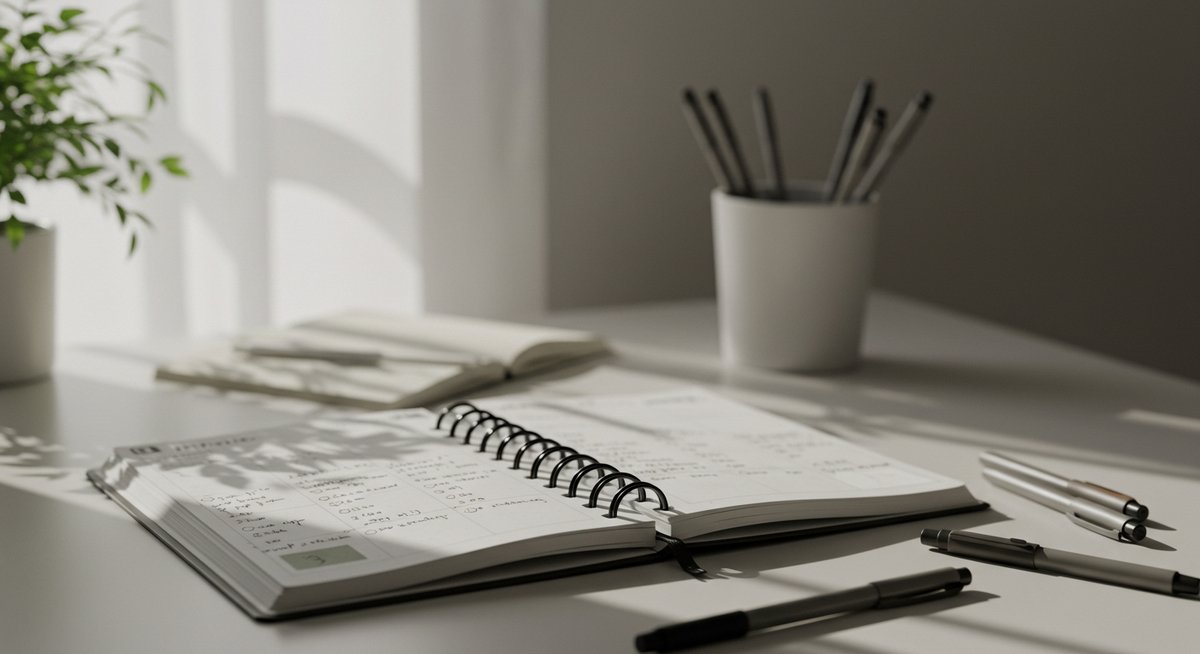
文末表現はシーンによって適切な使い方が異なります。状況に合わせて語尾を選ぶことで、より伝わりやすい文章を目指せます。
ビジネス文書やメールでの適切な語尾
ビジネス文書やメールでは、相手への敬意や配慮を意識した語尾が求められます。「ございます」「いただきます」「お願いいたします」など、より丁寧な表現が効果的です。
たとえば、「ご確認をお願いいたします」「ご連絡いただけますと幸いです」など、相手を立てる表現がよく使われます。疑問形の場合も「いかがでしょうか」「ご都合は如何でしょうか」といった柔らかい語尾が好まれます。
具体的な使い分けを表にまとめます。
| シーン | 適した語尾 | 例文 |
|---|---|---|
| 依頼 | お願いいたします | ご協力をお願いいたします |
| 確認 | いただけますか | ご確認いただけますか |
| 提案・案内 | いかがでしょうか | ご利用いかがでしょうか |
レポートや報告書で意識すべき文末表現
レポートや報告書では、客観性とわかりやすさが重視されます。ですます調を使う場合でも、「〜であると考えられます」「〜と推測されます」など、控えめな断定や推測の語尾が適しています。
数値や事実を述べる際は、「〜です」「〜ます」で簡潔にまとめ、考察部分では「〜と思われます」「〜と考えます」を使うことで、文章に奥行きを持たせられます。また、報告や結論の部分では、「〜となります」「〜といえます」といった語尾もよく用いられます。
適切な語尾の例をまとめます。
- 〜と考えられます
- 〜となります
- 〜と思われます
- 〜であるといえます
Webライティングで読者に伝わる文体の選び方
Webライティングでは、読者との距離感や読みやすさを重視することが大切です。ですます調が基本ですが、硬くなりすぎないようバリエーションを持たせると効果的です。
また、ターゲットやコンテンツの目的によって、柔らかさや親しみやすさ、信頼感を文末表現で調整しましょう。たとえば、初心者向け記事では「〜してみましょう」「〜できます」など、前向きで優しい語尾が好まれます。一方、専門的な解説記事では「〜といえます」「〜が重要です」など、やや断定的な表現で信頼感を持たせることができます。
シーン別におすすめの文末表現をまとめると次の通りです。
| 目的 | おすすめ語尾 | イメージ |
|---|---|---|
| 初心者向け | 〜してみましょう | 優しい・安心感 |
| 専門的解説 | 〜といえます | 信頼感・説得力 |
| お知らせ・案内 | 〜となります | わかりやすさ |
まとめ:文末表現を意識して伝わる文章を目指そう
文章の文末表現は、読む人に与える印象や伝わりやすさを左右します。文体や語尾を意識して使い分けることで、より伝わる文章を書くことができます。
用途や場面ごとに適切な文末表現を選ぶことが大切です。基本の型を押さえつつ、慣れてきたらバリエーションも取り入れてみましょう。読み手に誠実に伝わる文章を目指して、文末表現にも工夫を重ねてみてください。









