離脱率と直帰率の違いを即理解して改善につなげる方法

ウェブサイトの改善でよく話題になる「直帰率」と「離脱率」は、似ているようで役割が違います。どちらもユーザー行動を示す重要な指標ですが、誤解したまま対策を始めると効果が出にくくなります。ここでは短時間で本質をつかみ、実務で使える判断基準や優先順位、GA4特有のポイントまでわかりやすく整理します。まずは直感的な理解から入り、続けて定義・計算、実例、改善テクニック、そして優先順位付けの方法まで順を追って説明します。日々の改善業務にすぐ使えるチェックリストも最後に用意しています。
離脱率と直帰率の違いを短時間で理解し改善に結びつける方法

直感的に分かる両指標の本質
直帰率は「訪問者が最初のページだけ見てセッションを終了した割合」を示します。つまり、そのページが最初にユーザーの期待に応えられなかった可能性を示す指標です。一方、離脱率は「特定ページがセッション内で最後に見られた割合」を示します。あるページが離脱ポイントになっているかどうかを示すもので、必ずしも悪いとは限りません。例えば購入完了ページやサンクスページは高い離脱率が自然です。
ページの役割(ランディング/中間/ゴール)に応じて直帰率・離脱率の解釈を変えることが大切です。ランディングページは直帰率を下げる工夫、中間ページでは回遊を促す導線改善、ゴールページは離脱率が高くても問題にならないケースがあるため目的に合わせた改善を行います。まずは各ページの役割を把握してから指標を見てください。
どちらを優先すべきかの判断基準
優先順位はサイトの目的とページの役割で決めます。新規流入を増やす施策をするならランディングページの直帰率改善が優先です。コンテンツサイトで回遊を上げたい場合は中間ページの離脱率を下げることを重視します。ECならカート・チェックアウトページの離脱率が直接売上に直結するため、ここを最優先にします。
また、CVR(コンバージョン率)や収益インパクトと合わせて判断してください。直帰率が高くてもCVRに影響がなければ後回しでよい場合があります。簡易的なフレームワークとして、「影響度(収益/目標への直結度)×改善しやすさ(実行コスト)」で優先度を算出すると実務で使いやすくなります。
改善で期待できる効果の概略
直帰率と離脱率の改善は主に以下の効果が期待できます。
- 流入からの継続閲覧が増え、ページビューや滞在時間の向上。
- 回遊率向上により広告のLTV改善やSEO評価の向上。
- ECではカート離脱減少により直接的な売上増加。
- サイト内導線改善によりコンバージョン率や登録数の増加。
ただし改善施策は測定と検証が不可欠です。数値は短期的に変動するため、ABテストや段階的な実装で因果を確認しながら進めてください。まず小さな改善を検証し、効果が出れば他ページへ横展開するのが効率的です。
GA4で見ると変わるポイント
GA4では「セッション」と「エンゲージメント」の考え方が強化され、直帰率の計算方法も旧来とは異なります。GA4では直帰率が従来より低く報告される傾向があり、エンゲージメント指標(エンゲージメント率、エンゲージメント時間)を併用して評価する必要があります。イベントベースの計測により、スクロールやクリックを自動でエンゲージメントとしてカウントできるため、単純に直帰率だけで判断しないことが重要です。
設定によってはカスタムイベントやコンバージョン設定が測定結果に大きく影響します。GA4移行時は重要イベントを正しく設定し、旧指標との乖離を把握してから閾値を見直してください。
まず着手すべきページの選び方
初動では「トラフィックが多く、かつCVに影響するページ」を優先します。具体的にはランディングページTOP、主要カテゴリーページ、カート・チェックアウトページです。次に直帰率や離脱率が高く、かつ改善余地が大きいページを抽出します。
抽出手順の例:
- GAで流入数とCV貢献度を確認
- 直帰率・離脱率の高いページを上位10件抽出
- ページ役割(ランディング/中間/ゴール)で分類
- 収益影響度と改善コストで優先順位付け
これにより、短期的に効果を出しやすいページから着手できます。
直帰率と離脱率の定義と計算の基礎

直帰率の定義
直帰率は、訪問者がそのセッションで最初にアクセスしたページのみを閲覧してサイトを離れた割合を示す指標です。ランディングページがユーザーの期待に合っているか、導線やコンテンツが分かりやすいかを測るのに使います。高い直帰率は必ずしも悪いわけではなく、検索結果で答えが完結する場合や問い合わせページなど目的が達成されたケースもあります。したがって直帰率を見る際はページの目的や流入元を併せて確認することが重要です。
ページの役割ごとに適切な目標値を設定し、他の指標(滞在時間、イベント発火、コンバージョン)と合わせて評価することで、より正確な改善方針が立てられます。
直帰率の計算式と注意点
直帰率は通常、直帰セッション数 ÷ ランディングセッション数 × 100で計算されます。直帰セッションとは、そのセッション内でページ遷移が発生せず、セッションが終了したものを指します。
注意点:
- GA4では従来の直帰率定義が変わるため、比較時は指標の違いを意識する必要があります。
- 自動イベント(スクロールやエンゲージメント)を計測すると直帰扱いにならない場合があるため、設定によって数値が変動します。
- ページの目的を無視して単純に数値だけで判断すると誤った施策になる可能性があります。
離脱率の定義
離脱率は、特定ページがセッション内で最後に見られた割合を示す指標です。あるページが「離脱ポイント」になっているかどうかを判断できます。離脱率が高いページは、そのページでユーザーの行動が止まっている可能性があるため、導線やコンテンツ、CTAの位置などを見直すサインとなります。ただしサンクスページや完了ページは高離脱が自然であるため、ページの役割を踏まえて解釈する必要があります。
離脱率はページ単位のボトルネック検出に向いており、改善対象ページを絞る際に有用です。
離脱率の計算式と注意点
離脱率は、そのページの離脱数 ÷ 総ページビュー数 × 100で計算されます。離脱数はそのページがセッション内で最後に表示された回数です。
注意点:
- ページビュー数に対する割合のため、人気ページでは離脱率が目立ちやすい点に注意してください。
- 多段階のフロー(例:記事→関連記事→外部リンク)では自然な離脱も多くなるため、単純な追及は誤りになります。
- イベント計測や遷移ログと組み合わせると原因分析がしやすくなります。
セッションとページビューの違い
セッションはユーザーがサイトにアクセスしてから離脱するまでの一連の行動のまとまりを示します。一方、ページビューは個別ページが表示された回数を示します。同一セッション内で複数のページビューが発生するため、直帰率はセッションベース、離脱率はページビューベースで評価されます。
この違いを理解しないと、例えば「離脱率が高い=直帰が多い」と誤解してしまいます。目的に応じてどちらの単位で評価するかを選んでください。
GA4と旧アナリティクスの違い
GA4はイベントベースでエンゲージメントを重視するため、旧来の直帰率の扱いが変わります。GA4ではエンゲージメント率(または直帰率の反対指標)やエンゲージメント時間を併用することが推奨されます。自動計測イベント(スクロール、動画再生、クリックなど)をオンにすると、直帰とみなされるセッションが減り、旧アナリティクスとの比較が難しくなります。
移行時は主要イベントやコンバージョンの定義を揃え、過去データとの比較期間は慎重に設定してください。
目安は何パーセントか業界別の参考値
目安は業界やページ役割によって大きく異なりますが、参考値の一例を示します(あくまで目安):
- メディア/コンテンツ:直帰率30〜60%程度が一般的
- ECサイト(商品詳細など):直帰率20〜40%程度
- ランディング広告流入ページ:直帰率40〜70%程度
- B2Bサイト(資料請求導線など):直帰率30〜50%程度
重要なのは同業他社や過去の自サイトデータと比較して改善トレンドを見ることです。絶対値にこだわりすぎず、目的に合わせた適切な目標設定をしてください。
違いを正しく読み解く実務的な具体例
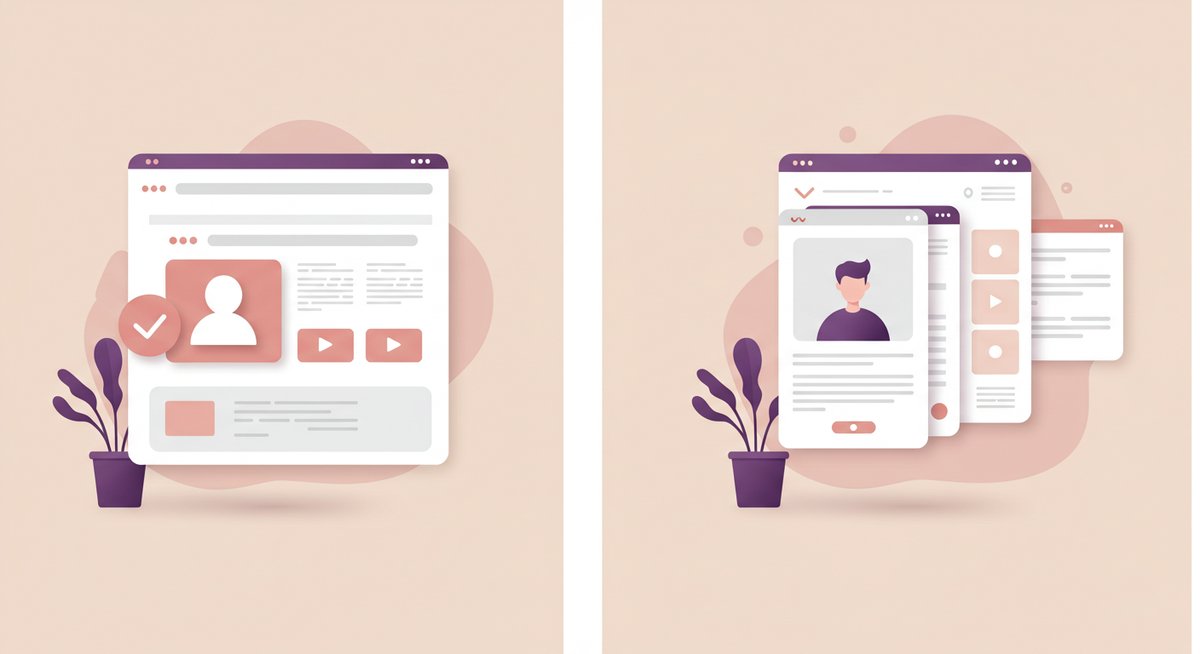
ランディングページでの典型的な傾向
ランディングページは新規流入が多く、直帰率が高めに出ることが一般的です。特に検索流入で「答えを一目で知りたい」ユーザーが来る場合、ページが要点を短時間で伝えられないと直帰につながります。改善ポイントとしては見出しの明確化、ファーストビューでの要約、適切なCTA配置が有効です。
また、ランディング広告からの流入では期待値が高いため、広告文とページ内容の整合性がとれていないと直帰率が跳ね上がります。流入元ごとのランディングページ最適化を行うと効果が出やすくなります。
記事コンテンツでの解釈例
記事ページでは直帰率が高くても、ページで求められた情報が完結していれば問題ない場合があります。しかし滞在時間が短く離脱率が高い場合は、コンテンツの質や読みやすさ、内部リンクの不足が疑われます。関連記事や目次、中見出しで導線を作り、他ページへ誘導する施策が有効です。さらに画像や表、要約を入れてスクロール継続を促すことも検討してください。
ECサイトのチェックアウトでの見方
チェックアウトや決済フローでの離脱率は直接売上に影響します。ここでの離脱はユーザーの不安(送料、支払い方法、入力負担)や技術的問題(遅延、エラー)によることが多いです。改善はフォームの簡素化、ゲスト購入対応、入力補助、信頼性表示、ページ速度改善が中心になります。離脱ポイントをステップごとに可視化して優先改善することが重要です。
カートやフォームページで示す課題
カートページや問い合わせフォームで高い離脱率が出る場合、フォーム項目の多さや入力UX、モバイルでの表示崩れが原因であることが多いです。必須項目の見直し、入力補助、エラーメッセージの明確化、進行状況バーの設置など、ユーザーの心理的負担を減らす施策を優先してください。
また、信頼性を高めるための保証表示やプライバシーポリシーの明示も有効です。
広告流入ページでの直帰率の考え方
広告からの流入はユーザーの期待値が高く、広告文とランディングページの乖離が直帰を招きやすいです。CTRと直帰率をセットで見て、広告文の見直し、ランディングページのメッセージ一致、または流入キーワードの見直しを行ってください。広告のターゲティングが広すぎる場合は流入の質が下がるため、セグメント別の着地ページを用意することも効果的です。
誤った解釈でやりがちなミス
よくある誤りは「直帰率だけを見て改善する」ことや「離脱率が高い=必ず悪」と決めつけることです。ページの役割や流入元、滞在時間やコンバージョンの文脈を無視すると的外れな施策になります。GA4移行後は指標の定義が変わる点も見落としやすいので、比較時は注意が必要です。数値の変動が見られたら、イベントやトラッキング設定の確認も行ってください。
直帰率と離脱率を下げる具体的なテクニック集

ファーストビューで伝えるべき情報
ファーストビューは訪問後数秒で判断されるため、要点を簡潔に伝えることが重要です。具体的には次を明確に示してください。
- ページの主旨(何が得られるか)
- CTAの位置と目的
- 信頼を示す要素(実績やレビューの抜粋)
視覚的には大きめの見出しと簡潔なサブコピー、目を引くCTAを用意し、スクロールを促す導線を作ると直帰抑制につながります。
ページ表示速度を優先的に改善する項目
速度改善は離脱低減に直結します。優先度の高い対策は以下です。
- 画像の最適化(遅延読み込み、適切なフォーマット)
- JavaScriptの軽量化と遅延読み込み
- キャッシュ設定とCDNの導入
これらを実施することでモバイルでの離脱を効果的に減らせます。
内部リンクと導線で回遊を促す方法
記事下やサイドバーに関連コンテンツを表示するだけでなく、文中で自然に関連記事へ誘導することが重要です。おすすめの手法:
- 関連記事の選定を自動化して適切に表示
- 次に読むべきコンテンツへの明確な提案(例:初心者向け→上級者向け)
- パンくずやカテゴリーナビでページ間の辿りやすさを向上
これらでページビューと滞在時間の改善が期待できます。
モバイルでの見せ方と操作性の改善
モバイルは操作性が成否を分けます。対応ポイント:
- ボタンやリンクは指で押しやすいサイズにする
- モバイルファーストのレイアウトで不要な要素を省く
- フォームは一画面あたりの項目を減らしオート入力を活用
モバイルでの離脱を減らすと全体のCVRも向上します。
CTAとコンバージョン導線の最適化
CTAは目的に合わせて色・文言・配置を最適化します。効果的な方法は次の通りです。
- 具体的な行動を示す文言(例:「資料をダウンロード」)
- ファーストビューとスクロール後の両方にCTAを設置
- 不安要素(料金や無料の明記)を近くに表示
これによりクリック率と次工程への遷移が改善します。
ABテストで検証する実務手順
ABテストの基本手順:
- 仮説設定(何をどの程度改善したいか)
- KPIと検証期間の設定
- サンプルサイズを見積もり実施
- 結果を統計的に検証し有意なら本番導入
仮説は小さく分けて複数回検証すると学習が早く進みます。
改善すべきページの見つけ方と優先順位付け
コンバージョンに直結するページの探し方
まずGAでコンバージョン経路を可視化し、どのページが流入経路や転換経路に関わっているかを確認します。売上やリード獲得に直結するページを抽出し、そのページの直帰率や離脱率を優先的に分析します。収益影響が大きいページほど改善優先度を高く設定してください。
滞在時間と流入元で分けたセグメント分析
滞在時間や流入元(検索、広告、SNSなど)でセグメント分けすると具体的な問題が見えやすくなります。例えば検索流入は滞在時間が短い傾向があるため、要約を強化する対応が有効です。広告流入では広告文と着地の整合性をチェックします。セグメント別に改善施策を設計すると効果が出やすくなります。
定量指標と定性調査を組み合わせる方法
定量データ(直帰率・離脱率・滞在時間)だけでなく、ヒートマップやユーザーテスト、アンケートで定性情報を集めると原因が明確になります。例えばフォーム離脱が多い場合はヒートマップで離脱ポイントを特定し、ユーザーテストで実際の入力における課題を把握します。両者を組み合わせて仮説検証を行ってください。
GA4でのレポート作成とダッシュボード設計
GA4では探索レポートを使ってセグメント別の直帰・離脱分析を行います。重要なのは以下の項目をダッシュボード化することです。
- ランディング別直帰率
- 主要ページの離脱率
- 流入チャネル別エンゲージメント率
これにより日常的なモニタリングが容易になり、早期に異常を検知できます。
外部ツールを使った詳細な行動分析
ヒートマップ(クリック・スクロール)、セッションリプレイ、フォーム解析ツールを活用すると、ページ上で何が起きているかを視覚的に把握できます。これらは定量データだけでは見えないUX課題を発見するのに有効です。導入時は計測対象ページを絞り込み、プライバシー配慮の設定を行ってください。
改善効果を継続的に追跡する計測ルール
改善後は必ず計測ルールを決めて追跡します。推奨ルール:
- 主要KPIと追跡期間の明確化
- 変更点ごとにタグやイベントで識別
- 定期的(週次・月次)のレビューとレポート化
これにより改善の再現性が担保され、長期的な最適化サイクルが回せます。
今すぐ取り組める改善優先チェックリスト
- トラフィックとCV貢献度の高いページを上位10で抽出する
- ランディングページのファーストビューで要点とCTAを明確化する
- 主要ページの画像最適化と遅延読み込みを実施する
- カート/フォームの必須項目を見直し、入力負担を減らす
- 流入元ごとにランディングページのメッセージ整合を確認する
- GA4で重要イベントとコンバージョンを正しく設定する
- ヒートマップでユーザー行動を可視化し、離脱ポイントを特定する
- 小さなABテストを回し、効果のある改善のみを本実装する
- 改善ごとに計測ルールを設定し、週次で結果をレビューする
まずは上から順に3つを実行して状況を把握し、効果が見えたら残りの項目へ進めてください。









