冗長表現の例を知り文章が伝わるコツを身につけよう

冗長表現の基本とその例を理解しよう
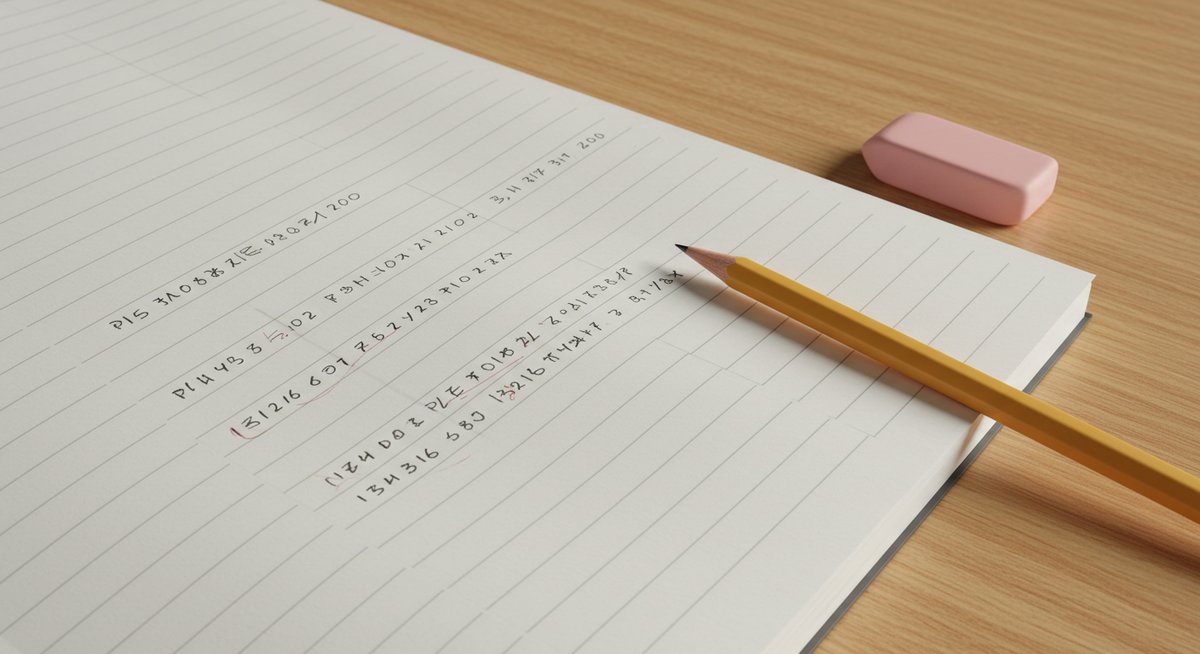
文章をわかりやすく伝えるためには、無駄な言葉を省くことが大切です。ここでは冗長表現の基本やその例について紹介します。
冗長表現とは何か
冗長表現とは、本来伝えたい内容以上の言葉を重ねてしまい、文章が長くなったり分かりにくくなったりする表現のことです。たとえば「後でまた連絡します」は、「後で」と「また」の意味が重なっています。必要以上に同じ意味や内容を繰り返すことで、読む側にとって理解しにくい文章になりやすいのが特徴です。
冗長な表現は、文章のプロでも無意識に使いがちです。また、丁寧に伝えようとするあまり、気づかないうちに言葉が増えてしまうこともあります。このような言葉の重なりをなくすことで、スッキリとした伝わりやすい文章を目指せます。
代表的な冗長表現の具体例
実際によく使われている冗長表現には、どのようなものがあるのでしょうか。以下の表に、代表的な例と、簡潔に直した表現をまとめました。
| 冗長表現 | 簡潔な表現 |
|---|---|
| あらかじめ事前に | 事前に |
| まず最初に | 最初に |
| 必ずしも〜とは限らない | 〜とは限らない |
このような表現は、知らず知らずのうちに使ってしまうことがあります。文章を書く際には、一度見直してみるとよいでしょう。余分な言葉を減らすことで、文章全体がすっきりし、伝えたい内容が読み手にストレートに届きやすくなります。
つい使いがちな冗長表現の傾向
日常会話やビジネス文書では、「念のため再度」「現在進行中」など、つい使いたくなる冗長なフレーズが存在します。これらは、意味を強調したいときや丁寧さを表現したいときに無意識に使われやすい傾向があります。
また、慣用句や言い回しのクセでも冗長表現が入り込みやすくなります。たとえば「一番最初」「元に戻す」など、慣れ親しんだ言葉こそ注意が必要です。文章を書くときは、伝えたい内容をシンプルに表現できるか意識してみると良いでしょう。
冗長表現が文章にもたらす影響
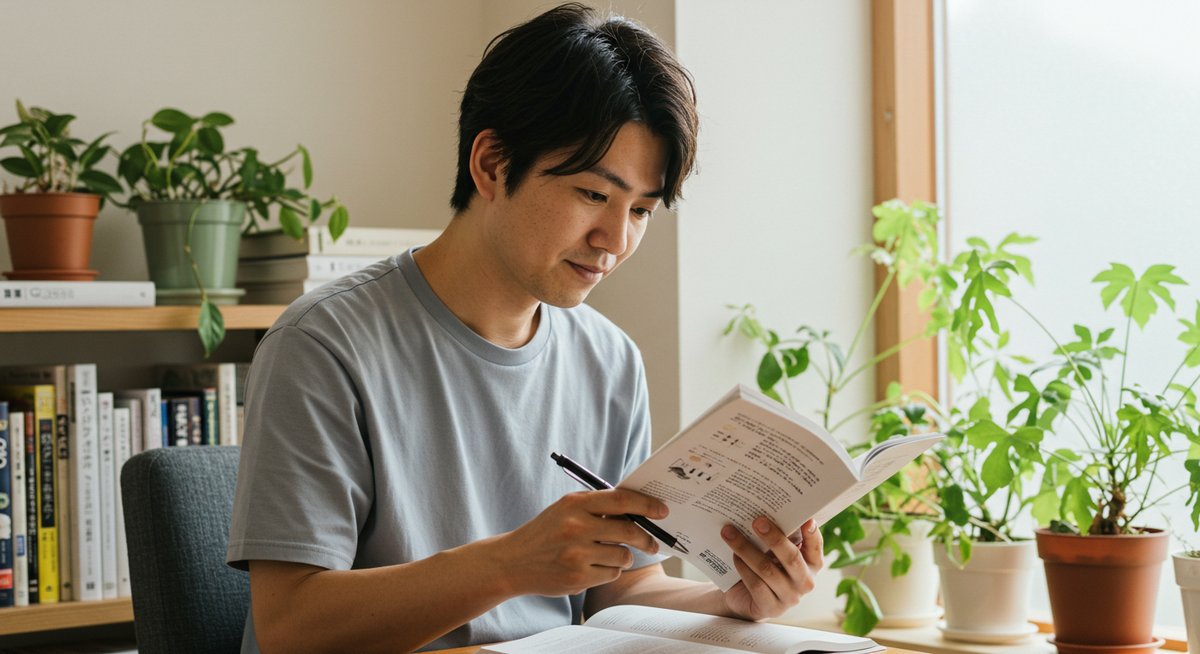
冗長表現が多いと、読み手に伝わりにくくなったり文章全体の印象がぼやけたりすることがあります。ここではその理由や影響について解説します。
読者に伝わりにくくなる理由
冗長な表現が多い文章は、情報が増えて内容がぼやけやすくなります。たとえば、「今現在の状況を詳しく説明します」は「現在の状況を説明します」で十分意味が伝わります。余計な言葉が入ることで読み手は本質をつかみにくくなります。
また、文章が長くなることで、読む側の集中力が続きにくくなります。一文が長くなりがちなので、どこがポイントか分かりづらくなるのも難点です。冗長表現を減らすことで、簡潔で分かりやすい印象に変わります。
冗長表現が与えるテンポや印象への影響
文章のテンポは、情報量が適切であるほど読みやすくなります。冗長な表現が多いと、文章が重たく感じられ、テンポが悪くなります。読むリズムが途切れると、最後まで読んでもらえないこともあります。
さらに、冗長表現が多用されると、書き手が要点を整理できていない印象を与えてしまうこともあります。読みやすい文章は、無駄な言葉がなく必要な情報だけが伝わるため、信頼感や好印象にもつながります。
冗長表現を避けるべきシチュエーション
特に注意したいのは、ビジネス文書やメール、報告書などの場面です。これらは多くの人が読むため、わかりやすさが重視されます。冗長な言い回しは内容を不明瞭にしてしまい、誤解や手戻りの原因になりやすいです。
また、プレゼン資料やウェブサイトの本文でも、スペースや時間が限られていることが多いです。読みやすく簡潔にまとめることで、相手に負担をかけずに伝えることができます。状況に応じてシンプルな表現を心掛けることが大切です。
よくある冗長表現のパターンと改善方法
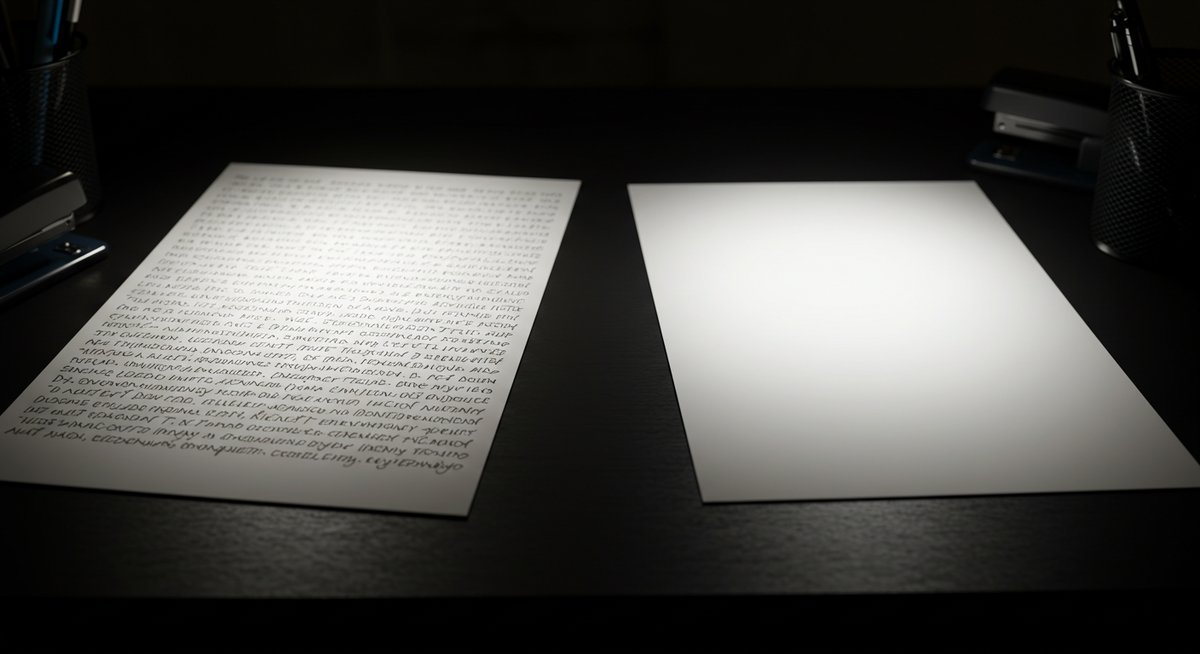
冗長表現にはいくつかのパターンがあります。ここでは重複や丁寧すぎる言い回しなどの見分け方と、改善のコツを紹介します。
重複表現や二重敬語の見分け方
重複表現は、同じ意味の言葉を重ねてしまうパターンです。たとえば「まだ未完成」といった言い回しがよく見られます。二重敬語は、「お伺いさせていただきます」など、敬語表現が重なって過剰になるケースです。
見分け方のポイントは、「意味が重なっていないか」「敬語が二重になっていないか」をチェックすることです。特に敬語は、丁寧に伝えたい気持ちからつい増えがちですが、過剰になるとかえって不自然に見えてしまうので注意が必要です。
不要な接続詞や助詞の削除ポイント
文章の中で「そして」「それから」などの接続詞が多用されると、内容がくどくなります。すべての文頭に接続詞を入れる必要はありません。接続詞を使わなくても意味が伝わる場合は、思い切って削除しましょう。
また、「~のようなものを」や「~において」などの助詞や助動詞も、無駄に長くなりやすい部分です。文章を読んでいて「意味が変わらないか」と注意しながら、不要な部分を減らすのがコツです。
一文一義を意識した簡潔な表現への書き換え
一文で複数の内容を詰め込みすぎると、長くて分かりにくい文章になってしまいます。「一文一義」を意識して、一つの文には一つの意味や要点だけを入れるようにしましょう。
たとえば、「資料を確認した後、必要ならば修正し、その後メールで送付してください」という文は、「資料を確認してください。必要なら修正してください。その後、メールで送付してください」と分けることで、より分かりやすくなります。簡潔にすることで、読み手の負担も減らせます。
冗長表現を減らす実践的なテクニック

冗長表現をなくすためには、具体的な方法を知ることが役立ちます。ここでは推敲や構成の工夫、削りすぎへの注意点を紹介します。
チェックツールや音読を活用した推敲法
文章を書いた後は、チェックツールや音読を使って見直すのが効果的です。チェックツールは冗長表現や重複した言い回しを自動で指摘してくれるので、客観的な視点で文章を整えられます。
一方、音読は自分の耳でリズムや違和感を確認できるのがメリットです。声に出して読むことで、言葉の重なりや言い回しの不自然さに気づきやすくなります。時間を置いて再度見直すことも、ミスの発見につながります。
読みやすさを高める構成の工夫
冗長表現を避けるには、文章全体の構成を工夫することも大切です。まず、伝えたい内容を箇条書きやメモに分けて整理し、要点だけを文章にまとめると、無駄が減ります。
また、段落ごとに内容を分けることで、情報のまとまりが良くなります。見出しや表を使って視覚的にも読みやすくすることで、文章全体がすっきりした印象になります。
冗長表現の削りすぎに注意するバランス感覚
冗長表現を減らすことに集中しすぎると、今度は文章がそっけなく冷たい印象になることがあります。特に、丁寧に伝えるべきビジネスメールや案内文では、必要な配慮や言葉を省かないよう注意が必要です。
大切なのは、相手や目的に合わせて「ちょうどよい長さや丁寧さ」を保つことです。内容の分かりやすさと相手への思いやり、どちらもバランスよく考える視点が求められます。
まとめ:冗長表現の例を知り簡潔で伝わる文章を目指そう
冗長表現は、知らず知らずのうちに使ってしまうことが多いものです。例や改善方法を知ることで、より分かりやすい文章を書けるようになります。
簡潔で伝わる文章を目指すには、余計な言葉を省き、要点を整理しながら書くことが大切です。推敲や読み返しを習慣にし、読み手にとって親切で分かりやすい表現を意識してみてください。









