独自ドメインに移行してアクセスが急落したときに最初に確認すべき7つのポイント
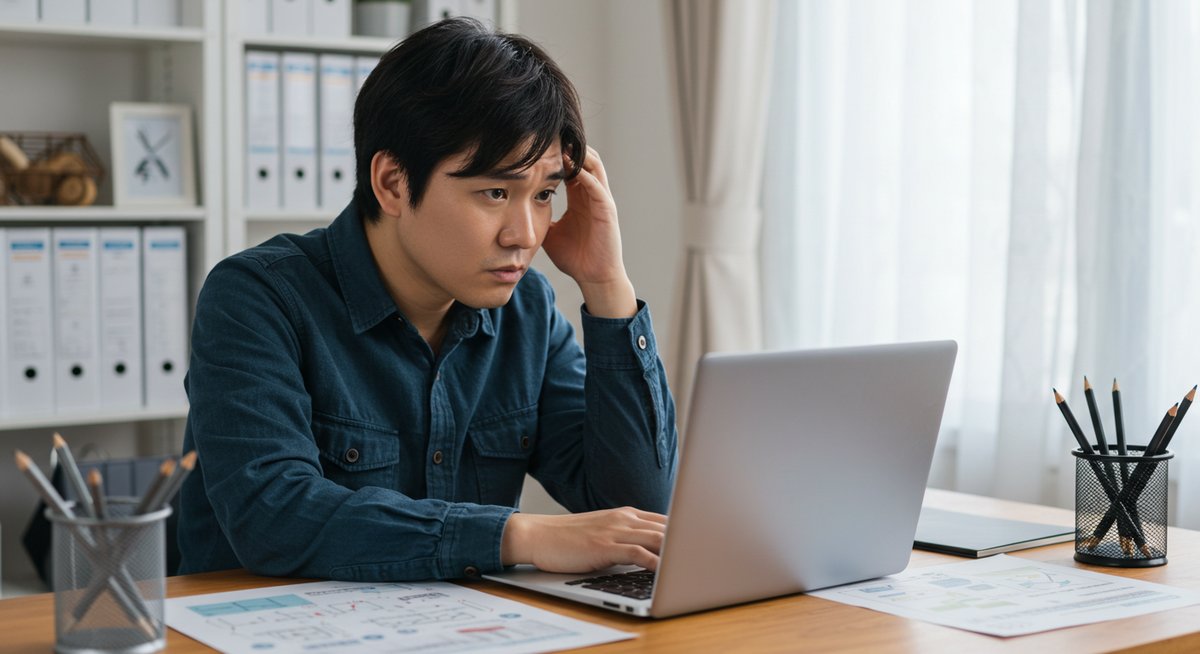
ウェブサイトを独自ドメインに移行した際、アクセス数が急に落ちると不安になります。移行作業自体は技術的なミスや設定漏れが原因になることが多く、落ち着いて確認すべきポイントを順にチェックすれば原因の特定と対処が進みます。本記事では、まず確認すべき項目と落ち着いて対応するための流れ、回復の目安、実務での具体的手順を分かりやすくまとめます。技術的な用語は平易に説明し、すぐに使えるチェックリストも載せていますので、移行後の不安を減らしていきましょう。
独自のドメインのアクセス数が急落したときにまず確認すること

移行直後はアクセス減少が一時的に起きることがありますが、放置すると長期的な流入減に繋がります。まずは慌てず、トラフィック変化の原因を絞り込むための基本項目を順番に確認してください。
一つずつ確実にチェックする順序の例を挙げます。移行直後のPV動向、旧URLからの301リダイレクト、Search Consoleの設定、XMLサイトマップの送信状況、トラッキングコードの動作などが対象です。これらは短時間で見つかる問題が多く、早期に対応すれば回復を速められます。
技術的に不安がある場合はスクリーンショットやログを保存しておくと、外部のエンジニアに依頼するときに役立ちます。また、優先順位をつけて対応することで、サイト運営に支障が出ないように進められます。
移行直後のPV変動は想定内か確認する
移行直後は検索エンジンやユーザー行動の変化でPVが上下しやすく、短期間の乱高下は必ずしも問題とは限りません。まずは過去のトレンドや同規模の移行事例と比較し、どの程度の変動が「想定内」かを把握してください。
チェックのポイントは、期間を分けて比較することです。移行直前の1週間〜1か月と、移行後の同期間を比較し、どのページ群で落ちているかを特定します。特定のカテゴリや検索クエリだけが落ちているなら技術的な問題よりコンテンツ評価の変化が原因かもしれません。
加えて、サーチコンソールやアクセス解析で被検索クエリや表示回数の変化を確認します。表示回数が大きく減っている場合はインデックスやクローリングの問題、クリック率が落ちている場合は検索結果のタイトルやスニペットが影響している可能性があります。まずは冷静にデータで状況を把握しましょう。
すべての旧URLに301リダイレクトがあるか確認する
旧URLから新URLへの301リダイレクトは最も重要な設定の一つです。個別ページごとに正しくリダイレクトされていないと、検索評価や被リンク効果が新ドメインに引き継がれません。まずは代表的なページ(上位流入のページや被リンクが多いページ)を重点的に確認してください。
確認方法はツールやcurlで旧URLにアクセスし、HTTPステータスと最終的な到達先URLを確かめます。大量のページがある場合はマッピング表と自動チェックスクリプトを用意すると効率的です。ワイルドカードリダイレクトを使う場合も、例外ルールがないかを確認してください。
誤って302リダイレクトや複数回のリダイレクトチェーンになっていると評価が減少します。301に統一し、チェーンは可能な限り短くしてください。リダイレクトが正しく設定されていても、送信ミスやサーバー設定で一部が抜けることがあるため、サンプルチェックを忘れないでください。
Search Consoleに新ドメインを登録したか確認する
新ドメインを登録していないと、Search Consoleでのエラー通知やカバレッジ確認ができず、問題の早期発見が遅れます。まずは新ドメインをプロパティとして追加し、所有権を確認してください。
Search Consoleでは、カバレッジ、モバイルユーザビリティ、セキュリティ問題などの通知を受け取れます。また、サイトマップを送信してインデックス状況を把握するためにも必要です。旧ドメインからのサイト移行ツール(Change of Address)を利用できる場合は、それも併せて実施してください。
所有権の確認が済んだら、プロパティ内のカバレッジレポートやURL検査ツールで代表ページのインデックス状況を確認します。問題が出ている場合はエラー内容に従って修正し、再検査を依頼してください。
XMLサイトマップを生成して送信しているか確認する
XMLサイトマップは検索エンジンにサイト構造を伝える重要な手段です。移行後は新しいURLだけを含む最新のサイトマップを生成し、Search Consoleに送信してください。古いサイトマップに旧URLが残っていると混乱の原因になります。
サイトマップには優先度や更新頻度を過度に設定する必要はありませんが、主要ページが漏れていないことを確認してください。動的に生成する場合は、移行直後のキャッシュや設定ミスで旧URLが混在することがあるため、内容を目視でもチェックします。
送信後はSearch Consoleのサイトマップステータスで受信・インデックス状況を確認し、エラーが出ていれば修正します。サイトマップが正しく反映されるとクロール頻度の改善につながるため、早めに対応しましょう。
トラッキングコードやタグが正しく機能しているか確認する
アクセスが減ったように見えて、実は解析ツールの計測漏れというケースもあります。Googleアナリティクスやタグマネージャー、アクセス解析のコードが新ドメインに適切に設置されているかをまず確認してください。
確認方法はリアルタイムレポートでテストページにアクセスしてイベントやページビューが計測されるかを確かめることです。サブドメインやクロスドメイン計測がある場合はCookie設定やドメイン許可、同一トラッキングIDの利用状況を確認します。
また、リダイレクトで参照元情報が消えることがあります。参照元が(unknown)やdirectに偏っていないかをチェックし、必要ならUTMパラメータやリンク元への対応を検討してください。計測環境の問題は比較的早く修正できるため、まずはここを確かめることをおすすめします。
独自ドメイン移行でアクセスが下がる理由を整理する

ドメイン移行でアクセスが下がるのは複数の要因が重なることが多く、技術面と評価面の両方を整理することが重要です。ここでは代表的な原因を分かりやすく整理します。
原因を把握する際は、検索流入、被リンク評価、内部リンク構造、解析計測の四つの観点でチェックしてください。早期に技術的問題を潰し、評価面の回復には時間がかかることを前提に対応を進めると効率的です。
ドメインパワーとドメイン年齢の影響を把握する
検索エンジンはドメインの歴史や信頼性を評価要因の一つとして扱うことがあり、新しいドメインは既存ドメインに比べて評価の反映に時間がかかることがあります。これが一因で流入が落ちることがあるため理解しておくことが大切です。
特に被リンクの評価は旧ドメインから新ドメインへ完全に引き継がれるまで時間がかかります。移行直後はドメイン年齢や過去の評価が働かないため、検索順位が一時的に下がるケースが発生します。焦らずに正しいリダイレクトと被リンク維持の取り組みを続けることが重要です。
ただし、適切に301リダイレクトやサイトマップを整備すれば、時間とともに評価は移行先に移っていきます。短期的な変動は想定の範囲として扱い、長期的なトレンドを見守る姿勢が必要です。
インデックス未反映で検索流入が途絶えるケース
新しいドメインのページが検索エンジンにインデックスされていないと、検索からの流入が激減します。Search ConsoleのカバレッジやURL検査でインデックス状況を確認し、代表ページが「未登録」になっていないか確認してください。
インデックス未反映の原因は、サイトマップ未送信、クロールの制限(robots.txtやnoindex)、サーバーエラー、重いページ読み込みによるクロール失敗などが考えられます。これらを一つずつ潰していけば、クロール頻度とインデックス数は回復します。
問題を修正したらSearch Consoleで再クロールをリクエストし、状況が改善するかを観察します。即時に反映されないこともあるため、数日〜数週間の経過観察が必要です。
重複コンテンツやcanonical設定のミス
新旧両方のドメインが同時に存在していると、同一コンテンツが重複として扱われることがあります。canonicalタグが旧ドメインを指したままだったり、両方のURLがindexableになっていると検索エンジンがどちらを優先すべきか判断できず、結果的に評価が分散します。
チェック項目は以下の通りです。
- 各ページのcanonicalが新ドメインの正しいURLを指しているか
- 旧ドメインのページがnoindexになっているか、もしくは完全に301で飛んでいるか
- 同一コンテンツが別パスで存在していないか
canonicalの誤設定は比較的見落としやすいため、サイト内の代表ページで必ず確認してください。
アナリティクスや参照元が分散して見える問題
移行に伴いトラッキング設定が分かれてしまうと、本当のトラフィックが正確に見えなくなります。たとえば、旧ドメインと新ドメインで別々のプロパティにデータが入っていると総流入が分散して見え、実際のユーザーは減っていないのに「アクセスが減った」と誤認することがあります。
参照元情報が消えるケースも注意点です。リダイレクトやリンクの貼り替えでUTMが消えたり、外部リンクのリファラーが切れるとオーガニック/リファーラルトラフィックの内訳が変化します。解析ツールを統合し、参照元ごとの計測を整理して事実を正確に把握してください。
アクセスが回復するまでの期間の目安と見方

移行後の回復期間はケースバイケースですが、一般的な目安と見方を押さえておくと安心して対応できます。短期的な対応と長期的な経過観察を両立させましょう。
基本的には技術的問題を速やかに解決し、インデックスと評価の移行には時間を要する点を念頭に置いてください。焦らずデータを定期的に確認し、改善を継続することが重要です。
移行直後の数週間は順位が上下しやすい
移行直後の数週間は検索順位や表示回数が乱高下しやすく、一部のキーワードで大きく上下することがあります。検索エンジンは新しいドメインの評価を試験的に変動させながら適正な順位を決める傾向があるためです。
この期間は短期的な順位の上下に一喜一憂せず、問題が技術的なミスによるものか評価の変動によるものかを見極めてください。技術的ミスがない場合は、データを日次・週次で追いながら安定化を待つのが現実的です。
半年から一年で評価が安定することが多い
多くのケースで、被リンク評価やドメイン信頼の移行が完了し、検索評価が安定するまでに数か月から一年程度かかります。特に大規模サイトや被リンクが多いサイトでは時間がかかる傾向にあります。
この期間中は、コンテンツの質を維持しながら被リンクの修正や内部施策を継続することが効果的です。定期的にSearch Consoleや解析データでトレンドを確認し、回復傾向が見えるかをチェックしていきます。
トレンド系や速報性の高い記事は例外的に早く回復する
ニュース性やトレンド性の高いコンテンツは、検索エンジンによるインデックスが早く、流入が比較的速く戻る傾向があります。これは頻繁にクロールされるためで、コンテンツの性質によって回復速度が異なることを理解しておいてください。
そのため、重要な速報記事やトレンド記事は移行時に特に優先して確認し、301リダイレクトやインデックス状況を早めに整えることで回復を早められます。
被リンクやSNS流入が回復を早める要因になる
外部からの流入源が早期に新ドメインへ戻ると回復が加速します。被リンクのアンカーテキストやリンク先が新URLに更新されれば、検索エンジンの評価移行もスムーズになります。
実務的には主要な被リンク元に連絡してリンク先の更新を依頼する、SNSでの告知を行い直リンクを増やすなどの施策が有効です。こうした外部施策は評価回復のスピードアップに直結しやすいため、移行後は並行して実施することをおすすめします。
実務で行う具体的な改善手順とチェックリスト

ここからは実務的にすぐ使える具体的手順をチェックリスト形式で示します。順番に実行し、状況を確認しながら進めてください。各項目は重要度が高いものから並べています。
リストは現場での作業優先度に沿っています。まずは致命的な設定ミスを潰し、その後で最適化や外部対応を進めると効率的です。
旧URLと新URLのマッピングを正確に作る
正確なマッピング表は移行作業の基盤です。旧URLと新URLの対応表をCSVやスプレッドシートで作成し、上位流入ページや被リンクがあるページを優先的にリストアップしてください。
マッピングにはステータス(301済み、未設定、要確認)や備考(例:構造変更あり)を含めると管理が楽になります。評価の高いページが漏れないよう、被リンクツールで外部リンクの多いURLも抽出してマップに入れてください。
全ページに対して正しい301リダイレクトを設定する
マッピングに基づき、旧URLから新URLへ301リダイレクトを一括または個別に設定します。サーバー設定やCDN、アプリケーションレベルでの実装方法を確認し、302やリダイレクトチェーンになっていないかテストします。
実装後はランダムに複数ページをチェックし、HTTPステータスと最終到達先を確認してください。自動化ツールで全URLを検証すると抜け漏れが見つかりやすくなります。
内部リンクとパンくずのURLをすべて更新する
サイト内部のリンクが旧URLのままだとユーザーとクローラー双方に悪影響を与えます。CMSのテンプレート、記事内リンク、ナビゲーション、パンくずリストなどを新URLに書き換えてください。
検索順位の評価移行を早めるために、内部リンクから新ドメインのURLへ直接飛ぶようにすると理想的です。変更後はサイト内でリンク切れがないかをサイト監査ツールでチェックします。
canonicalとhreflangの指し先を確認して修正する
各ページのcanonicalタグが新ドメインを指しているかどうかを確認します。間違って旧ドメインを指していると評価が旧ドメインに留まり、新ドメインの順位が上がりません。
多言語サイトではhreflangの設定も重要です。各言語版が正しいドメインとURLを示しているかを検証し、必要なら一括修正してください。
robots.txtで重要ページをブロックしていないか確認する
移行時にrobots.txtで誤ってクロールを制限していると、検索流入が途絶えます。robots.txtの内容を確認し、重要なディレクトリやページがDisallowされていないかをチェックしてください。
また、開発用の設定が本番に残っていないか、ステージング向けの制限が残っていないかも併せて確認します。問題があれば即時修正し、Search Consoleでクロール可能性を再確認します。
Search Consoleでカバレッジやエラーを定期確認する
Search Consoleのカバレッジ、モバイル、セキュリティ、検索パフォーマンスの各レポートを定期的にチェックしてください。エラーや警告が出たら優先順位をつけて対応します。
特にカバレッジのエラー(404、サーバーエラー、noindex混在など)は早期対応が必要です。修正後は検証リクエストを送り、改善が反映されるかを確認します。
被リンク元に移行の連絡やリンク修正を依頼する
重要な被リンク元には個別に連絡し、リンク先を新URLに更新してもらうよう依頼します。特に大手メディアやパートナーサイト、主要ディレクトリのリンクは優先度が高いです。
依頼する際は、新旧両方のURLと更新理由を明確に伝え、操作が簡単になるように具体的なリンク情報を提供してください。多数ある場合は、被リンクの優先順位をつけて順次対応します。
サイト表示速度やモバイル対応を最適化する
ページ表示速度やモバイルフレンドリー性は検索順位に影響するため、移行後に改めて最適化を行ってください。画像の最適化、キャッシュ設定、不要なスクリプトの削除などの基本施策が効果的です。
モバイル対応は特に重要で、モバイルファーストの評価基準に則って問題がないかを確認します。改善点が見つかったら優先順位をつけて実行し、改善効果を計測します。
独自ドメインに移行したあとは手順を着実に実行して回復を目指す
ドメイン移行後は焦らず、上で挙げたチェック項目を順に潰していくことが最も確実な回復策です。技術的な設定漏れを早期に修正し、Search Consoleや解析ツールでの長期的なモニタリングを続けてください。
同時に、被リンク修正やSNSでの告知、コンテンツの品質維持など評価を高める施策を並行して進めると回復が早まります。時間がかかる場合でも、一つずつ着実に対応を続ければ、アクセスは徐々に戻ってきます。









